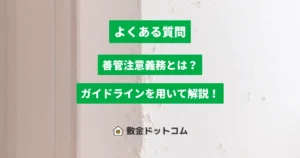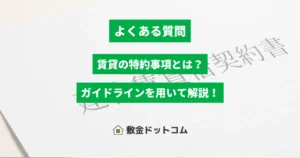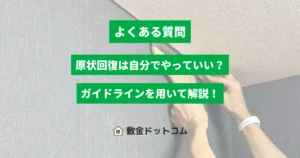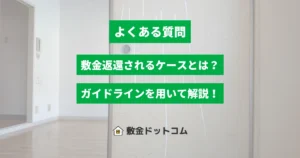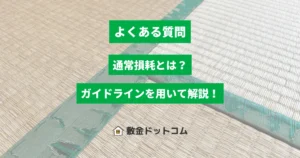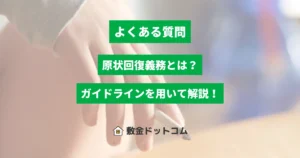賃貸借契約書で定められた損害賠償額は支払わなければならない?原状回復のガイドラインを用いて解説
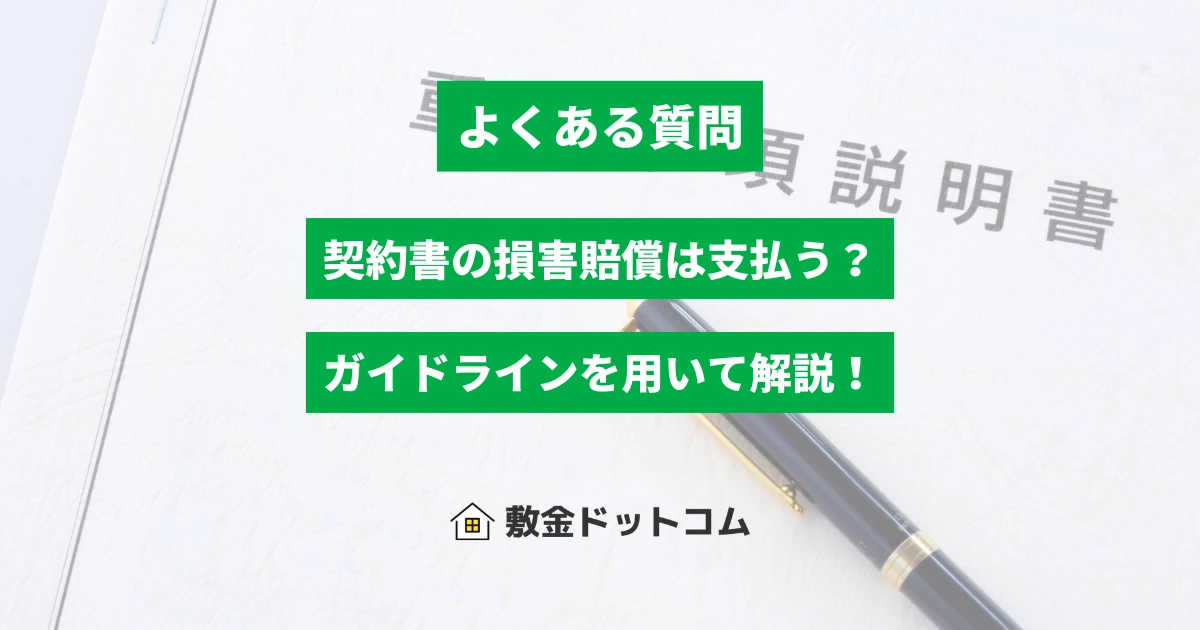
賃貸借契約書には、退去時の原状回復や損害賠償についての条項が記載されていますが、実際にトラブルになった際、「本当にこの金額を支払わなければならないのか?」と疑問に思う方は多いでしょう。
特に、大家さんから高額な請求を受けた場合、法的に正当なのか判断に迷います。
この記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に、契約書の損害賠償条項の法的効力や支払い義務の範囲を解説します。
この記事を読むことで、不当な請求を見極める方法や適正な原状回復の基準が分かり、トラブル回避や適切な対応ができるようになります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
基本概念の説明
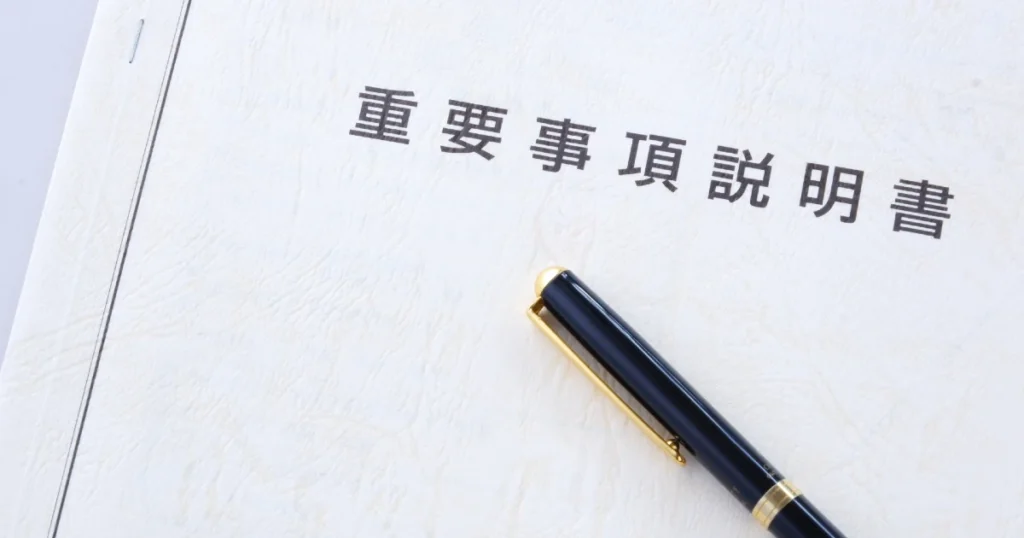
賃貸借契約書の損害賠償条項は、借主が退去時に部屋を原状回復する際のルールを定めたものです。
ただし、契約書に記載されているからといって、すべての請求が法的に有効とは限りません。
国土交通省のガイドラインでは、「経年劣化」と「借主の故意・過失による損傷」を明確に区別するよう定めています。
経年劣化は大家さんの負担であり、借主が賠償する必要はありません。
また、損害賠償額が不当に高額な場合、消費者契約法の「不当条項」に該当し無効になる可能性もあります。
重要なのは、契約内容と実際の損傷の原因・程度を照らし合わせ、法的な合理性を判断することです。
トラブル回避のための実践的アドバイス
実際に退去時に大家さんから損害賠償を請求された場合、以下のポイントに注意して対応しましょう。
- 修理費の内訳や損傷の写真を要求し、経年劣化と故意・過失の区別が正しいか検証する
- 国土交通省の「原状回復ガイドライン」で、壁紙の汚れやフローリングの傷など、具体的な基準を確認する
- 不当な請求の場合、大家さんと直接交渉するか、自治体の相談窓口や弁護士に助言を求める
特に注意が必要なのは、経年劣化分を含んだ全額請求や、相場よりも明らかに高額な修理費、さらに契約書に記載のない不明確な費用を求められた場合です。
これらの請求は、国土交通省のガイドラインに照らして不当である可能性が高く、借主が過剰な負担を強いられるリスクがあります。
経年劣化は大家の負担範囲であり、修理費も適正な相場に基づいているか、契約書で明確に定められた費用かどうかを慎重に確認する必要があります。
関連記事:賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
まとめ
賃貸借契約書の損害賠償条項は、すべてのケースで支払い義務が生じるわけではありません。
重要なのは、請求内容が「原状回復ガイドライン」に照らして適正かどうかを判断することです。
経年劣化と借主の責任を明確に区別し、不当な請求には根拠をもって対処しましょう。
トラブルを防ぐためにも、入居時と退去時に部屋の状態を写真で記録し、契約書の内容を事前に確認しておくことが大切です。
適切な知識を持てば、不要な支出や紛争を避けられます。