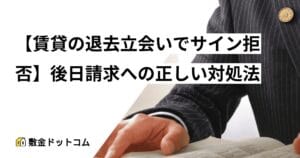【敷金が返ってくる割合は69%】貸主が敷金を返すまでの流れ
賃貸住宅の退去時に気になるのが、敷金の返還問題です。
実際の調査データによると、東京では敷金が100%返還される割合はわずか12%で、平均返還率は42%にとどまり、約3割の人が敷金を全く返してもらえないという厳しい現実があります。
多くの借主が2ヶ月分の敷金を支払っているにもかかわらず、実際に返還されるのは1ヶ月分にも満たないケースが多いのが実情です。
この記事では、敷金返還の実態と貸主が敷金を返すまでの具体的な流れ、さらにトラブルを避けるための事前準備について、行政書士の視点から詳しく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金の返還率はどのくらい?
賃貸住宅の敷金返還について理解するためには、まず現状の返還率を把握することが重要です。
東京の敷金返還率の厳しい現実
リクルート住宅総研の調査によると、東京では敷金が100%返還された割合はわずか12%という驚くべき結果が出ています。

- 100%返還:わずか12%
- 0%(全く返還されない):31%
- 平均返還率:42%
- 2ヶ月分の敷金のうち1ヶ月分も返ってこない
- 特段修繕をしなくても敷金の約半分は差し引かれる
これは非常に深刻な状況で、借主の約3人に1人が敷金を全く返してもらえず、完全に返還される人は10人に1人程度という現実があります。
世帯人数別の返還率の違い
同調査によると、世帯人数によっても敷金の返還率に違いが見られます。
| 世帯人数 | 100%返還割合 | 平均返還率 |
|---|---|---|
| 1人世帯 | 約14% | 約43% |
| 2人世帯 | 約11% | 約41% |
| 3人以上世帯 | 約10% | 約39% |
世帯人数が多くなるほど敷金の返還率が下がる傾向があり、家族での居住期間が長いほど、原状回復費用の負担が重くなることがわかります。
これらの数字は借主にとって厳しい現実ですが、適切な知識と準備により改善は可能です。
敷金が返ってこない理由とは?
なぜ日本では敷金の返還率がこれほど低いのでしょうか。その背景には複数の要因があります。
日本特有の原状回復ルール
日本の賃貸住宅では「壁に釘の1本も打てない」という不文律があります。
国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によれば、壁等のくぎ穴・ネジ穴で下地ボードの張替えが必要な程度のものは原状回復が必要とされています。
しかし、実際にはルールが拡大解釈され、画鋲やピンですら打つことをためらう借主が少なくありません。
カレンダーやポスターを貼ることですら躊躇してしまう状況があります。
曖昧な費用負担の境界線
原状回復ルールの曖昧さが敷金返還率の低さに大きく影響しています。


- 賃貸はとにかく触ってはいけないという暗黙の了解
- 画鋲やピンですら使用をためらう借主心理
- 何もしなくても敷金の約半分は原状回復名目で差し引かれる実態
- 礼金や更新料など「何に対する費用か」が曖昧な制度
- 業界慣行として正当性が主張される不透明な費用負担
この曖昧さが借主の不利益につながり、敷金返還率の低下を招いています。
借主の知識不足
多くの借主が原状回復に関する正しい知識を持たないまま契約し、退去時になって初めて高額な原状回復費用を請求されるケースが後を絶ちません。
国土交通省のガイドラインでは通常の使用による損耗は借主負担ではないとされているにもかかわらず、この事実を知らない借主が多いのが現状です。
正しい知識を身につけることで、不当な費用負担を避けることができます。
貸主が敷金を返すまでの具体的な流れ
敷金返還までの流れを把握しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
退去から敷金返還までのタイムライン
一般的な敷金返還の流れは以下のようになります。


- 退去立会い(当日):部屋の状況確認と記録
- 原状回復工事の見積もり(1〜2週間後)
- 敷金精算書の作成・送付(3〜4週間後)
- 借主への説明・同意確認(必要に応じて)
- 敷金返還(通常1〜2ヶ月以内)
退去立会いでのポイント
退去立会いは敷金返還の基準を決める重要な機会です。
この時点で部屋の状況をしっかりと記録し、貸主との認識を合わせることが後のトラブル防止につながります。
立会い時に確認すべき項目は、壁紙の汚れや傷、床の傷、設備の動作状況、鍵の返却などです。疑問点があれば遠慮なく質問し、可能であれば写真撮影も行いましょう。
敷金精算書の内容確認
貸主から送付される敷金精算書には、原状回復費用の内訳が詳細に記載されています。
国土交通省のガイドラインに基づき、通常の使用による損耗や経年変化については借主の負担とならないことを確認することが重要です。
精算書で確認すべき項目には、クリーニング費用の妥当性、修繕費用の詳細、経年劣化と故意・過失の区別などがあります。不明な項目については必ず説明を求めてください。
精算書に疑問がある場合は、まず貸主に説明を求め、納得できない場合は専門家への相談を検討してください。
敷金返還トラブルを防ぐための事前準備
敷金返還トラブルを避けるためには、入居時からの準備が欠かせません。
入居時の状況記録
入居時に部屋の状況を詳細に記録しておくことで、退去時の原状回復範囲を明確にできます。


- 壁紙の汚れや傷の写真撮影(日付入り)
- 床やカーペットの状況記録
- 設備の動作確認と記録
- 貸主との立会い確認書の保管
- 契約書の原状回復条項の詳細確認
契約内容の十分な理解
賃貸借契約書の原状回復に関する条項を入居前にしっかりと確認することが重要です。
特に「通常の使用による損耗」と「借主の故意・過失による損耗」の区別について理解しておくことで、後のトラブルを防げます。
契約書に記載されている原状回復の範囲が国土交通省のガイドラインと矛盾していないか、特約事項に不当な内容が含まれていないかも重要なチェックポイントです。
居住中の適切な管理
居住中の適切な管理も敷金返還率を高めるポイントになります。
定期的な清掃、換気による湿気対策、設備の正しい使用、小さな破損の早期対応などを心がけることで、退去時の原状回復費用を最小限に抑えることができるでしょう。
特に水回りのカビ対策、結露防止、喫煙による汚れの防止などは、原状回復費用に大きく影響する要素です。
日常的な管理は敷金返還だけでなく、快適な居住環境の維持にもつながります。
トラブル発生時の対応方法
万が一敷金返還でトラブルが発生した場合の対応方法についても知っておきましょう。
まずは冷静な話し合いを
トラブルが発生した際は、まず貸主との冷静な話し合いを心がけることが大切です。
国土交通省のガイドラインを基に、具体的な根拠を示しながら説明することで、多くの場合は円満に解決できます。
感情的にならず、事実に基づいた冷静な議論を心がけることが重要です。必要な書類や写真などの証拠を整理して臨みましょう。
専門家への相談
話し合いで解決しない場合は、専門家への相談を検討してください。


- 消費生活センター:無料相談窓口
- 行政書士:契約書の確認や書面作成支援
- 認定司法書士:簡易裁判所での代理業務
- 弁護士:複雑な法的手続きや訴訟対応
- 不動産適正取引推進機構:業界団体の相談窓口
複雑な法的手続きが必要な場合は、認定司法書士や弁護士への相談をお勧めします。
調停や訴訟以外の解決方法
法的手続きに進む前に、以下のような解決方法も検討できます。
宅地建物取引業協会による苦情相談、不動産業者の加盟する業界団体への申し立て、賃貸住宅管理業者登録制度を活用した相談などがあります。
争いごとを避け円満解決を目指すことで、時間と費用の節約にもつながります。
まとめ
敷金返還は賃貸住宅において避けて通れない重要な問題です。
現在の東京では敷金の平均返還率が42%と低い状況ですが、適切な知識と準備により、返還率を高めることは十分可能です。
入居時の状況記録、契約内容の十分な理解、居住中の適切な管理、退去時の冷静な対応など、各段階での準備が重要になります。
約3割の人が敷金を全く返してもらえない現状を踏まえ、借主として正当な権利を守るためにも、国土交通省のガイドラインを正しく理解し、適切な対応を心がけることが大切です。
トラブルが発生した場合は、まず冷静な話し合いを心がけ、必要に応じて専門家への相談を検討してください。
争いごとを避け、円満な解決を目指すことが、借主と貸主双方にとって最良の結果をもたらすでしょう。
- 東京の敷金100%返還率はわずか12%、平均返還率は42%
- 約3割の借主が敷金を全く返してもらえない厳しい現実
- 入居時の状況記録と契約内容の理解がトラブル防止の鍵
- 居住中の適切な管理で原状回復費用を最小限に抑制
- トラブル発生時は冷静な話し合いと専門家相談を検討