経年劣化を踏まえた賃借人の負担割合と敷金返還への影響
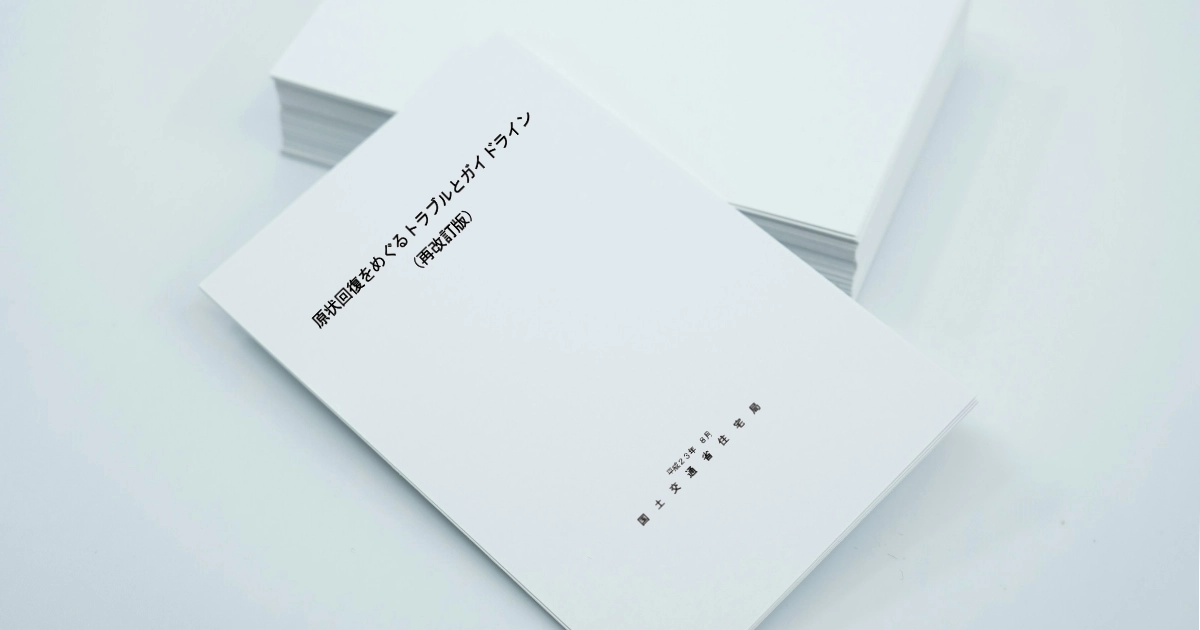
賃貸借契約における原状回復(元の状態に戻すこと)義務では、賃借人の過失による損傷と経年劣化(時間が経って自然に古くなること)による自然損耗の区別が重要な争点となります。
特に長期間の賃貸借では、退去時の損耗が通常使用の範囲内なのか、賃借人の責任によるものなのかの判断が複雑になります。
今回ご紹介する東大阪簡易裁判所平成15年1月14日判決は、賃借人の過失を認めつつも、経年劣化による減価を適切に考慮した画期的な判例です。
この事例では、子供の落書きという明確な過失があったにも関わらず、57か月という賃借期間における自然損耗を数値化して負担額を算定しました。
本記事では、この判例の詳細な分析を通じて、経年劣化と特別損耗の適正な区分方法と、実務上の対策について解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
概要
本事例は、平成9年5月から平成14年2月まで約57か月間継続した賃貸借契約における原状回復費用の負担を巡る争いです。
月額賃料9万3000円、敷金(入居時に預ける保証金)27万9000円の条件で締結された契約で、退去後に発見された壁クロス(壁紙)の落書きや床カーペットの汚損が争点となりました。

- 賃借期間
平成9年5月〜平成14年2月(約57か月) - 月額賃料
9万3000円 - 敷金
27万9000円 - 争点となった損耗
壁クロスの落書き・破損、床カーペットの汚損
賃貸人は、原状回復費用として35万6482円と延滞賃料等5万6588円の合計額を主張し、敷金を充当してもなお13万4070円が不足するとして追加請求を行いました。
これに対して賃借人は、子供の落書きによる損傷は認めるものの、経年劣化を考慮すれば負担額は3320円に過ぎないと反論し、敷金の大部分の返還を求めました。
本件では、明確な過失行為がある中で、いかに経年劣化による減価を考慮するかが主要な争点となりました。
契約内容と特約の詳細
本件賃貸借契約書には、賃借人の修繕負担を定める明確な特約が設けられていました。

- 賃貸借契約の基本条件
- 賃借期間:平成9年5月〜平成14年2月(57か月間)
- 月額賃料:9万3000円
- 敷金:27万9000円(賃料の3か月分)
- 修繕負担に関する特約
- 「畳の表替え又は裏返し、障子又は襖の張替え、壁の塗替え又は張替え等は賃借人の負担とする」
契約書の特約は比較的簡潔で、畳・障子・襖・壁等の修繕を賃借人負担とする内容でした。
この特約の特徴は、具体的な部位を明示している一方で、通常損耗(普通に使っていてできる傷み)と特別損耗の区別や経年劣化による減価について言及していない点です。
賃貸人が主張した原状回復項目は、壁クロスの張替え、床カーペットの張替え、畳の表替えなど、特約に含まれる範囲でした。
しかし、57か月という長期間の使用を経た物件において、これらの損耗がすべて賃借人の責任によるものかが争点となりました。
敷金27万9000円に対して35万円を超える原状回復費用の請求は、経年劣化を考慮しない算定方法の問題点を浮き彫りにしました。
賃貸人・賃借人の主張のポイント
本件では、損耗の原因と負担額の算定方法について、当事者間で大きく見解が分かれました。
| 争点 | 賃貸人側の主張 | 賃借人側の主張 |
|---|---|---|
| 損耗の原因 | 壁クロスの落書き・破損、床カーペットの汚損はすべて賃借人の責任 | 子供の落書き(11㎡部分)のみが過失、その他は通常使用による自然損耗 |
| 負担額の算定 | 原状回復費用35万6482円+延滞賃料5万6588円 | 経年劣化考慮後の負担額3320円のみ |
| 経年劣化の扱い | – | 57か月経過で残存価値28.75%を主張 |
賃貸人は、退去後の物件に「壁クロスに多数の落書き・破損、ビス穴等があり、床カーペットには多数の汚損があった」として、これらを賃借人の通常使用を超える損耗と主張しました。
一方、賃借人側は具体的な反論として、損耗の大部分は57か月間の通常使用による経年変化であり、自らの責任は子供の落書きをした11㎡部分のみであると主張しました。
特に重要なのは、賃借人が経年劣化による減価率を数値化し、クロスの残存価値(古くなっても残る価値)を28.75%として、実際の負担額を3320円と算定した点です。
この主張は、入居時新品のクロスであっても、57か月経過により大幅に価値が減少しているという減価償却(時間とともに価値が下がること)の概念に基づいています。
裁判所の判断と法的根拠
裁判所は、経年変化と通常使用による減価を重視した明確な判断を示しました。
| 判断項目 | 裁判所の認定 | 結論 |
|---|---|---|
| 過失による損害 | 賃借人の自認する過失(子供の落書き)は存在 | この部分のみ賃借人負担 |
| その他の損耗 | 経年変化及び通常使用によって生ずる減価の範囲のもの | 賃借人負担の対象外 |
| 延滞賃料 | 争いのない事実として認定 | 敷金から控除 |
| 最終判断 | 賃借人の請求に理由あり | 敷金21万9092円の返還を認める |
裁判所の判断で最も重要なのは、「賃借人の自認する過失(子供の落書き)による損害及び争いのない延滞賃料等を除くと、賃貸人が原状回復費用として請求する金額は、経年変化及び通常使用によって生ずる減価の範囲のもの」との認定です。
この判断により、明確な過失行為(子供の落書き)があっても、その他の損耗については57か月という長期間の使用による自然損耗として扱われました。
結果として、賃貸人の35万円を超える請求は大部分が棄却され、賃借人の敷金返還請求21万9092円が全面的に認容されました。
この判決は、経年劣化を数値化して負担額を算定する賃借人の手法を支持し、原状回復費用の適正な算定基準を示した重要な判例となりました。
判例から学ぶポイント
この判例は、経年劣化の考慮と負担額の適正算定に関する重要な指針を示しました。
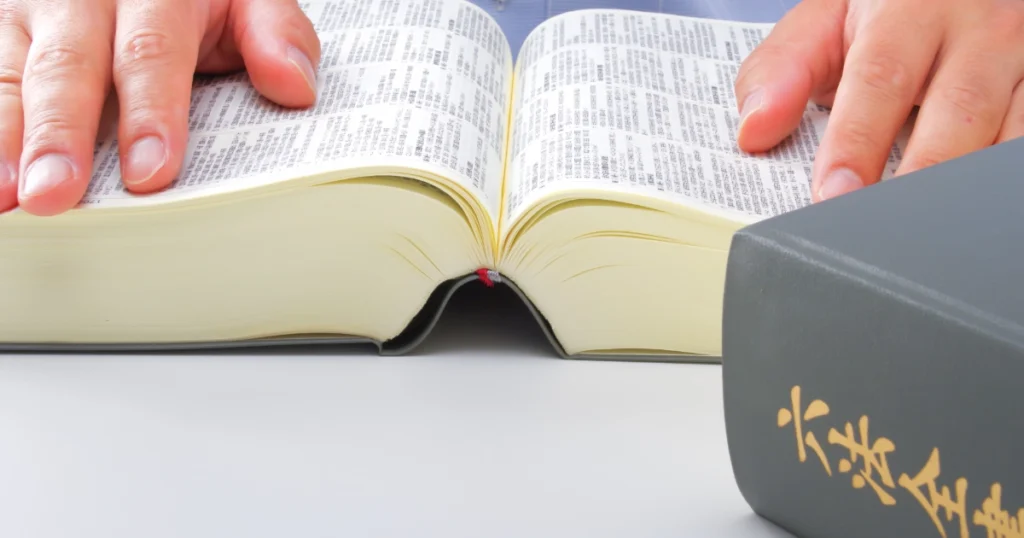
経年劣化による減価の重要性
- 長期使用による自然損耗の認定
57か月間の使用による損耗は通常使用の範囲として扱われる - 過失の限定的判断
明確な過失行為(落書き)があっても、その範囲は限定的に認定される - 数値的な負担算定
残存価値による具体的な負担額算定が有効と認められる
最も重要な教訓は、過失による損傷があっても、経年劣化による減価を考慮した適正な負担額算定が必要という点です。
賃借人が主張した残存価値28.75%という数値は、57か月間の使用期間と設備の耐用年数(使える期間の目安)を考慮した合理的な算定として認められました。
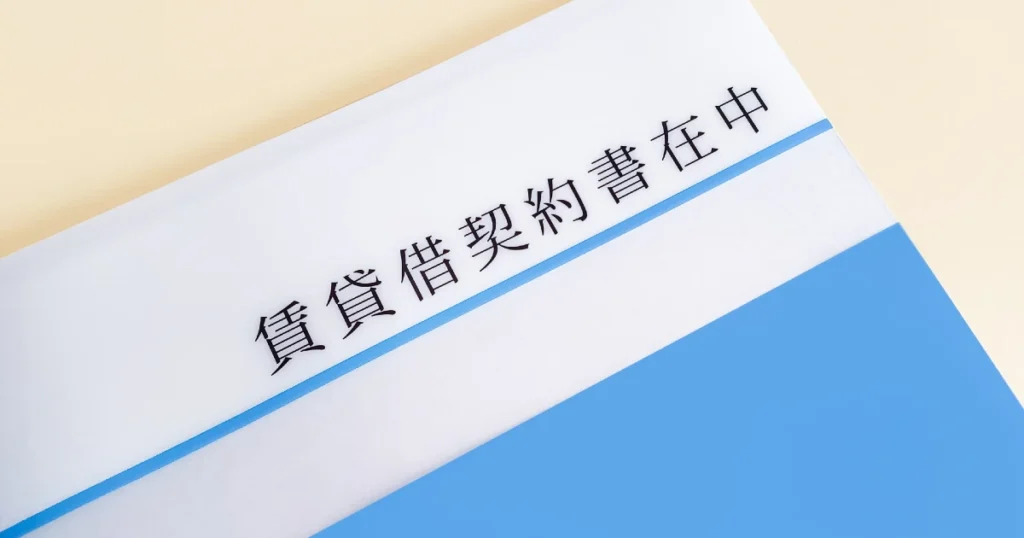
実務への重要な影響
- 修繕特約があっても経年劣化の考慮は必須
- 過失の範囲は具体的かつ限定的に判断される
- 減価償却の概念を用いた負担額算定が有効
この判例により、原状回復費用の算定において、単純に修繕費用を請求するのではなく、使用期間に応じた減価を考慮することの重要性が確立されました。
また、子供の落書きのような明確な過失行為があっても、その影響範囲を適正に限定し、その他の損耗については経年変化として扱う判断手法が示されています。
賃貸借契約における実践的対策
経年劣化を適切に考慮した公正な負担分担を実現するため、契約書の作成には細心の注意が必要です。

契約締結時の重要チェックポイント
- 経年劣化による減価償却の計算方法が明記されているか
- 設備ごとの耐用年数と残存価値の算定基準が記載されているか
- 「賃借人負担」の範囲が具体的に限定されているか
借主の皆様には、まず修繕特約の内容を詳細に確認することをお勧めします。
「畳・クロス・カーペット等は賃借人負担」といった包括的な条項がある場合は、経年劣化による減価がどの程度考慮されるかを事前に確認してください。
特に重要なのは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠した負担区分(誰が費用を払うかの分け方)表が添付されているかです。
契約期間が長期になる予定の場合は、年数に応じた減価率の適用について明文化を求めることも有効です。
また、入居時の物件状況を詳細に記録し、写真等で保存しておくことで、退去時の適正な負担判断に役立ちます。
不明な点がある契約書については、専門家に相談して適正な条項への修正を求めることをお勧めします。
まとめ
東大阪簡易裁判所の本判決は、原状回復費用の算定において経年劣化を適切に考慮することの重要性を明確に示しました。
賃借人の過失による損傷があっても、57か月という使用期間を考慮して通常使用による減価を認定した判断は、公正な負担分担の在り方を示しています。
この判例により、修繕特約があっても経年劣化による減価を無視した請求は認められないことが確立され、賃借人の権利保護が進展しました。
実務においては、減価償却の概念を契約条項に明確に盛り込むことで、退去時の紛争を効果的に防止できます。
適正な負担区分による公正な賃貸借関係の構築が、健全な住宅市場の発展に不可欠です。
- 過失による損傷があっても、経年劣化による減価を考慮した負担額算定が必要
- 長期間(57か月)の使用による損耗は通常使用の範囲として認定される
- 残存価値を数値化した具体的な負担額算定が有効な手法として認められる
- 修繕特約があっても経年劣化の考慮は法的に必須要件となる
- 契約書には減価償却の計算方法と負担区分を明確に記載することが重要
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)【判例20】





