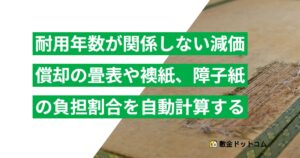【賃貸に10~30年】退去費用の相場と耐用年数による負担減の仕組み
「10年以上住んでいるけど、退去費用はいくらかかるの?」「20年も住めば壁紙代はタダになるって本当?」——長く住んだ賃貸物件からの退去を控え、費用面で不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
結論から言えば、賃貸物件に長く住むほど、設備や内装材の「耐用年数」により借主の負担は軽くなります。国土交通省のガイドラインでは、壁紙やカーペットの耐用年数は6年とされており、6年以上住んでいれば残存価値は1円。つまり、借主の負担はほぼゼロになるのです。
この記事では、賃貸アパートに10年・15年・20年・30年と長期間住んだ場合の退去費用の考え方を、設備ごとの耐用年数一覧、居住年数別のシミュレーション、実際の費用相場まで具体的に解説します。長期居住でも借主負担となるケースや、退去費用を抑えるためのポイントもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
長期居住で退去費用が安くなる理由
1-1. 経年劣化・通常損耗は貸主負担が原則
賃貸物件の退去費用を考える上で、まず理解しておきたいのが「経年劣化」と「通常損耗」は貸主(大家さん)の負担になるという原則です。
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復について次のように定義しています。
- 原状回復とは:「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」
- 経年変化・通常損耗:時間の経過や通常の使用による損耗は、賃料に含まれているため貸主負担
- 借主負担となるもの:故意・過失による損傷、善管注意義務違反による損傷のみ
つまり、「入居時の状態に戻す」のではなく、「借主の責任で生じた損傷だけを修繕する」のが原状回復の本来の意味です。日焼けによる壁紙の変色や、家具を置いていた跡のへこみなどは、借主が直す必要はありません。
1-2. 耐用年数と残存価値の考え方
長期居住者にとって特に重要なのが「耐用年数」と「残存価値」の考え方です。
設備や内装材には「耐用年数」が定められており、年数が経過するほど価値が下がっていきます。借主が負担する金額は、この「残存価値」に基づいて計算されます。
- 基本的な考え方:耐用年数が経過するにつれ、設備の価値は減少していく
- 計算式:借主負担額 = 修繕費用 ×(残存価値 ÷ 新品価値)
- 耐用年数経過後:残存価値は1円となり、借主負担はほぼゼロ
- 例:壁紙(耐用年数6年)に10年住んだ場合、耐用年数を超えているため借主負担は1円
長く住めば住むほど、設備の残存価値は下がり、借主の負担は軽くなります。10年以上住んでいる方は、多くの設備が耐用年数を超えているため、退去費用が大幅に抑えられる可能性が高いです。
2-1. 主な設備・内装材の耐用年数
国土交通省ガイドラインに基づく、主な設備・内装材の耐用年数は以下の通りです。耐用年数を超えて居住していれば、その設備の修繕費用は原則として借主負担にはなりません。
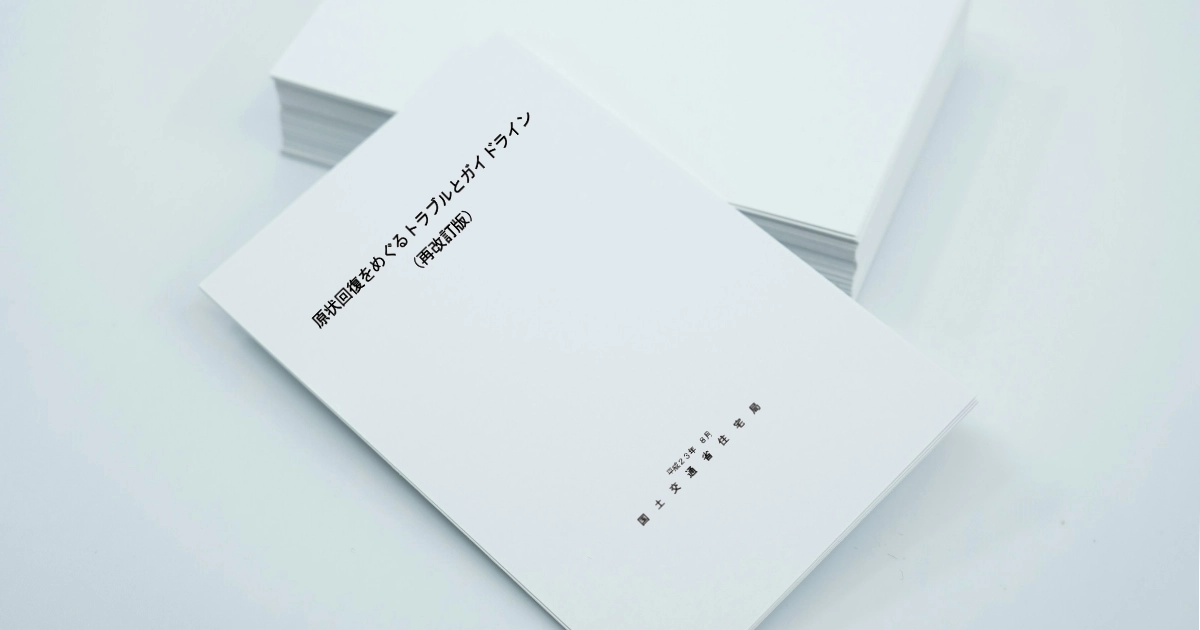
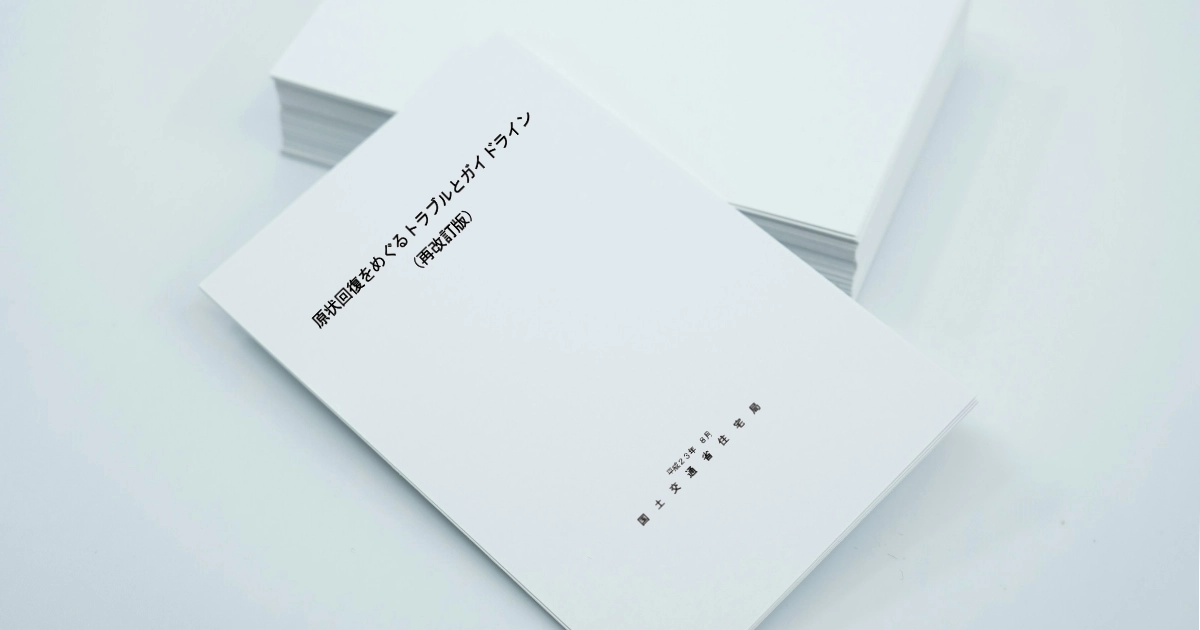
| 設備・内装材 | 耐用年数 | 備考 |
|---|---|---|
| 壁紙(クロス) | 6年 | 6年経過で残存価値1円 |
| カーペット | 6年 | 同上 |
| クッションフロア | 6年 | 同上 |
| エアコン | 6年 | 設備として設置されている場合 |
| インターフォン | 6年 | — |
| 流し台 | 5年 | — |
| ガスコンロ(ビルトイン) | 6年 | — |
| 金属製以外の家具 | 8年 | 備え付けのタンス・本棚など |
| 金属製の家具 | 15年 | — |
| 便器・洗面台 | 15年 | 給排水設備 |
| ユニットバス | 15年 | — |
2-2. 耐用年数が設定されていない設備
一部の設備・内装材には、明確な耐用年数が設定されていません。これらは長期居住でも借主負担が発生しやすい項目なので注意が必要です。


| 設備・内装材 | 耐用年数の扱い | 借主負担の考え方 |
|---|---|---|
| フローリング | 建物と同じ(木造22年、RC47年など) | 部分補修は経過年数考慮なし、全面張替えは経過年数を考慮 |
| 畳表・畳床 | 消耗品扱い | 経過年数は考慮されない場合あり |
| 襖・障子 | 消耗品扱い | 経過年数は考慮されない場合あり |
| 鍵の交換 | — | 紛失した場合は借主負担、それ以外は貸主負担 |
| ハウスクリーニング | — | 特約がある場合は借主負担 |
フローリングは建物と同じ耐用年数が適用されるため、木造アパートでも22年と長期間です。20年住んでいても、フローリングに故意・過失による傷があれば借主負担が発生する可能性があります。一方、壁紙やカーペットは6年で耐用年数を迎えるため、長期居住者にとっては有利です。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
居住年数別シミュレーション
3-1. 壁紙(クロス)の負担割合シミュレーション
壁紙(クロス)の耐用年数は6年です。居住年数ごとの借主負担割合を見てみましょう。


| 居住年数 | 残存価値(目安) | 借主負担割合 | 張替費用10万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 3年 | 約50% | 50% | 約5万円 |
| 6年 | 1円(ほぼ0%) | ほぼ0% | ほぼ0円 |
| 10年 | 1円 | ほぼ0% | ほぼ0円 |
| 15年 | 1円 | ほぼ0% | ほぼ0円 |
| 20年 | 1円 | ほぼ0% | ほぼ0円 |
| 30年 | 1円 | ほぼ0% | ほぼ0円 |
6年以上住んでいれば、壁紙の張替え費用は原則として借主負担になりません。10年・20年・30年と長く住んでいる方は、壁紙に関しては安心して退去できます。
3-2. 設備ごとの耐用年数経過状況(居住年数別)
居住年数ごとに、各設備の耐用年数を経過しているかどうかを一覧にまとめました。


| 設備 | 耐用年数 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁紙・カーペット | 6年 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 |
| エアコン | 6年 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 |
| 流し台 | 5年 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 |
| 金属製以外の家具 | 8年 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 |
| 便器・洗面台 | 15年 | △未経過 | ◎経過 | ◎経過 | ◎経過 |
| フローリング(木造) | 22年 | △未経過 | △未経過 | △未経過 | ◎経過 |
| フローリング(RC造) | 47年 | △未経過 | △未経過 | △未経過 | △未経過 |
◎経過=耐用年数を超えており借主負担はほぼゼロ、△未経過=故意・過失があれば負担が発生する可能性あり
10年以上の長期居住者は、壁紙・カーペット・エアコンなど多くの設備が耐用年数を超えています。15年以上住んでいれば便器・洗面台も含まれ、さらに負担が軽くなります。30年住んだ木造アパートなら、フローリングも耐用年数を超えるため、ほとんどの設備で借主負担がゼロになる可能性があります。
長期居住でも借主負担になるケース
4-1. 故意・過失による損傷
耐用年数を超えていても、借主の故意・過失による損傷は借主負担となります。以下のようなケースは、長期居住者でも費用を請求される可能性があります。
- タバコのヤニ汚れ:喫煙による壁紙の変色・臭い付着
- ペットによる傷・臭い:引っかき傷、噛み跡、排泄物の染み
- 飲み物・食べ物のシミ:こぼして放置したことによるシミ
- 重量物による穴:ネジ・釘で下地ボードまで損傷した穴
- 落書き・傷:子どもの落書き、家具移動時の傷
4-2. 善管注意義務違反
借主には「善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)」があります。この義務に違反した場合も、借主負担が発生します。
- 結露を放置したカビ:日常的な換気や拭き取りを怠った結果のカビ
- 掃除を怠った油汚れ:キッチンの油汚れを長期間放置
- 水漏れの放置:水漏れに気づいていながら報告・対処しなかった
- 冷蔵庫下のサビ放置:サビを発見しながら対処せず床に損傷を与えた
4-3. 特約による例外
契約書に「特約」がある場合、ガイドラインの原則とは異なる負担を求められることがあります。以下のような特約がないか、契約書を確認しましょう。
- ハウスクリーニング代借主負担:退去時のクリーニング代は借主が負担する
- 畳・襖の張替え費用借主負担:経過年数に関わらず借主が負担する
- 鍵交換費用借主負担:紛失の有無に関わらず借主が負担する
- ペット飼育に伴う原状回復費用:ペット可物件で追加の負担が定められている
特約が有効となるには、借主が特約の内容を認識し、負担の意思表示をしていることが必要です。ただし、10年以上前の契約では記憶が曖昧なことも多いので、退去前に必ず契約書を確認しましょう。特約の内容に疑問がある場合は、消費生活センターに相談することをお勧めします。
5-1. 間取り別の退去費用相場
退去費用の相場は間取りによって異なります。以下は一般的な目安ですが、10年以上の長期居住者は耐用年数超過により、この金額より大幅に安くなる可能性があります。


| 間取り | 一般的な相場 | 10年以上居住の目安 |
|---|---|---|
| ワンルーム・1K | 約5〜7万円 | 約2〜4万円 |
| 1DK・1LDK | 約6〜8万円 | 約3〜5万円 |
| 2K・2DK・2LDK | 約8〜12万円 | 約4〜7万円 |
| 3DK・3LDK | 約9〜15万円 | 約5〜8万円 |
5-2. 項目別の費用相場
退去費用の内訳として請求されやすい項目と、その費用相場を確認しておきましょう。


| 項目 | 費用相場 | 長期居住者の負担 |
|---|---|---|
| ハウスクリーニング | 2〜5万円(広さによる) | 特約があれば負担 |
| 壁紙張替え(1面) | 3〜5万円 | 6年超でほぼ0円 |
| 壁紙張替え(全室) | 8〜15万円 | 6年超でほぼ0円 |
| フローリング補修 | 1〜3万円 | 故意・過失あれば負担 |
| フローリング張替え | 10〜20万円 | 建物の耐用年数による |
| 畳表替え(1畳) | 4,000〜8,000円 | 特約があれば負担 |
| 襖張替え(1枚) | 2,000〜5,000円 | 特約があれば負担 |
| 鍵交換 | 1〜2万円 | 紛失した場合は負担 |
| エアコンクリーニング | 1〜2万円 | 6年超でほぼ0円 |
長期居住者の退去費用で最も大きな割合を占めるのは「ハウスクリーニング代」です。壁紙や設備は耐用年数超過で負担がなくなりますが、ハウスクリーニング代は特約で借主負担と定められていることが多いため、契約書の確認が重要です。
6-1. 退去前の写真撮影
退去費用のトラブルを防ぐ最も有効な手段が写真による記録です。退去時の部屋の状態を証拠として残しておきましょう。
- 日付入りで撮影:スマホの設定で日付を表示させるか、新聞と一緒に撮影
- 全体と詳細の両方を撮る:部屋全体の写真+傷や汚れのアップ写真
- 撮影箇所:壁4面、床、天井、窓、ドア、キッチン、浴室、トイレ、収納内部、ベランダ
- 動画も活用:写真では伝わりにくい傷の深さなどは動画で記録
6-2. 契約書・重要事項説明書の確認
長期居住者は契約時の記憶が曖昧になりがちです。退去前に必ず賃貸借契約書と重要事項説明書を読み返し、特約の内容を確認しましょう。
- 原状回復に関する特約:「ハウスクリーニング代は借主負担」などの記載
- 敷金の精算方法:敷金から差し引く費用の範囲
- 解約予告期間:退去の何ヶ月前に通知が必要か(通常1〜2ヶ月前)
- 退去立会いの有無:立会いが必須かどうか
6-3. 高額請求時の交渉方法
退去費用が高額だと感じた場合は、以下の手順で交渉を進めましょう。
- 請求書の内訳を確認:何にいくらかかっているのか、項目ごとに確認する
- 耐用年数と照らし合わせる:10年以上住んでいるなら、壁紙等は耐用年数超過を主張
- ガイドラインを根拠に交渉:国土交通省ガイドラインのPDFを持参して説明
- 書面で回答を求める:口頭でのやり取りは記録に残らないため、書面での回答を依頼
- 消費生活センターに相談:交渉が進まない場合は第三者に相談
原状回復義務の詳しい範囲については、以下の記事で解説しています。
まとめ:長期居住者の退去で損をしないために
賃貸アパートに10年・15年・20年・30年と長く住んだ方は、耐用年数の考え方を理解しておくことで、退去費用を大幅に抑えられる可能性があります。壁紙やカーペットは6年、便器・洗面台は15年で耐用年数を迎え、それ以降は借主負担がほぼゼロになります。
この記事のポイント
- 耐用年数と負担の関係
- 壁紙・カーペット・エアコンは6年で残存価値1円
- 便器・洗面台は15年で残存価値1円
- フローリングは建物の耐用年数(木造22年、RC造47年)
- 退去前に必ず行うこと
- 契約書の特約を確認する
- 退去時の写真を日付入りで撮影する
- 請求書の内訳を確認し、疑問があれば交渉する
長期居住者は退去費用で有利な立場にあります。ただし、「長く住んでいるから何も払わなくていい」と思い込むのは危険です。特約の内容、故意・過失による損傷、フローリングなど耐用年数の長い設備については、しっかり確認しておきましょう。請求内容に納得できない場合は、消費生活センター(188番)に相談することをお勧めします。事前準備をしっかり行えば、退去費用で大きく損をすることは避けられます。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 原状回復費用の相場や耐用年数は、物件や地域によって異なる場合があります。
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の最新版は、国土交通省のウェブサイトでご確認ください。