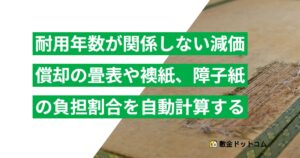【賃貸アパートに1~6年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?
賃貸アパートに1年住んだ場合と6年住んだ場合では、退去費用にどのくらいの差が出るのでしょうか。国土交通省のガイドラインでは、設備や内装材の耐用年数に基づいて経年劣化を考慮し、入居年数が長いほど借主の費用負担が軽くなる仕組みになっています。
入居1年なら修繕費の約83%が借主負担ですが、6年経過すると耐用年数6年の設備は残存価値1円となり、借主負担はほぼゼロになります。この違いを知っておくことが、退去費用の適正な判断につながります。
この記事では、入居1年から6年までの居住年数別に、設備・内装材の残存価値と退去費用の相場を比較しながら解説します。負担額の計算方法、費用を抑えるポイント、高額請求時の相談先まで網羅していますので、ぜひ参考にしてください。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
入居年数による費用負担の違い
原状回復費用の借主負担は、入居年数によって大きく変わります。短期入居では設備の残存価値が高いため借主の負担割合が大きく、長期入居では経年劣化による減額が進み負担が軽くなります。まずは1~2年と5~6年の違いを比較してみましょう。
1-1. 短期入居(1~2年)の費用負担の特徴
入居1~2年で退去する場合、耐用年数6年の設備はまだ残存価値が高い状態です。借主の過失による損傷があれば、修繕費の大部分を負担することになります。
- 残存価値が高い:1年経過で約83%、2年経過で約67%の残存価値が残る
- 借主負担が大きい:壁紙の張替え費用3万円なら、1年退去で約2.5万円が借主負担
- 短期解約違約金の可能性:契約書に「1年未満は家賃1ヶ月分」などの特約がある場合も
- 通常損耗は対象外:短期でも普通に暮らして生じた損耗は貸主負担が原則
1-2. 長期入居(5~6年)の費用負担の特徴
一方、5~6年の長期入居では経年劣化が大きく進んでおり、耐用年数6年の設備は残存価値がほとんど残りません。6年経過した壁紙やカーペットは残存価値1円となり、借主の過失による損傷があっても費用負担はほぼゼロです。
- 残存価値がほぼゼロ:6年経過で耐用年数6年の設備は残存価値1円(実質ゼロ)
- 壁紙・カーペットは負担なし:6年経過後の張替え費用は基本的に貸主負担
- 注意が必要な設備もある:フローリングや畳表など耐用年数の定めがない設備は減額なし
- 故意・重過失は別:わざと壊した場合やペットによる損傷は年数に関わらず借主負担
入居年数が長いほど退去費用の負担は軽くなりますが、「耐用年数の定めがない設備」や「故意・重過失による損傷」は年数に関係なく借主負担になります。自分の入居年数と設備の耐用年数を照らし合わせて、適正な負担額を把握しましょう。
ここでは、入居1年から6年までの居住年数別に、主な設備・内装材の残存価値割合と借主の費用負担目安を比較テーブルで整理します。退去費用の見積もりを確認する際の参考にしてください。


| 設備(耐用年数6年) | 修繕費目安 | 1年 残存83% | 2年 残存67% | 3年 残存50% | 4年 残存33% | 5年 残存17% | 6年 残存1円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁紙クロス(1面) | 3~4万円 | 2.5~3.3万円 | 2.0~2.7万円 | 1.5~2.0万円 | 1.0~1.3万円 | 0.5~0.7万円 | ほぼ0円 |
| カーペット(6畳) | 4~6万円 | 3.3~5.0万円 | 2.7~4.0万円 | 2.0~3.0万円 | 1.3~2.0万円 | 0.7~1.0万円 | ほぼ0円 |
| クッションフロア(6畳) | 3~5万円 | 2.5~4.2万円 | 2.0~3.4万円 | 1.5~2.5万円 | 1.0~1.7万円 | 0.5~0.9万円 | ほぼ0円 |
| エアコン修繕 | 1~3万円 | 0.8~2.5万円 | 0.7~2.0万円 | 0.5~1.5万円 | 0.3~1.0万円 | 0.2~0.5万円 | ほぼ0円 |
| 給湯器修繕 | 1~3万円 | 0.8~2.5万円 | 0.7~2.0万円 | 0.5~1.5万円 | 0.3~1.0万円 | 0.2~0.5万円 | ほぼ0円 |
上記の表は「耐用年数6年」の設備に限った金額です。フローリングや畳表など耐用年数の定めがない設備は、居住年数による減額がありませんのでご注意ください。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
居住年数ごとの負担計算方法
退去費用の借主負担は、「修繕費 × 残存価値割合」で計算します。耐用年数が設定されている設備は、入居年数に応じて残存価値が直線的に減少する「定額法」で計算されます。
3-1. 壁紙クロスの計算例(1年 vs 6年)
壁紙クロスの耐用年数は6年です。タバコのヤニ汚れで1面の張替え(修繕費30,000円)が必要になった場合の、入居1年と6年の比較を見てみましょう。
- 修繕費:壁紙1面の張替え=30,000円
- 残存価値:耐用年数6年のうち1年経過→残存約83%
- 借主負担額:30,000円 × 83% = 約24,900円
- 貸主負担額:30,000円 − 24,900円 = 約5,100円
- 修繕費:壁紙1面の張替え=30,000円
- 残存価値:耐用年数6年のうち6年経過→残存価値1円
- 借主負担額:実質ほぼ0円(残存価値1円)
- 貸主負担額:30,000円(ほぼ全額が貸主負担)
このように、同じ壁紙の張替え費用30,000円でも、入居1年なら約24,900円の借主負担ですが、6年経過後はほぼ0円となります。入居年数による差額は約24,900円にもなるのです。
3-2. 耐用年数の定めがない設備
すべての設備に経年劣化による減額が適用されるわけではありません。フローリング・畳表・襖紙など、耐用年数の定めがない設備は入居年数に関係なく借主の過失分が負担になります。
- フローリング(部分補修):損傷箇所のみ補修で1~3万円。全面張替えは原則不要
- フローリング(全面張替え):借主の過失が広範囲に及ぶ場合は10~20万円以上
- 畳表替え(1枚):4,000~8,000円。消耗品扱いで入居年数に関わらず同額
- 襖紙(1枚):3,000~5,000円。破損した枚数分のみ借主負担
退去費用を合理的に抑えるポイント
4-1. 入居時・居住中の予防策
退去費用を抑えるために最も効果的なのは、入居時から予防策を講じておくことです。以下のポイントを実践しておくと、退去時の交渉で有利に働きます。
- 入居時の写真撮影:壁・床・天井・設備を日付入りで撮影し、証拠として保存する
- 既存の傷を書面で報告:入居前からの傷・汚れをメールや書面で管理会社に報告する
- 傷防止グッズの活用:家具の脚にフェルトパッド、壁に保護シート、冷蔵庫下にマットを設置
- こまめな掃除と換気:カビや油汚れの蓄積を防ぎ、退去時の原状回復費用を最小限にする
4-2. 退去時の交渉の進め方
退去費用の見積書が届いたら、以下のポイントを確認して交渉しましょう。特に入居年数が長い場合は、経年劣化による減額が正しく反映されているかが重要なチェックポイントです。
- 経年劣化の控除確認:入居年数に応じた残存価値の減額が反映されているか
- 通常損耗の除外:日焼けや家具跡など通常使用の損耗が費用に含まれていないか
- 施工範囲の妥当性:一部の損傷なのに全面張替えの費用が請求されていないか
- 単価の相場確認:修繕単価が市場相場と大きく乖離していないか
5~6年お住まいだった方が、壁紙やカーペットの「新品交換費用」を全額請求されるケースは少なくありません。しかし、耐用年数6年の設備は6年経過で残存価値1円です。見積書に経年劣化の控除が反映されていない場合は、ガイドラインを根拠に減額を求めましょう。
管理会社との交渉で解決しない場合や、明らかに不当な高額請求を受けた場合は、専門機関に相談することで適正な解決につながります。


| 相談先 | 特徴 | 費用 |
|---|---|---|
| 消費生活センター(188番) | 退去費用トラブルの相談・助言。まず最初に相談すべき窓口 | 無料 |
| 法テラス(0570-078374) | 収入要件を満たせば弁護士費用の立替制度を利用可能 | 無料相談あり |
| 各地の宅建協会 | 不動産取引に関する相談窓口。賃貸トラブルにも対応 | 無料 |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭問題を簡易裁判所で原則1日で審理 | 手数料数千円 |
相談時には、契約書のコピー、退去費用の見積書、入居時の写真など証拠資料を準備しておくと、より具体的なアドバイスを受けることができます。
原状回復義務の詳しい範囲については、以下の記事で解説しています。
まとめ:入居年数と耐用年数の関係を理解して適正な退去費用を判断しよう
入居1年と6年では、退去費用の借主負担に大きな差があります。耐用年数6年の設備は1年退去で約83%の負担ですが、6年経過すれば残存価値1円でほぼ負担なし。この仕組みを知っておくことが、不当な請求を防ぐ第一歩です。
この記事のポイント
- 入居年数と費用負担の関係
- 耐用年数6年の設備は1年退去で約83%、6年退去で残存価値1円(ほぼ0円)
- フローリングや畳表など耐用年数の定めがない設備は年数に関係なく部分補修が原則
- 通常の使用による損耗は入居期間に関わらず貸主負担
入居年数が何年であっても、退去費用の見積書は必ず内容を確認してください。耐用年数の表と計算方法を手元に控えておき、各項目の残存価値が正しく反映されているか照合しましょう。不明な点があれば、署名する前に専門家に相談することをおすすめします。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 耐用年数や残存価値の計算は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づくものであり、契約書の特約が優先される場合があります。
- 費用相場は一般的な目安であり、地域や物件の状態によって実際の金額は異なります。