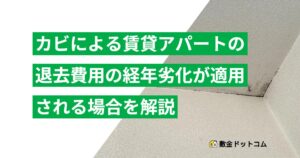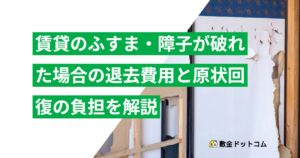【内容証明郵便の書き方を解説】敷金返還請求書のテンプレート付き
「敷金が返ってこないけど、どうやって請求すればいいの?」——退去後に敷金の返還を求めても貸主や管理会社が対応してくれないケースは珍しくありません。
結論から言えば、内容証明郵便による敷金返還請求書の送付が最も効果的な解決手段です。内容証明郵便は「いつ・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれる制度であり、法的な証拠力を持つ正式な意思表示として機能します。
この記事では、内容証明郵便の書式ルールと形式要件、敷金返還請求書に記載すべき項目、そのまま使えるテンプレート、送付手続きの流れ、送付後の対応まで実践的に解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金返還で内容証明郵便が必要になるケース
退去時の敷金返還トラブルは、貸主と借主の間で負担区分の認識が食い違うことが主な原因です。国土交通省のガイドラインでは、通常損耗や経年劣化による修繕費用は貸主負担と明確に定められています。
1-1. 貸主負担となる修繕費用の具体例
以下の項目はガイドラインにおいて貸主が負担すべきとされている費用です。これらを理由に敷金から控除された場合は、内容証明郵便で返還を請求できます。
- 壁紙の変色・日焼け:紫外線や経年による自然な劣化
- フローリングの色褪せ:日照や経年による自然な変化
- 畳の日焼け:日光が当たることで起きる自然な変色
- 家具設置跡:テーブルやベッドの脚による床の凹み
- 設備の経年故障:耐用年数を超えたエアコンや給湯器の不具合
1-2. 内容証明郵便が効果的な理由
内容証明郵便は単なる手紙とは異なり、郵便法に基づいて「いつ・誰に・どのような内容を送ったか」を郵便局が公的に証明する制度です。
多くの貸主は内容証明郵便を受け取った時点で、借主が法的手続きを真剣に検討していると認識し、交渉に応じる姿勢を見せるようになります。また、後に調停や訴訟に進む場合にも、意思表示を行った証拠として活用できます。
内容証明郵便には「最後通告」としての心理的効果もあり、送付しただけで円満に解決するケースが多く見られます。まずは書面での意思表示を行うことが重要です。
内容証明郵便には厳格な形式要件が定められており、書式に不備があると受け付けてもらえない場合があります。ここでは手書き・窓口の場合とe内容証明サービスの場合、それぞれの要件を解説します。
2-1. 基本的な形式要件
郵便局の窓口で差し出す場合は、郵便法施行規則第24条に基づく文字数制限を守る必要があります。一方、e内容証明サービスを利用する場合は文字数制限がないため、より詳細な内容を記載できます。
- 1行の文字数:縦書きは1行20字以内、横書きは1行20字以内または26字以内
- 1枚の行数:縦書き26行以内、横書き20字×26行、26字×20行、13字×40行
- 同一内容を3通作成:送付用・差出人控え・郵便局保管用
- 使用文字:ひらがな・カタカナ・漢字・数字・英字・句読点・一般的な記号
2-2. e内容証明サービスの活用メリット
日本郵便が提供する「e内容証明(電子内容証明)」サービスを利用すれば、インターネット上から24時間いつでも内容証明郵便を差し出すことができます。
- 文字数制限なし:手書き版のような1行・1枚の文字数制限がない
- 24時間対応:郵便局の営業時間を気にせず差し出せる
- Word形式で作成:パソコンで文書を作成し、そのままアップロード可能
- 3通の用意が不要:1ファイルのアップロードで自動的に3通分が処理される
退去費用の交渉を専門家に依頼する方法は、以下の記事で解説しています。
敷金返還請求書に必要な記載事項とテンプレート
敷金返還請求書を作成する際は、法的な根拠を明確にしつつ、請求内容を具体的に記載することが重要です。ここでは必須の記載事項と、そのまま使えるテンプレートを紹介します。
3-1. 文書のヘッダーと基本情報
内容証明郵便の冒頭には、文書の日付・差出人(借主)の住所氏名・受取人(貸主)の住所氏名を正確に記載します。受取人の名前や住所に誤りがあると送達できない場合があるため、契約書に記載された情報を確認しましょう。
- 表題:「敷金返還請求書」と明記
- 契約情報:物件の所在地、契約日、契約期間、敷金の額
- 請求の根拠:民法第622条の2(敷金返還義務)、ガイドラインの該当箇所
- 請求金額:返還を求める具体的な金額と算出根拠
- 支払期限:「本書面到達後14日以内」など具体的な期限
- 振込先:返還金の振込口座情報
3-2. 請求の法的根拠と記載のポイント
敷金返還請求の法的根拠は、民法第622条の2「賃貸人は、敷金を受け取っている場合、賃貸借が終了し建物の明渡しを受けたときは、敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない」という規定です。
請求書にはこの条文を引用したうえで、控除された各項目がガイドラインのどの分類に該当するか(通常損耗・経年劣化など)を具体的に記載しましょう。
3-3. 敷金返還請求書のテンプレート
以下は敷金返還請求書の記載例です。実際に使用する際は、ご自身の契約内容に合わせて具体的な金額や項目を修正してください。


| 記載箇所 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 表題 | 敷金返還請求書 |
| 冒頭 | 私は貴殿との間で下記賃貸借契約を締結し、令和○年○月○日に退去・明渡しを完了いたしました。 |
| 契約情報 | 物件所在地:○○県○○市○○町○-○-○ ○○マンション○○号室/契約日:令和○年○月○日/敷金:金○○万円 |
| 請求根拠 | 民法第622条の2に基づき、敷金の返還を請求いたします。貴殿が控除した○○費用○○円は、国土交通省ガイドラインにおいて通常損耗・経年劣化に該当し、貸主負担とされています。 |
| 請求金額 | つきましては、敷金○○万円から正当な控除額○○円を差し引いた金○○円を、本書面到達後14日以内に下記口座へお振り込みください。 |
| 法的措置の予告 | 上記期限内にお支払いいただけない場合は、少額訴訟等の法的手続きを検討せざるを得ませんことを申し添えます。 |
請求書には感情的な表現を避け、法的根拠と事実に基づいた冷静な文面を心がけましょう。威圧的な表現は逆効果になる場合があります。
内容証明郵便の送付手続きと費用
内容証明郵便の送付方法は、郵便局窓口で差し出す方法とe内容証明サービスを利用する方法の2つがあります。それぞれの手順と費用を確認しましょう。
4-1. e内容証明サービスの利用手順
e内容証明サービスは、パソコンとインターネット環境があれば自宅から24時間いつでも差し出せる便利な方法です。
- 会員登録:日本郵便のe内容証明サービスにアカウントを作成
- 文書の作成:Word形式で敷金返還請求書を作成
- 文書のアップロード:サイト上でWordファイルをアップロード
- 宛先の入力:受取人(貸主)の住所・氏名を入力
- 料金の支払い:クレジットカードまたは料金後納で決済
- 差出完了:日本郵便が印刷・封入・発送を代行
4-2. 送付費用と配達証明の重要性
内容証明郵便の費用は送付方法によって異なります。配達証明を必ず付けることが重要です。配達証明がないと「届いていない」と主張される可能性があります。
- 基本料金(定形郵便):110円
- 一般書留加算料金:480円
- 内容証明加算料金:480円(1枚目)+290円(2枚目以降1枚ごと)
- 配達証明料金:350円(差出時に付加する場合)
- 合計目安:1枚の場合は約1,420円、e内容証明の場合は約1,500〜2,000円
内容証明郵便を送付した後は、相手方の反応に応じた適切な対応が必要です。返答がない場合や拒否された場合の次のステップについて解説します。
5-1. 相手方からの反応パターン
内容証明郵便を受け取った貸主や管理会社の反応は、主に以下の3パターンに分かれます。
- 全額または一部返還に応じる:請求内容を認め、指定期日までに返還される
- 減額を提示して交渉を求める:一部の項目について反論し、和解案を提示してくる
- 返答がない・受取拒否:期限を過ぎても反応がない場合は次の法的手続きを検討
5-2. 次のステップ:調停・少額訴訟の活用
内容証明郵便を送付しても解決しない場合は、段階的に法的手続きを検討します。


| 手続き | 概要 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 民事調停 | 裁判所の調停委員が間に入り、話し合いで解決を目指す手続き | 数千円 |
| 少額訴訟 | 60万円以下の請求を原則1回の審理で解決する裁判手続き | 約1万円 |
| 通常訴訟 | 60万円を超える場合や複雑な法律問題がある場合の裁判手続き | 数万円〜 |
5-3. 専門家への相談タイミング
以下のような場合は、一人で対応せず専門家に相談することをおすすめします。
- 請求額が高額:敷金の返還額や原状回復費用が大きく、対応に不安がある場合
- 特約の解釈が複雑:契約書の特約条項について法的判断が必要な場合
- 相手方が弁護士を立てた:貸主側が法律の専門家を介入させてきた場合
- 内容証明郵便に自信がない:文書の作成方法や送付手続きに不安がある場合
内容証明郵便の作成は行政書士に依頼することもできます。費用は1〜3万円程度が目安ですが、法的根拠を正確に記載したプロの文書は交渉力が高まります。迷ったらまずは法テラス(0570-078374)への無料相談を検討しましょう。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
まとめ:内容証明郵便で敷金返還を実現しよう
敷金返還トラブルの解決には、内容証明郵便による正式な請求が最も効果的です。法的根拠と具体的な金額を記載した文書を送付することで、多くの場合、貸主側は返還交渉に応じるようになります。
この記事のポイント
- 内容証明郵便の書き方と形式要件
- 窓口差出は文字数制限あり、e内容証明は制限なし
- 民法第622条の2を根拠に敷金返還を請求する
- 契約情報・請求金額・支払期限を具体的に記載
- 配達証明を必ず付けて送付する
- 送付後の対応と次のステップ
- 多くのケースで送付後に返還交渉が進む
- 返答がない場合は調停・少額訴訟を検討
- 費用は窓口で約1,420円、e内容証明で約1,500〜2,000円
- 不安な場合は行政書士や法テラスに相談
敷金返還請求は「泣き寝入り」する必要のないトラブルです。ガイドラインと民法を根拠にした内容証明郵便を送れば、多くの場合は解決に向かいます。この記事のテンプレートを参考に、まずは行動を起こしてみてください。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 内容証明郵便の費用や手続きは変更される場合があります。最新情報は日本郵便のホームページでご確認ください。