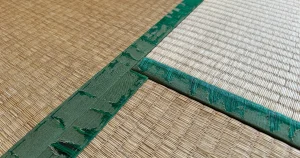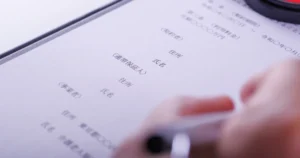原状回復工事はガイドラインに沿って業者を自分で選べるのか?

賃貸住宅を退去する際、多くの借主が直面する原状回復(元の状態に戻すこと)工事の問題。
適切な知識と手順があれば、スムーズに進められます。
特に「業者を自分で選べるのか」「費用を抑えるために自分で修繕してもいいのか」という疑問は非常に重要です。
結論から言えば、借主が責任を負う修繕については原則として借主が業者を選定する権利がありますが、賃貸借契約書の内容や損耗の性質によってこの権利が制限される場合もあります。
また、多くの契約では借主による修繕作業を禁止する条項が設けられており、この場合は一切のDIY修繕が契約違反となります。
国土交通省のガイドラインでは通常の使用による損耗は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担とされていますが、実際の現場では様々なトラブルが発生しています。
本記事では、原状回復工事における業者選定の権利とDIY対応について、法的根拠と実践的な対応方法を詳しく解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復工事における責任分担の基本的な理解とその法的根拠
原状回復工事における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化(時間が経って自然に古くなること)」なのか「入居者の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。
この責任分担の理解が、工事業者選択の権利を左右する重要な要素となります。
民法第606条および第621条では、賃借人には「善管注意義務(注意深く大切に扱う義務)」があり、通常の注意をもって物件を使用・管理する義務があるとされています。
一方で、貸主には通常損耗(普通に使っていてできる傷み)に対する修繕義務が課せられています。

- 民法第606条(賃貸人による修繕等)
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責に帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 - 民法第621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、入居者負担となる損傷について、工事業者の選択権は基本的に入居者にあることが示されています。
ただし、貸主が負担する通常損耗については、貸主が業者を選定する権利があります。
壁紙の耐用年数(使える期間の目安)は6年、畳の耐用年数は6年など、具体的な基準により責任分担が決定され、これに基づいて工事発注の権限も決まります。
入居期間が長期にわたる場合は、経年劣化による価値減少を考慮した負担割合に応じて業者選択権も調整されることがあります。
つまり、原状回復工事の業者選択権は、損傷の原因と責任分担によって決まり、入居者負担部分については入居者が業者を選ぶ権利があり、適正な見積もりを取得することで費用を抑制できます。
原状回復工事の業者は自分で選べる?

原状回復工事の業者を自分で選べるケース
借主が原状回復工事の業者を自由に選択できる場合は、賃貸借契約書に特別な制限条項がなく、かつ貸主または管理会社が承諾(同意すること)している状況です。
この場合、費用削減や工事品質の向上を目的として、複数の業者から見積もりを取得することが可能になります。
具体的には、契約書に「借主指定業者での工事可能」との記載がある場合や、退去時に管理会社から複数の選択肢を提示された場合などが該当します。
借主は相見積もりを取り、価格や工事内容を比較検討できます。
ただし、選択した業者が適切な資格や保険を持っているか確認が必要で、工事後のトラブル対応についても事前に取り決めておくことが重要です。
また、工事品質が基準を満たさない場合は追加工事が必要となるリスクもあるため、実績のある信頼できる業者を選定することが求められます。
原状回復工事の業者を自分で選べないケース
多くの賃貸物件では、原状回復工事の業者を借主が自由に選択することはできません。
これは管理会社や貸主が品質管理とトラブル防止の観点から、指定業者制度を採用しているためです。
特に大手不動産会社が管理する物件では、この傾向が顕著に見られます。
契約書に「指定業者での工事実施」との条項がある場合、借主は必ず指定された業者を利用しなければなりません。
これは工事品質の統一、アフターサービスの確保、責任の所在の明確化といった理由によるものです。
指定業者制度では、価格が相場より高めに設定されることもありますが、工事不良によるトラブルが発生した際の対応が迅速で、保証制度も整備されています。
借主が勝手に他の業者を使用した場合、契約違反となり、やり直し工事や違約金の支払いを求められる可能性があります。
このため、契約内容を事前に十分確認することが必要です。
原状回復工事業者を自分で選ぶ際のポイントと賃貸借契約書に記載されている注意すべき条項の例
賃貸借契約書には、原状回復工事の業者選択に関する重要な条項が記載されており、これらを見落とすと後々トラブルの原因となります。
契約締結前に該当箇所を入念にチェックし、不明な点は必ず確認することが重要です。

条項例
- 貸主指定業者使用に関する条項
借主は、原状回復工事を実施する場合、貸主が指定する施工業者を使用するものとする。やむを得ず借主が業者を選択する場合は、事前に貸主の書面による承認を得なければならない。承認を得ずに施工した場合は、借主の責任において再工事を行うものとする。 - 業者選択事前承認制に関する条項
借主が独自に施工業者を選定する場合は、当該業者の資格・実績・保険加入状況等を明記した書面を貸主に提出し、施工開始前に承認を得るものとする。貸主は合理的理由なく承認を拒否しないものとするが、技術力・信頼性に疑義がある場合は承認を保留することができる。 - 工事品質基準及びやり直し規定に関する条項
施工された工事が貸主の定める品質基準に満たない場合、または一般的な施工水準を下回る場合は、借主の費用負担により適正な水準まで補修・やり直しを行うものとする。品質基準については契約締結時に別途定めるものとする。 - 複数見積取得及び業者選定に関する条項
借主は原状回復工事の実施にあたり、複数の施工業者から見積書を取得し、価格・工期・施工内容を総合的に検討の上、最も適切な業者を選定するよう努めるものとする。見積書の写しは貸主に提出し、施工内容について事前協議を行うものとする。 - 工事完了検査及び免責に関する条項
工事完了後、貸主は相当な期間内に検査を実施し、不備がある場合は借主に補修を求めることができる。借主選択業者による施工不良・手抜き工事等が原因で追加補修が必要となった場合、その費用は借主が負担するものとし、貸主は一切の責任を負わないものとする。
代表的な条項として「原状回復工事は貸主指定業者にて実施すること」「借主による業者選択は事前承認制とする」「工事品質が基準に満たない場合は借主負担でやり直しを行う」などがあります。
また「見積書(工事費用の予想額を示した書類)は複数業者から取得し、最安値業者を選択すること」という条項や「工事完了後30日以内に貸主による検査を実施する」といった品質管理に関する規定も重要です。
さらに「借主選択業者による工事不良の場合、追加費用は借主負担とする」という免責条項にも注意が必要です。
これらの条項を理解せずに業者を選択すると、予想外の費用負担や工事のやり直しが発生するリスクがあります。
原状回復工事は自分でやってもいい?

原状回復工事を自分でやってもいいケース
軽微な損傷や汚れについては、借主が自分で修繕することが認められているケースがあります。
特に、日常的な清掃レベルの作業や簡単な補修であれば、賃貸借契約で禁止されていない限り自己対応が可能です。
具体的には、壁の小さな画鋲穴の補修、軽微な汚れの清掃、フローリングのワックスがけ、水回りのカビ取り清掃などが該当します。
これらの作業は専門技術を必要とせず、市販の補修材料で対応可能です。
ただし、作業前には必ず管理会社や大家に連絡し、許可を得ることが重要です。
また、修繕箇所の写真を撮影し、使用した材料や作業内容を記録として残しておくことで、後日のトラブルを防げます。
自己修繕により退去費用を大幅に削減できる場合もありますが、仕上がりの品質には十分注意が必要です。
原状回復工事を自分でやってはいけないケース
電気工事、水道工事、ガス工事など専門的な資格が必要な作業や、建物の構造に関わる修繕については、借主が自分で行うことは法的に禁止されています。
また、広範囲の修繕や高度な技術を要する作業も避けるべきです。
壁紙の全面張り替え、フローリングの張り替え、水回りの配管修理、電気配線の修理、エアコンの取り付け・取り外しなどは専門業者に依頼する必要があります。
これらの作業を素人が行った場合、かえって損害を拡大させたり、安全上の問題を引き起こしたりする可能性があります。
また、借主が無断で行った修繕工事が原因で事故が発生した場合、賠償責任を問われる可能性もあります。
さらに、不適切な修繕により物件価値を下げてしまった場合、原状回復費用以上の損害賠償を求められることもあるため、専門性の高い作業は必ず業者に依頼しましょう。
原状回復工事を自分でやる際のポイントと賃貸借契約書に記載のある注意すべき条項例
多くの賃貸借契約書には、借主による修繕行為に関する制限や手続きについて明記されています。
これらの条項を見落とすと、契約違反となり追加費用が発生する可能性があります。
条項例
- 修繕工事事前承諾に関する条項
借主が物件内において修繕工事を実施する場合は、工事内容、使用材料、施工方法、工事期間等を明記した書面により、事前に貸主の承諾を得なければならない。承諾を得ずに実施した修繕については、借主の費用負担により原状回復を求めることがある。 - 原状回復義務に関する条項
借主が実施した修繕工事については、契約終了時に貸主指定の専門業者による検査を受けるものとし、施工不良や基準不適合が認められた場合は、借主の責任において専門業者による修正工事を実施するものとする。 - 損害拡大責任に関する条項
借主が自己判断により修繕を行った結果、不適切な施工方法や材料使用により損害が拡大した場合、借主は拡大した損害を含む全ての修繕費用及び損害賠償責任を負うものとする。また、近隣住戸への影響についても借主が責任を負う。 - 使用材料指定に関する条項
借主が修繕工事において使用する材料は、貸主が指定する品質基準に適合するものでなければならず、指定メーカー・指定品番がある場合はこれに従うものとする。代替材料を使用する場合は事前に貸主の承認を得るものとする。 - 施工業者承認に関する条項
借主が修繕工事を実施する場合は、適切な資格・保険を有する貸主承認済みの施工業者を使用するものとし、個人や無資格業者による施工は禁止する。承認を得ていない業者による施工で生じた損害については、借主が全責任を負うものとする。
代表的な条項として「修繕工事の事前承諾条項」があり、借主が修繕を行う前に書面による許可を得ることを義務付けています。
「原状回復義務条項」では、借主による修繕であっても最終的には専門業者による確認が必要とされる場合があります。
「損害拡大責任条項」では、不適切な自己修繕により損害が拡大した場合の責任範囲が定められています。
また、「使用材料指定条項」により、修繕に使用する材料が指定されている場合もあります。
契約書を詳細に確認し、不明な点は契約前に質問することが重要です。
条項に違反した場合、契約解除や損害賠償請求のリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
まとめ

原状回復工事の業者選定については、借主が修繕責任を負う損傷に限り、原則として借主に選定権があります。
一方、DIY対応はまず賃貸借契約書の内容確認から始めることが最も重要で、契約書で借主による修繕が禁止されている場合は軽微な補修であっても一切行ってはいけません。
契約上問題がない場合でも、画鋲穴の補修や軽度の清掃作業などの軽微な作業に限定し、専門技術を要する工事は必ず専門業者に依頼しましょう。
重要なのは、まず損耗の性質を正確に判断し、責任分担を明確にすることです。
トラブルを避けるためには、入居時に原状回復に関する取り決めを明確にし、退去時には国土交通省ガイドラインを参考に客観的な判断を行い、作業前には貸主や管理会社の承諾を得ることが大切です。
疑問や問題が生じた場合は、一人で悩まず専門機関に相談し、適切な解決を目指しましょう。
- 大多数の賃貸物件では「指定業者制度」が適用され、借主の自由選択は制限される。貸主が承諾した場合のみ例外可
- 指定業者以外での工事は契約違反となり、やり直し工事や違約金のリスクがある。借主選定業者の工事不良は全責任を負う
- 契約締結前に「原状回復工事」「修繕条項」(指定業者・材料・事前承諾)を確認し、不明点は解消する
- 軽微な補修や清掃は自己実施可能(要事前確認)。専門資格が必要な工事(電気・水道等)は業者依頼必須
- 不適切な修繕で損害が拡大した場合、原状回復費以上の賠償責任が発生する可能性あり
- 修繕時は写真・作業内容を記録し、証拠を残す