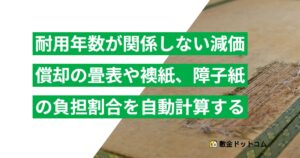【賃貸アパートに1年未満】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?
賃貸アパートに入居して1年未満で退去する場合、退去費用はどのくらいかかるのでしょうか。国土交通省のガイドラインでは、設備や内装材ごとに「耐用年数」が定められており、入居期間に応じて借主の費用負担が変わります。
1年未満の短期退去では、設備の残存価値が高いため借主の負担割合が大きくなる傾向があります。ただし、すべてが借主負担になるわけではなく、通常の使用による損耗は貸主負担です。
この記事では、耐用年数の制度と仕組みをわかりやすく解説したうえで、1年未満退去時の設備別費用相場、負担割合の計算方法、そして費用を抑えるための具体的な対策をお伝えします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
耐用年数の制度と仕組みを知ろう
1-1. 耐用年数とは何か
耐用年数とは、設備や内装材が通常の使用で使い続けられる年数の目安です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、この耐用年数に基づいて退去時の費用負担を算出します。
- 経年劣化の基準:年数が経つほど設備の残存価値が下がり、借主負担も減少する
- 1年未満の場合:残存価値が高いため、借主の過失による損傷は高めの負担になりやすい
- 通常損耗は対象外:どれだけ短期でも、普通に暮らして生じた損耗は貸主負担
- 定めがない設備もある:フローリングなど一部の設備には耐用年数の定めがない
1-2. 主な設備の耐用年数一覧
ガイドラインで定められた主な設備・内装材の耐用年数は以下のとおりです。

| 設備・内装材 | 耐用年数 | 1年経過時の残存価値 |
|---|---|---|
| クロス(壁紙) | 6年 | 約83% |
| カーペット | 6年 | 約83% |
| クッションフロア | 6年 | 約83% |
| 畳表 | 経過年数考慮なし | —(消耗品扱い) |
| エアコン | 6年 | 約83% |
| 給湯器 | 6年 | 約83% |
| 流し台 | 5年 | 約80% |
| フローリング | 定めなし | —(部分補修が原則) |
1年未満で退去した場合、借主の過失による損傷があると修繕費の約80〜85%を負担することになります。以下は主な設備別の費用相場です。
- 壁紙クロス(1面張替え):修繕費2〜4万円×残存83%=借主負担1.7〜3.3万円
- カーペット(6畳):修繕費4〜6万円×残存83%=借主負担3.3〜5万円
- クッションフロア(6畳):修繕費3〜5万円×残存83%=借主負担2.5〜4.2万円
- エアコン修繕:修繕費1〜3万円×残存83%=借主負担0.8〜2.5万円
2-1. 耐用年数の定めがない設備の費用相場
フローリングや畳表など、耐用年数の定めがない設備は居住年数による減額が適用されません。
- フローリング(部分補修):損傷箇所のみの補修で1〜3万円程度
- フローリング(全面張替え):借主の過失が広範囲に及ぶ場合、10〜20万円以上
- 畳表替え(1枚):4,000〜8,000円程度(消耗品扱いで全額借主負担の場合あり)
- ユニットバス・洗面台:部分補修が原則。傷の程度により5,000〜3万円程度
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
費用負担割合の計算方法
3-1. 壁紙クロスの計算例
耐用年数が設定されている設備は、「修繕費×残存価値割合」で借主負担を計算します。具体的な計算例を見てみましょう。
- 前提条件:入居8ヶ月で退去、タバコによる壁紙のヤニ汚れで1面張替え
- 修繕費:壁紙1面の張替え費用=30,000円
- 残存価値:耐用年数6年のうち8ヶ月経過→残存約89%
- 借主負担額:30,000円×89%=約26,700円
3-2. 特約がある場合の注意点
契約書にクリーニング特約や短期解約違約金が定められている場合、上記の負担割合計算とは別に費用が発生します。1年未満で退去する際は、特に以下の特約に注意が必要です。
- 短期解約違約金:「1年未満の退去は家賃1ヶ月分」など→家賃とは別途発生
- クリーニング特約:入居期間に関わらず一定額の負担→2〜5万円程度
- フリーレント違約金:無料期間分の家賃を返還する条項がないか確認
- 鍵交換特約:入居期間に関わらず負担→1〜2万円程度
1年未満で退去する場合、原状回復費用に加えて短期解約違約金やクリーニング特約の費用が上乗せされることがあります。退去を決める前に、契約書の特約欄を必ず確認しましょう。
退去費用を抑える予防策と対応
4-1. 入居直後から始められる対策
短期退去が見込まれる場合は、入居直後から退去費用の対策を始めておくことが重要です。
- 入居時の写真撮影:壁・床・天井・設備を日付入りで撮影し保存する
- 既存の傷を報告:発見した傷・汚れをメールなど書面で管理会社に報告する
- 契約書の特約を把握:短期解約違約金やクリーニング特約の有無を確認する
- 傷防止グッズの活用:家具の脚にフェルトパッド、壁に保護シートを貼る
4-2. 退去時の交渉ポイント
見積書が届いたら、以下のポイントを確認して交渉しましょう。
- 経年劣化の控除:修繕費から残存価値に応じた減額がされているか確認
- 通常損耗の除外:日焼けや家具跡など通常使用の損耗が含まれていないか
- 施工範囲の妥当性:損傷は一部なのに全面張替えの費用を請求されていないか
- 単価の相場比較:修繕単価が市場相場と大きく乖離していないか
1年未満の短期退去でも、通常の使用による損耗は貸主負担が原則です。「入居期間が短いからすべて借主負担」という請求は正しくありません。ガイドラインの計算方法を理解して、適正な負担額かどうかを確認しましょう。
管理会社との交渉で解決しない場合は、専門機関に相談することで適正な解決につながります。


| 相談先 | 特徴 | 費用 |
|---|---|---|
| 消費生活センター(188番) | 退去費用トラブルの相談・助言。まず最初に相談すべき窓口 | 無料 |
| 法テラス(0570-078374) | 収入要件を満たせば弁護士費用の立替制度を利用可能 | 無料相談あり |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭問題を簡易裁判所で1日で審理 | 手数料数千円 |
原状回復義務の詳しい範囲については、以下の記事で解説しています。
まとめ:耐用年数を理解して適正な費用負担を判断しよう
1年未満の短期退去では費用負担が大きくなりがちですが、耐用年数と残存価値の仕組みを理解しておけば、不当な請求に対して根拠をもって交渉できます。
この記事のポイント
- 1年未満退去の費用負担
- 耐用年数6年の設備は残存価値約83%→借主負担は修繕費の約8割
- 通常損耗は入居期間に関わらず貸主負担が原則
- フローリング・畳表は耐用年数の定めがなく部分補修が基本
短期退去でも諦める必要はありません。耐用年数の表と計算方法を手元に控えておき、見積書の各項目と照合してみてください。適正な負担額との差額が大きい場合は、ガイドラインを根拠に減額交渉しましょう。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 耐用年数や残存価値の計算はガイドラインに基づくものであり、契約書の特約が優先される場合があります。