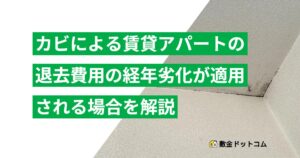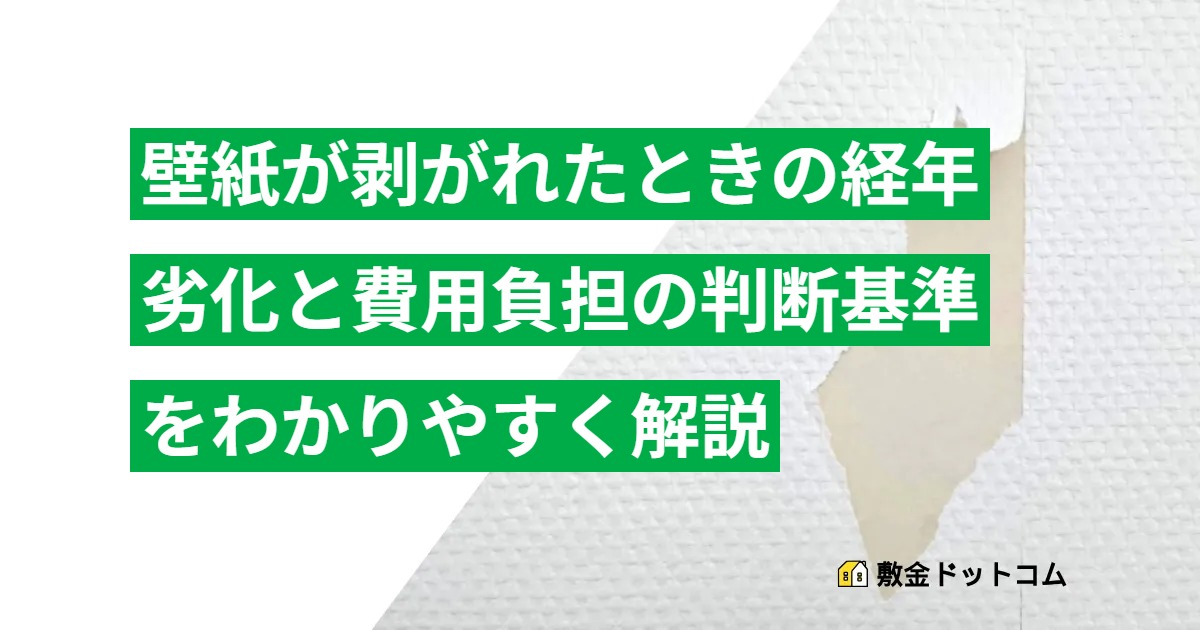
【壁紙が剥がれたときの退去費用】経年劣化と費用負担の判断基準
「賃貸の壁紙が剥がれてしまった…退去費用はいくらかかるの?」「経年劣化なら負担しなくていいって本当?」——退去を控えた方にとって、壁紙の損傷と費用負担は大きな不安要素ではないでしょうか。
結論から言えば、壁紙の剥がれが「経年劣化」によるものか「入居者の過失」によるものかで、費用負担者が変わります。さらに、入居期間が6年を超えている場合は、壁紙の残存価値がほぼゼロになるため、借主負担が大幅に軽減されます。この記事では、費用負担の判断基準から張り替え費用の相場、高額請求への対処法まで解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
壁紙の費用負担は「経年劣化か過失か」で決まる
国土交通省のガイドラインでは、壁紙(クロス)の耐用年数を6年と定めています。退去費用の負担は「経年劣化・通常損耗」と「借主の過失」のどちらに該当するかで大きく変わります。
- 接着剤の劣化:年数の経過により接着力が低下して剥がれた場合
- 湿気による浮き:建物の構造上の問題で湿気がこもり壁紙が浮いた場合
- 日焼けによる変色:日光が当たる場所の壁紙が色あせた場合
- 画鋲・ピンの穴:カレンダーやポスターを留めた小さな穴
- 家具の設置跡・電気ヤケ:家具や家電の背面にできた日焼け跡や黒ずみ
一方、以下のケースでは借主が費用を負担します。ただし、借主の過失であっても入居年数に応じた減価償却が適用されるため、全額負担にはなりません。
- 物をぶつけた傷・釘穴・テープ跡:家具移動時の破損や強力テープによる剥がれ
- タバコのヤニ汚れ:喫煙による変色・臭いは全面張替えになりやすい
- ペットの引っかき傷:猫の爪とぎや犬のかじり跡は通常損耗に該当しない
- 結露放置によるカビ:適切な換気を怠った結果の損傷は善管注意義務違反
入居期間と借主負担割合の関係
壁紙の耐用年数は6年で、6年以上入居していれば残存価値は1円となり、借主の負担はほぼゼロになります。借主の過失で壁紙が剥がれた場合でも、入居期間に応じて負担額は減額されます。

| 入居期間 | 残存価値(目安) | 借主負担の考え方 |
|---|---|---|
| 1年 | 約85% | 張替え費用の約85%を負担 |
| 3年 | 約50% | 張替え費用の約50%を負担 |
| 5年 | 約17% | 張替え費用の約17%を負担 |
| 6年以上 | 1円(ほぼゼロ) | 原則として負担なし |
「6年以上住んでいるのに壁紙の全額交換費用を請求された」という場合は、ガイドラインに基づいて減額交渉ができます。入居期間を証明できる契約書のコピーを用意しておきましょう。
入居期間ごとの具体的な負担割合は、ガイドラインの負担割合表で確認できます。
壁紙の張り替え費用の相場
ペットによる損傷の費用目安
ペットによる壁紙の損傷は借主負担となり、損傷の程度によって費用が大きく変わります。タバコのヤニやペットの傷は経年劣化の減額が適用されにくいため、特に注意が必要です。


| 損傷内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 壁紙の引っかき傷 | 1面あたり3〜5万円 | 猫の爪とぎ被害が多い |
| 壁紙の剥がれ・破れ | 部分補修1〜3万円 | 犬がかじった場合など |
| 臭いの染み付き | 消臭1〜5万円 | 壁紙交換が必要な場合も |
| 下地まで損傷 | 追加で1〜3万円 | 下地ボードの補修費用 |
場所・広さ別の張り替え費用
壁紙の張り替え費用は、㎡単価×面積で算出されます。1㎡あたり800〜1,500円が相場で、場所や広さによって総額が変わります。


| 場所 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| リビング(6畳) | 4〜6万円 | 天井を含まない壁のみ |
| キッチン | 4〜8万円 | 油汚れ対策の壁紙は割高 |
| トイレ | 3〜7万円 | 狭いが作業効率が下がる |
| 洗面所 | 4〜7万円 | 防カビ壁紙を使用する場合も |


| 部屋の広さ | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 6畳 | 4〜5万円 | 壁のみ(天井除く) |
| 8畳 | 5〜6万円 | 同上 |
| 1K全体 | 8〜12万円 | 全室張り替えの場合 |
| 1LDK全体 | 12〜18万円 | 同上 |
部分的な損傷であれば、㎡単位での補修が原則です。「1ヶ所の傷で全面張替え」を請求された場合は、ガイドラインを根拠に部分補修を求める交渉が可能です。
高額請求への対処と剥がれ発見時の対応
壁紙の剥がれを発見したら、すぐに写真を撮影して証拠を残し、自分で修繕せずに管理会社へ報告しましょう。無断修繕は材質の不一致や契約違反のリスクがあり、経年劣化の証明も困難になります。
退去時に納得できない高額請求を受けた場合は、以下のステップで対処しましょう。
- 請求内訳の確認:項目ごとの金額と算出根拠を書面で求める
- ガイドラインと照合:国土交通省ガイドラインに照らして妥当性を確認
- 経年劣化の主張:入居期間を根拠に減価償却分の減額を交渉
- 専門機関に相談:解決しない場合は消費生活センターや少額訴訟を検討
管理会社との交渉で解決しない場合は、消費生活センター(188番)に相談しましょう。無料で専門的な助言やあっせんを受けられます。60万円以下の請求であれば少額訴訟も有効な手段です。
退去立会い当日の注意点も事前に把握しておくと安心です。
壁紙の剥がれは退去時のトラブルになりやすい項目の一つです。入居時から写真を撮影しておくこと、剥がれを発見したらすぐに管理会社へ報告すること、そして退去時にはガイドラインを確認して交渉に臨むことが重要です。
まとめ:壁紙の剥がれで損をしないために
壁紙が剥がれた場合の退去費用は、「経年劣化か過失か」「入居期間は何年か」によって大きく変わります。ガイドラインを理解し、適切な証拠を残すことで、不当な請求に対抗できます。
この記事のポイント
- 費用負担の判断基準
- 経年劣化・通常損耗は貸主負担
- 故意・過失による損傷は借主負担
- 6年以上の入居で残存価値はほぼゼロ
- トラブルを防ぐ対策
- 剥がれを発見したら写真で記録
- 自分で修繕せず管理会社へ報告
- 高額請求にはガイドラインを根拠に交渉
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 原状回復費用の相場や判断基準は、物件や地域、契約内容によって異なる場合があります。