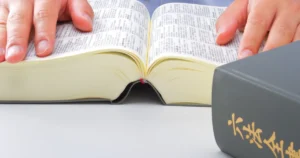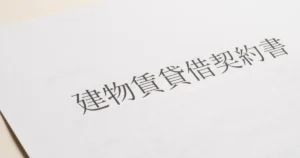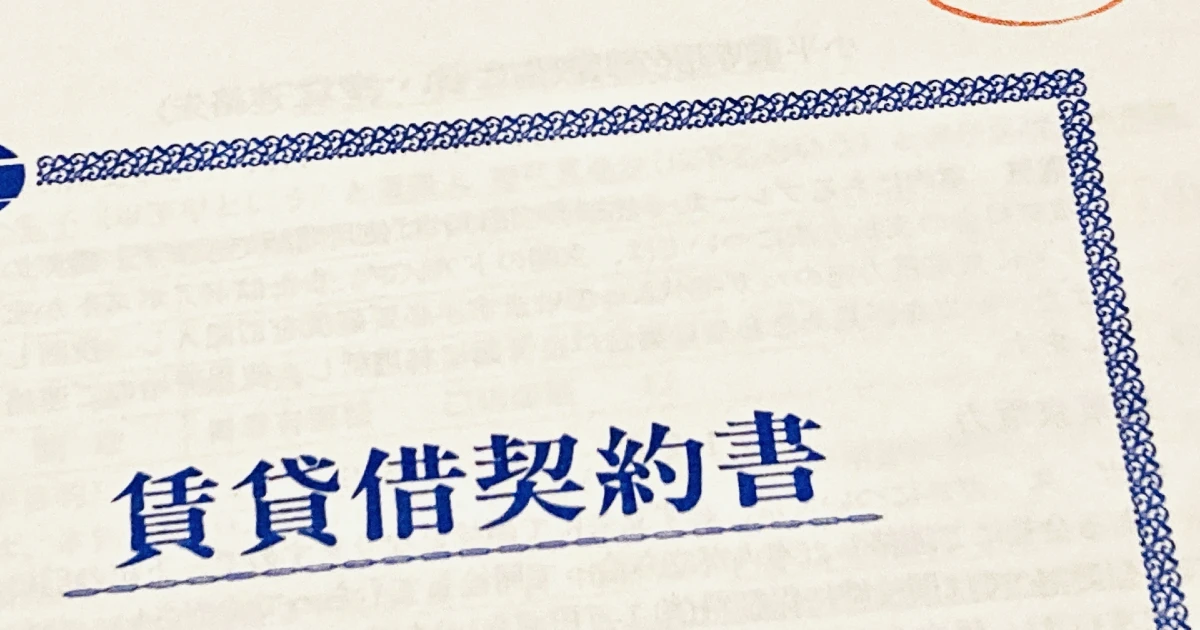
【賃貸借契約書の読み方】退去立会い前に見るべきポイントを解説
賃貸物件からの退去を控えているあなたは、賃貸借契約書を退去立会い前に必ず読み返すことで、不当な原状回復費用の請求を防ぐことができます。
契約書には、退去時の負担区分や特約事項が記載されており、国土交通省のガイドラインと照らし合わせることで自分の権利を守れるのです。
本記事では行政書士の視点から、契約書の基本構成や重要な条文の読み方、さらに原状回復に関わる具体的なチェックポイントを解説します。
記事を読み終える頃には、退去立会いで不利益を被ることなく、適正な費用負担について自信を持って対応できるようになるでしょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸借契約書の基本構成とは?
賃貸借契約書は、賃貸住宅における貸主と借主の権利義務を定めた重要な法的文書になります。
契約書の基本構成を理解することで、退去時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
契約書の構成要素を押さえる
賃貸借契約書は一般的に、タイトル、前文、本文、後文、署名欄の5つの要素で構成されています。
タイトルには「建物賃貸借契約書」などの文書名が記載され、前文では契約当事者の特定と契約締結の意思が示されるでしょう。
本文は契約内容の中核を成す部分で、賃料や契約期間、物件の使用方法、原状回復義務などの具体的な取り決めが条文として記載されます。
後文では契約書の作成部数や保管方法が明記され、最後の署名欄で貸主と借主が署名押印することで契約が成立するのです。
本文の条文番号の読み方
契約書の条文番号は、「条→項→号→ア・イ・ウ」という階層構造で整理されており、正確な読み方を理解する必要があります。
たとえば「第5条第2項第3号イ」と表記されている場合、第5条の中の第2項、その中の第3号、さらにその中のイという意味になるでしょう。
条文を引用する際は、「第5条第2項第3号イの規定により」のように正確に特定することが求められます。
この階層構造を理解しておくと、退去立会い時に管理会社が根拠とする条文を素早く確認でき、適切に対応可能です。
契約書の条文番号は法律文書特有の表記方法です。階層構造を理解しておくことで、退去時の費用負担に関する条項を正確に把握できるでしょう。
契約書の重要な法的表現を理解できる?
賃貸借契約書には、法的な意味を持つ特殊な表現が多数使用されており、正しい解釈が不可欠になります。
特に退去時の費用負担に直結する表現を理解しておくことで、不当な請求を防ぐことが可能です。
接続詞の使い分けを知る
契約書では「並びに」「及び」「又は」「若しくは」といった接続詞が厳密に使い分けられています。
「並びに」と「及び」はどちらも並列を示しますが、「並びに」は大きなグループを結ぶ際に使用され、「及び」は小さなグループを結ぶ際に使用されるのです。
たとえば「壁及び天井の汚損並びに床の傷」という表現では、「壁及び天井の汚損」が一つのグループ、「床の傷」が別のグループとして扱われています。
同様に「又は」と「若しくは」も選択を示しますが、「若しくは」は小さな選択肢を結び、「又は」は大きな選択肢を結ぶという違いがあるでしょう。
数量表現の正確な意味
契約書における数量表現は、その境界値の扱いによって意味が大きく変わります。
「以上」と「超えて」は似ていますが、「10万円以上」は10万円を含むのに対し、「10万円を超えて」は10万円を含まないという違いがあるのです。
同様に「以下」と「未満」についても、「10万円以下」は10万円を含みますが、「10万円未満」は10万円を含みません。
原状回復費用の負担区分を定める条項で「敷金の範囲内」と「敷金を超えて」では、敷金額ちょうどの請求が含まれるかどうかが異なってくるでしょう。
期間表現の計算方法
契約書の期間表現では、「から起算して」と「から」、さらに「から~まで」という表現の違いを理解する必要があります。
「契約締結日から起算して7日以内」という場合、契約締結日当日を1日目として数える初日算入の原則が適用されます。
一方「契約締結日から7日以内」の場合は、契約締結日の翌日を1日目として数える初日不算入が原則となるのです。
退去通知の期限や敷金返還の期限など、期間に関する条項を正確に理解しておくことで、権利を適切に行使できるでしょう。
法的表現の微妙な違いが、退去時の費用負担を大きく左右します。特に数量表現と期間表現は、具体的な金額や日数に直結するため注意が必要です。
退去時に確認すべき条項はどれ?
退去立会い前には、原状回復に関連する条項を重点的に確認する必要があります。
国土交通省のガイドラインと照らし合わせながら、自分の契約書の内容を確認することが重要です。
原状回復義務の範囲を確認する
原状回復とは、借主が退去時に部屋を入居時の状態に戻す義務のことですが、すべての損耗を回復する必要はありません。
国土交通省のガイドラインでは、通常損耗(普通に使っていてできる傷や汚れ)と経年劣化(時間の経過で自然に発生する劣化)は貸主負担とされています。
借主が負担すべきなのは、故意や過失、善管注意義務違反によって生じた損傷のみとなるのです。
たとえば、家具の設置跡による床のへこみや日焼けによる壁紙の変色は通常損耗に該当し、借主負担にはならないでしょう。
一方、タバコのヤニ汚れやペットによる傷、掃除を怠ったことによるカビなどは借主負担となります。


- 家具の設置跡による床のへこみ(通常損耗・貸主負担)
- 日焼けによる壁紙やフローリングの変色(経年劣化・貸主負担)
- 画鋲やピンの穴(通常損耗・貸主負担)
- タバコのヤニ汚れや臭い(借主負担)
- 掃除を怠ったことによるカビや水垢(借主負担)
特約条項の有効性を判断する
賃貸借契約書には、ガイドラインと異なる内容の特約が記載されている場合があります。
しかし、すべての特約が有効になるわけではなく、借主に不当に不利な内容の特約は無効となる可能性があるのです。
国土交通省のガイドラインでは、特約が有効となるための要件として、特約の必要性と合理性があること、借主が特約の内容を明確に認識していること、借主が特約による義務負担の意思表示をしていることの3点を挙げています。
たとえば「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担」という特約は、契約書に金額が明示されており契約時に十分な説明があった場合には有効と判断される可能性が高いでしょう。
一方「通常損耗も含めすべての原状回復費用は借主負担」といった包括的な特約は、消費者契約法により無効とされる可能性があります。
敷金の返還条件を把握する
敷金は賃料の不払いや原状回復費用の担保として貸主に預けるお金ですが、退去時には原則として返還されるものです。
契約書には敷金の返還時期や返還方法、控除できる費用の範囲が記載されており、これらの条項を事前に確認しておく必要があります。
一般的には、退去後1か月から2か月以内に敷金が返還されることが多く、原状回復費用や未払い賃料がある場合には敷金から控除されるでしょう。
ただし、通常損耗の補修費用や次の入居者を迎えるための設備更新費用など、本来貸主が負担すべき費用を敷金から控除することは認められません。
敷金の返還請求権は民法上の債権として認められており、正当な理由なく返還を拒否された場合には法的手段を取ることも可能です。
特約の有効性は個別の事情によって判断されます。不当な特約だと感じた場合は、消費生活センターや専門家に相談することをお勧めします。
退去立会いでの実践的な対応方法は?
契約書の内容を理解したら、退去立会い当日に実践的な対応を取ることが重要になります。
事前準備と当日の対応次第で、不当な請求を防ぐことが可能です。
立会い前の事前準備
退去立会いの前には、入居時の写真や契約書のコピー、原状回復ガイドラインの該当部分を印刷して持参しましょう。
入居時に撮影した部屋の状態を示す写真があれば、入居後に発生した損傷なのか元からあった傷なのかを明確に判断できます。
また、契約書の原状回復に関する条項や特約部分にマーカーを引いておくと、立会い時に素早く参照できて便利です。
さらに、退去立会い当日には必ずスマートフォンやカメラを持参し、指摘された損傷箇所をすべて撮影しておくことが重要になります。
日付入りの写真を残しておくことで、後日トラブルになった際の証拠として活用できるでしょう。


- 賃貸借契約書のコピー(原状回復条項にマーカー)
- 入居時に撮影した室内の写真データ
- 国土交通省ガイドラインの該当ページ印刷
- 撮影用のスマートフォンまたはカメラ
- メモ帳と筆記用具
立会い当日の対応ポイント
退去立会い当日は、管理会社の担当者と一緒に室内を確認しながら、指摘された損傷について一つひとつ記録を取ります。
担当者が借主負担と判断した箇所については、その根拠を契約書の条項番号とともに確認し、ガイドラインの内容と照らし合わせることが大切です。
もし通常損耗や経年劣化と思われる損傷を借主負担とされた場合は、その場で異議を述べ、ガイドラインの該当箇所を示しながら貸主負担であることを説明しましょう。
ただし、感情的にならず冷静に対応することが重要で、納得できない点は「検討させてください」と保留にして、後日専門家に相談する方法もあります。
立会い時には、すべての指摘事項と担当者の説明内容をメモに残し、可能であれば録音しておくことも有効な手段となるでしょう。
見積書の確認と交渉
退去立会い後に送られてくる原状回復費用の見積書は、項目ごとに詳細を確認する必要があります。
見積書には、修繕箇所、修繕理由、単価、数量、合計金額が明記されているべきで、不明瞭な項目があれば詳細な説明を求めましょう。
特に壁紙の張替えについては、損傷部分だけでなく居室全体の張替え費用を請求されるケースがありますが、ガイドラインでは原則として損傷部分を含む一面分のみの張替えが適正とされています。
見積金額に納得できない場合は、他の業者に相見積もりを取ることも可能で、複数の見積もりを比較することで適正価格を判断できるようになるのです。
また、経年劣化による価値減少を考慮した負担割合の計算がされているかも重要な確認ポイントとなります。
退去立会いは一度しかない重要な機会です。その場で署名を求められても、内容を十分確認してから判断することが大切でしょう。
トラブル時の相談先と法的手続きは?
退去立会いや原状回復費用について貸主や管理会社と話し合っても解決しない場合は、適切な相談先に支援を求める必要があります。
トラブルの程度に応じて、段階的に対応を進めることが効果的です。
行政機関への相談
賃貸住宅のトラブルについては、まず各自治体の消費生活センターや住宅相談窓口に相談することをお勧めします。
消費生活センターでは、専門の相談員が契約内容や見積書を確認し、ガイドラインに基づいた適切なアドバイスを提供してくれます。
相談は無料で受けられ、必要に応じて貸主や管理会社へのあっせんや調停を行ってくれる場合もあるのです。
また、国土交通省や各都道府県の住宅部局でも、賃貸住宅に関する相談窓口を設けており、ガイドラインの解釈について詳しい説明を受けることができるでしょう。
不動産業者が関与している場合は、都道府県の宅地建物取引業担当部署に相談することで、業者への指導を求めることも可能です。
専門家への法律相談
行政機関への相談でも解決しない場合や、高額な請求を受けている場合には、法律の専門家に相談することを検討しましょう。
弁護士や認定司法書士は、契約書の法的な解釈や特約の有効性について専門的な見解を示すことができ、必要に応じて交渉の代理人となることも可能です。
初回相談は無料または低額で受け付けている法律事務所も多く、日本司法支援センター(法テラス)では収入が一定以下の方を対象に無料法律相談を実施しています。
弁護士会や司法書士会でも定期的に無料相談会を開催しているため、まずは気軽に相談してみることで解決の糸口が見つかるかもしれません。
ただし、訴訟などの法的手続きを進める場合には、行政書士の業務範囲を超えるため、弁護士または認定司法書士に依頼する必要があることを理解しておきましょう。
少額訴訟と民事調停の活用
原状回復費用をめぐるトラブルが話し合いで解決しない場合、少額訴訟や民事調停という法的手続きを利用できます。
少額訴訟は、請求金額が60万円以下の場合に利用できる簡易な訴訟手続きで、原則として1回の審理で判決が出されるため迅速な解決が期待できるのです。
申立ては本人でも行うことができ、弁護士を依頼しなくても対応可能ですが、証拠書類の準備や主張の組み立てには注意が必要になります。
民事調停は、裁判所の調停委員が当事者の間に入って話し合いを進める手続きで、双方が合意すれば調停成立となり、合意内容は判決と同じ効力を持つでしょう。
調停は訴訟よりも柔軟な解決が可能で、今後の関係性を考慮した穏便な解決を目指せるという利点があります。
法的手続きは最終手段として考え、まずは行政機関や専門家の助言を受けながら話し合いでの解決を目指すことが望ましいでしょう。
賃貸借契約書の読み方と退去準備のまとめ
賃貸借契約書は、退去時のトラブルを防ぐために必ず読み返すべき重要な文書になります。
契約書の基本構成を理解し、特に本文の条項番号や法的表現の正確な意味を把握することで、自分の権利と義務を明確に認識できるでしょう。
退去立会い前には、原状回復義務の範囲、特約条項の有効性、敷金の返還条件といった重要な条項を確認し、国土交通省のガイドラインと照らし合わせて借主負担の範囲を正しく理解しておくことが不可欠です。
立会い当日は、入居時の写真や契約書、ガイドラインを持参し、指摘された損傷箇所を記録しながら冷静に対応することが大切になります。
見積書の内容に疑問がある場合は、消費生活センターや専門家に相談し、必要に応じて法的手続きを検討することで、適正な費用負担を実現できるのです。
契約書の正しい読み方を身につけることで、退去時の不当な請求を防ぎ、安心して新生活を始められるでしょう。
- 契約書は「条→項→号→ア・イ・ウ」の階層構造で整理されており、退去時の費用負担に関する条項を正確に特定できる
- 「以上」「超えて」「以下」「未満」などの数量表現は境界値の扱いが異なり、費用負担額に直接影響する
- 通常損耗と経年劣化は貸主負担が原則で、借主は故意・過失・善管注意義務違反による損傷のみ負担する
- 特約の有効性は必要性・合理性、借主の明確な認識、意思表示の3要件を満たす必要がある
- 退去立会い前に入居時の写真と契約書、ガイドラインを準備し、当日は指摘事項をすべて記録する