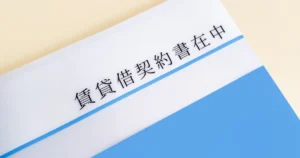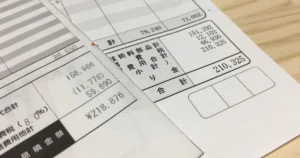オーナーチェンジした場合の敷金返還請求はどうする?
オーナーチェンジが発生した場合、敷金の返還請求は新しい建物所有者に対して行うことになります。
賃貸借契約書に記載された敷金の引き継ぎ義務が新オーナーに承継されるため、借主の権利は基本的に保護されます。
しかし、オーナーチェンジ時には敷金の引き継ぎが適切に行われているかの確認が重要でしょう。
特にファミリータイプの物件では売却されやすい傾向があるため、敷金承継の手続きについて事前に理解しておくことが円満解決への第一歩になります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
オーナーチェンジとは建物所有者が変わることですが、借主の権利はどうなる?
オーナーチェンジとは、賃貸物件の建物所有者が変更されることを指します。
賃貸借契約を結んでいる最中に物件が売却された場合でも、借主の権利と義務は新しい所有者に対してそのまま継続されます。
これは民法の「買主は売主の地位を承継する」という原則に基づいているためです。
具体的には、家賃の支払い義務、契約期間、そして敷金や保証金の取り扱いも含めて、すべての契約内容が新オーナーに引き継がれることになります。

- 賃貸借契約の継続(契約期間や家賃などの条件はそのまま)
- 敷金・保証金の承継義務(新オーナーが引き継ぎ責任を負う)
- 原状回復に関する取り決めの継続
- 借主の居住権の保護
- 契約違反による解除権の承継
ただし、ファミリータイプの物件は単身者向け物件に比べて売却される機会が多い傾向があります。
これは投資回収期間や収益性の観点から、オーナーが物件を手放しやすいためでしょう。
オーナーチェンジがあっても、借主の法的地位は変わりません。新しい所有者は、前の所有者が負っていた義務をすべて引き継ぐことになるのです。
オーナーチェンジ時の敷金承継はどのような仕組みになっている?
オーナーチェンジが発生した際の敷金承継は、法的に明確なルールが定められています。
新しい建物所有者は、前の所有者から敷金を受け取る義務と、借主に対して敷金を返還する義務の両方を承継します。
これにより、借主の敷金返還請求権は確実に保護される仕組みになっているのです。
具体的な承継の流れとしては、売買契約時に前の所有者から新しい所有者へ敷金相当額が引き渡されることが一般的でしょう。
敷金承継の法的根拠とは?
敷金承継の法的根拠は、民法の特定承継の原則に基づいています。
建物の所有権移転に伴い、敷金返還債務も新所有者に当然に移転するため、借主は新しいオーナーに対して敷金の返還を求めることができます。
ただし、実務上は売買契約書に敷金の引き継ぎに関する条項が明記されていることが重要になります。


- 前所有者から新所有者への敷金引き渡し
- 借主への所有者変更通知
- 新しい家賃振込先の案内
- 敷金預かり証の再発行(必要に応じて)
- 契約条件の継続確認
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、東京では敷金の平均返還率が42%にとどまっており、2ヶ月分の敷金のうち1ヶ月分も返ってこないのが実態です。
オーナーチェンジの際には、このような返還率の低さを念頭に置いて、適切な手続きを踏むことが大切でしょう。
オーナーチェンジ時こそ、敷金の取り扱いについて明確にしておくチャンスです。新しい所有者との関係を良好に保つためにも、最初の段階で確認を取っておきましょう。
敷金返還請求の具体的な手順はどのように進める?
オーナーチェンジ後の敷金返還請求は、通常の退去時と基本的に同じ手順で進められます。
重要なのは、新しい所有者に対して敷金の預託事実と返還請求権があることを明確に伝えることです。
まずは新しい管理会社や大家さんに連絡を取り、敷金の引き継ぎ状況を確認しましょう。
オンラインでの手続きを優先した進め方とは?
現代の賃貸管理では、多くの手続きがオンライン化されています。
まずは管理会社の公式ウェブサイトやアプリから、所有者変更の通知があるかを確認してください。
大手管理会社の場合、入居者向けポータルサイトのマイページに「重要なお知らせ」として所有者変更通知が掲載されることが多いです。
次に、メールや専用フォームを通じて敷金の引き継ぎ状況について問い合わせを行いましょう。


- 管理会社ウェブサイト・アプリでの所有者変更確認
- メールまたは専用フォームでの敷金引き継ぎ状況問い合わせ
- 退去届の電子申請(退去予定日の1ヶ月前)
- 立会い日程の電子調整
- 原状回復費用の電子見積もり受領
- 敷金精算書の電子交付
オンライン手続きが困難な場合は、電話連絡や書面での手続きも可能ですが、記録を残すためにもメールでのやり取りを優先することをおすすめします。
退去時の立会いで注意すべき点は?
オーナーチェンジ後の退去立会いでは、原状回復の基準について新しい所有者や管理会社と認識を合わせることが重要になります。
国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗は借主の負担にならないと明記されています。
特に「壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)」は借主負担とされていますが、下地ボードの張替えが不要な程度であれば原状回復義務はありません。
立会い時には、写真撮影を行い、損傷箇所の確認を双方で行うことで、後のトラブルを避けることができるでしょう。
オーナーチェンジがあった場合は、原状回復の基準について改めて確認を取ることが大切です。新しい所有者が以前とは異なる基準を持っている可能性もあるため注意が必要です。
オーナーチェンジでトラブルを避けるために注意すべき点は?
オーナーチェンジに伴う敷金返還トラブルを避けるためには、事前の準備と適切な対応が欠かせません。
最も重要なのは、賃貸借契約書や敷金の預かり証、家賃の支払い履歴などの書類を適切に保管しておくことです。
オーナーチェンジの際に、新しい所有者に対して借主の権利を証明するために必要になります。
書類の保管と管理のポイントは?
オーナーチェンジに備えて、下記の書類は必ず保管しておきましょう。
| 書類の種類 | 使用場面 |
|---|---|
| 賃貸借契約書(原本) | 契約条件の確認、敷金額の証明 |
| 敷金預かり証・領収書 | 敷金支払いの証明 |
| 家賃支払い履歴 | 契約履行の証明 |
| 入居時の物件状況確認書 | 原状回復範囲の確定 |
| 前回更新時の書類 | 最新の契約条件確認 |
これらの書類は電子データとしてクラウドストレージに保存するとともに、紙の原本も大切に保管することをおすすめします。
複雑な問題が生じた場合の相談先は?
オーナーチェンジに伴って複雑な法的問題が生じた場合は、専門家への相談を検討しましょう。
敷金の引き継ぎが適切に行われていない場合や、新しい所有者が敷金の存在を否認するような場合には、認定司法書士や弁護士への相談が必要になります。
また、消費生活センターでも賃貸住宅に関する相談を受け付けており、初回の相談先として活用できるでしょう。


- 消費生活センター(初回相談・情報収集)
- 認定司法書士(140万円以下の紛争解決)
- 弁護士(高額案件・複雑な法的問題)
- 不動産調停制度(裁判外紛争解決)
- 法テラス(資力要件を満たす場合)
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、争いごとを避けて円満解決を図ることを重視しており、まずは当事者間での話し合いによる解決を目指すことをすすめています。
オーナーチェンジでのトラブル予防には、日頃からの書類管理が重要です。面倒でも契約書類はきちんと保管しておく習慣をつけましょう。
まとめ
オーナーチェンジが発生した場合の敷金返還請求について、重要なポイントを整理してお伝えしました。
新しい建物所有者は法的に敷金返還義務を承継するため、借主の権利は適切に保護されます。
ただし、円滑な手続きのためには事前の準備と適切な対応が欠かせません。
特にファミリータイプの物件では売却される機会が多いため、オーナーチェンジに備えた準備をしておくことが重要でしょう。
日頃から契約書類を適切に保管し、オンライン手続きを活用して効率的に対応することで、敷金返還に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
複雑な問題が生じた場合は、認定司法書士や弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
- オーナーチェンジでも借主の敷金返還請求権は新所有者に承継される
- 賃貸借契約書や敷金預かり証などの書類保管が重要
- オンライン手続きを優先して効率的に対応する
- 原状回復の基準は国土交通省ガイドラインに準拠する
- 複雑な問題は認定司法書士や弁護士に相談を検討する