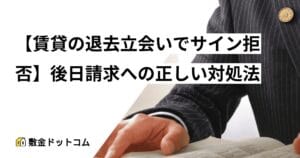退去費用の請求書を無視するとどうなる?敷金以上の請求への対処法
「退去費用の請求書が届いたけど、金額が高すぎて払えない」「敷金を超える請求が来たけど、無視したらどうなるの?」——退去後に届いた請求書の金額に驚き、対応に困っている方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、退去費用の請求書を無視することは絶対に避けるべきです。放置すれば延滞金の発生、保証会社からの督促、最悪の場合は訴訟に発展し、給与や財産を差し押さえられるリスクがあります。
この記事では、退去費用の請求書を無視した場合に起こるリスクから、敷金以上の高額請求への正しい対処法、国土交通省ガイドラインに基づく減額交渉の方法、そして消費生活センターや少額訴訟の活用まで、具体的に解説します。請求書が届いて困っている方、これから退去を控えている方に役立つ情報をお伝えします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
第1章:退去費用の請求書を無視するとどうなる?
1-1. 請求書を放置した場合の流れ
退去費用の請求書を無視し続けると、段階的に深刻な事態へと発展します。「払いたくない」「高すぎる」と感じても、放置は最悪の選択です。
- 督促状の送付(1〜2週間後):管理会社や大家さんから支払いを促す書面が届く
- 電話・訪問による催促(2週間〜1ヶ月後):連絡が取れない場合、電話や新住所への訪問も
- 保証会社からの督促(1〜2ヶ月後):保証会社が立替払いし、借主に請求を開始
- 内容証明郵便の送付(2〜3ヶ月後):法的措置の予告を含む正式な書面が届く
- 訴訟・強制執行(3ヶ月〜):少額訴訟や支払督促を経て、給与・財産の差押えに至る可能性
1-2. 無視することで発生する具体的なリスク
請求書を無視し続けると、金銭的にも社会的にも大きなダメージを受ける可能性があります。
- 延滞金・遅延損害金の発生:年率14.6%程度の遅延損害金が加算されるケースが多い
- 連帯保証人への請求:本人が払わない場合、連帯保証人に請求が行く
- 信用情報への影響:保証会社の記録に残り、次の賃貸契約が難しくなる
- 給与・預金の差押え:訴訟で敗訴すれば、強制執行で財産を差し押さえられる
- 精神的負担の増大:督促が続くことで、日常生活に支障をきたす
請求金額に納得できなくても、無視は禁物です。「支払いを拒否する」のと「対応しない」のは全く別物。納得できない場合は、その旨を書面で伝えて交渉を始めることが重要です。放置すれば、本来払わなくてよい金額まで払うことになりかねません。
第2章:敷金以上の請求が来る理由とその仕組み
2-1. なぜ敷金を超える請求が発生するのか
敷金を預けていたのに、退去後に追加で費用を請求されるケースは珍しくありません。その主な理由を理解しておきましょう。


| 理由 | 具体例 | 対処のポイント |
|---|---|---|
| 原状回復費用が高額 | 壁紙全面張替え、フローリング修繕など | 経年劣化分の減額を主張 |
| 特約による負担 | ハウスクリーニング代、畳表替え費用など | 契約書の特約内容を確認 |
| ペットによる損傷 | 爪傷、臭い染み付き、網戸破損など | 契約時の敷金増額分を考慮 |
| 過剰な請求 | 通常損耗を借主負担とする不当な請求 | ガイドラインに基づき反論 |
| 敷金ゼロ物件 | 初期費用が安い代わりに退去時に費用発生 | 契約時の説明を確認 |
2-2. 敷金返還請求権と時効について
逆に、敷金が正当に返還されない場合は「敷金返還請求権」を行使できます。2017年の民法改正で敷金の定義が明確化され、借主の権利が保護されています。
- 時効は5年:退去から5年以内に請求しなければ権利が消滅
- 名義に関わらず適用:「保証金」「預り金」等の名称でも担保目的なら敷金と同様に扱われる
- 返還義務の発生時期:物件の明渡しが完了した時点で返還義務が発生
- 差し引ける範囲:未払い家賃や借主の故意・過失による損傷の修繕費のみ
第3章:国土交通省ガイドラインで確認する「払うべき費用」
3-1. 原状回復の基本ルール
高額な請求が来た場合、まず確認すべきなのが国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。原状回復とは「入居時の状態に戻す」ことではなく、「借主の故意・過失による損傷を修繕する」ことと定義されています。
- 経年劣化:日照による壁紙の変色、畳の日焼け、設備の自然な劣化
- 通常損耗:家具設置によるカーペットのへこみ、画鋲の穴、冷蔵庫裏の黒ずみ
- 次の入居者のための費用:鍵の交換、消毒、ハウスクリーニング(特約がない場合)
3-2. 耐用年数による減額の仕組み
借主が負担する場合でも、設備の耐用年数に応じて負担額が減額されるのがガイドラインの考え方です。長く住んでいれば、その分負担は軽くなります。
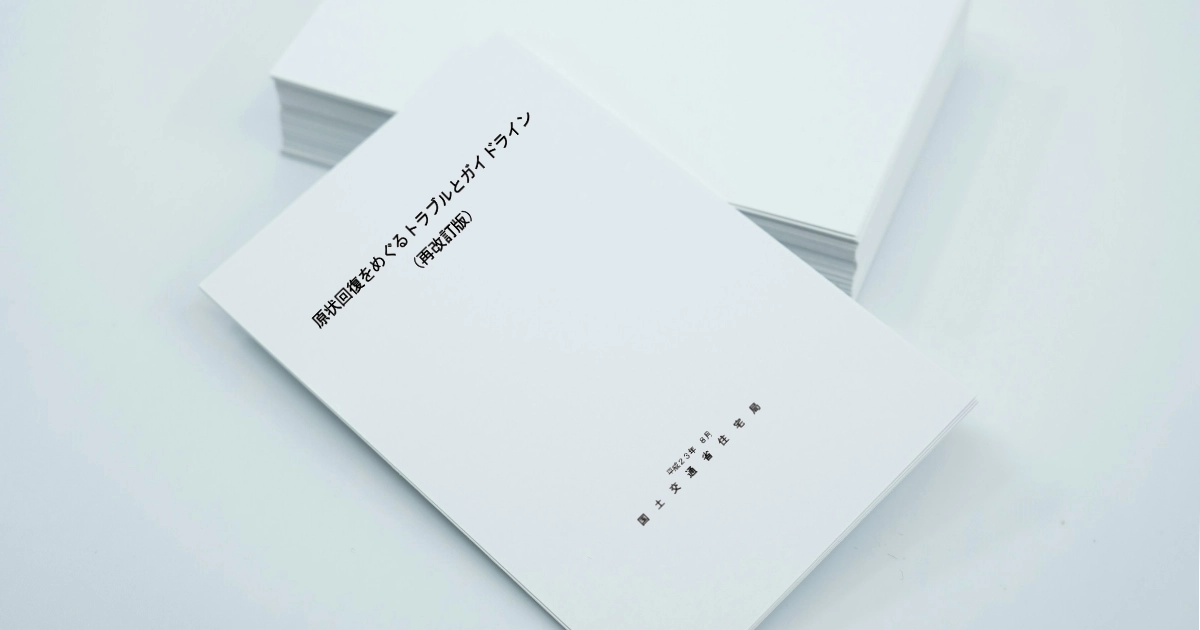
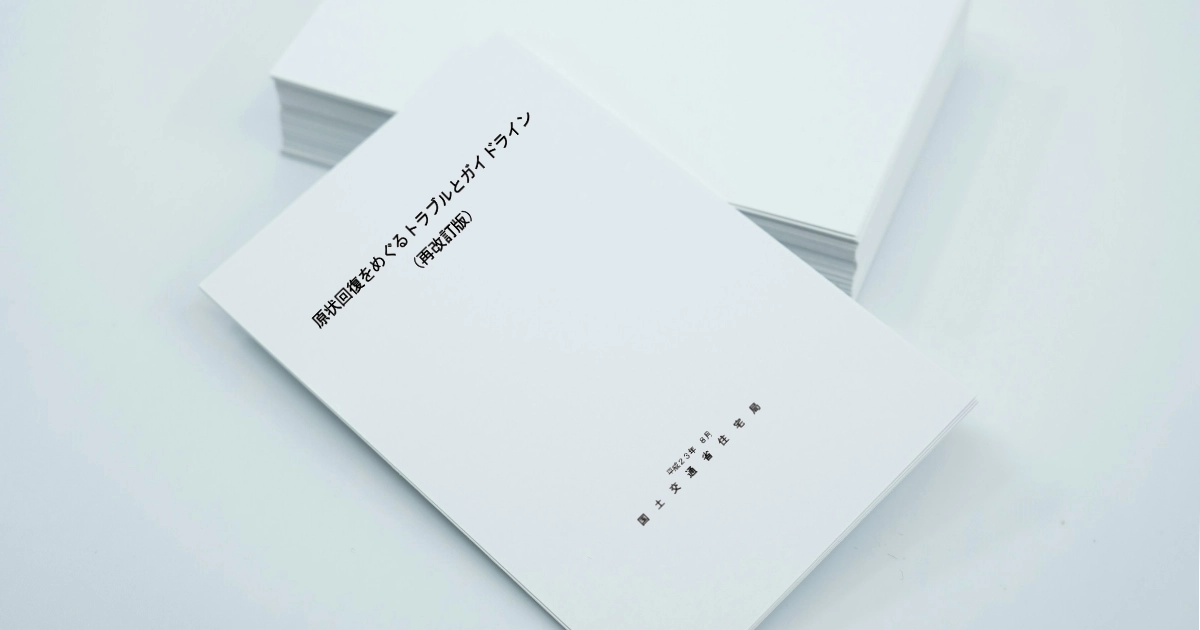
| 設備 | 耐用年数 | 6年居住時の残存価値 |
|---|---|---|
| 壁紙(クロス) | 6年 | 1円(ほぼゼロ) |
| カーペット | 6年 | 1円(ほぼゼロ) |
| クッションフロア | 6年 | 1円(ほぼゼロ) |
| エアコン | 6年 | 1円(ほぼゼロ) |
| ユニットバス・便器 | 15年 | 約60% |
| フローリング | 建物と同じ | 部分補修は経過年数考慮なし |
例えば、6年以上住んでいた物件で「壁紙の全面張替え費用10万円」を請求された場合、ガイドラインに基づけば残存価値は1円。借主負担はほぼゼロになるはずです。請求書の内容と入居期間を照らし合わせて、減額交渉の余地があるか確認しましょう。
第4章:請求書が届いたときの正しい対処法
4-1. まず行うべき3つのステップ
請求書が届いたら、感情的にならず、冷静に内容を確認して適切に対応することが重要です。
- 請求書の内訳を確認:何にいくら請求されているのか、項目ごとにチェック
- 契約書と照らし合わせる:特約の有無、原状回復の範囲を確認
- ガイドラインと比較:貸主負担のはずの項目が請求されていないかを確認
4-2. 納得できない場合の交渉方法
請求内容に疑問がある場合は、書面で根拠を示しながら交渉します。電話だけでなく、記録が残る形でやり取りすることが重要です。
- 具体的な項目を指摘:「〇〇の費用について、ガイドラインでは貸主負担とされています」
- 耐用年数を根拠に:「入居期間が〇年のため、残存価値は〇%です」
- 写真があれば提示:入居時・退去時の写真で入居前からの傷を証明
- 分割払いの相談:正当な請求額でも一括払いが難しければ分割を提案
第5章:話し合いで解決しない場合の対処法
5-1. 消費生活センターへの相談
管理会社との交渉が難航する場合は、消費生活センター(188番)に相談しましょう。敷金トラブルは相談件数が多く、適切なアドバイスを得られます。
- 請求内容の妥当性を判断:ガイドラインに照らして適正かどうかアドバイス
- 交渉方法の助言:どのように主張すべきか具体的に教えてもらえる
- あっせん(仲介):場合によっては管理会社との間に入ってもらえる
- 次のステップの案内:訴訟や調停の手続きについても相談可能
5-2. 内容証明郵便の送付
交渉が決裂し、法的措置を検討する段階になったら、内容証明郵便を送付します。これは「いつ、誰に、どんな内容を送ったか」を郵便局が証明するもので、相手に強いプレッシャーを与えます。
- 書式ルール:1行20字以内、1枚26行以内で作成
- 必要なもの:手紙3部、封筒1通、印鑑、郵便料金(1,500〜2,000円程度)
- 配達証明をつける:相手が受け取った日付を証明できる
- 電子内容証明も可能:インターネットで24時間受付のe内容証明サービスあり
5-3. 少額訴訟の活用
内容証明郵便を送っても解決しない場合は、少額訴訟を検討します。敷金返還請求は多くの場合60万円以下なので、少額訴訟の対象となります。


| 項目 | 少額訴訟 | 通常訴訟 |
|---|---|---|
| 請求額の上限 | 60万円以下 | 上限なし |
| 弁護士 | 不要(本人訴訟が一般的) | 必要な場合が多い |
| 審理回数 | 原則1回 | 複数回 |
| 判決までの期間 | 即日または数週間 | 数ヶ月〜1年以上 |
| 手数料 | 数千円程度 | 請求額により異なる |
| 裁判所 | 簡易裁判所 | 地方裁判所など |
少額訴訟は弁護士を立てずに本人が手続きでき、費用も抑えられます。ただし、できればこの段階に至る前に、話し合いで解決することが望ましいです。訴訟を起こす場合は、時効の5年以内に行う必要があります。
第6章:退去費用トラブルを防ぐための事前対策
6-1. 入居時・退去時にやるべきこと
退去費用のトラブルを防ぐ最も有効な手段は、入居時と退去時の記録です。「言った言わない」を防ぐための証拠を残しましょう。
- 入居時の写真撮影:傷や汚れを日付入りで記録。壁・床・設備すべて撮影
- 入居時チェックシートの提出:管理会社に傷の存在を書面で報告
- 退去時の写真撮影:荷物搬出後の状態を記録。入居時の写真と比較できるように
- 契約書の保管:退去後も精算が完了するまで保管
6-2. 契約時に確認すべき特約
退去費用の多くは契約時の「特約」で決まっています。入居前に特約の内容を把握しておくことで、退去時の想定外の出費を防げます。
- ハウスクリーニング代借主負担:金額の目安(1K:2〜3万円、2LDK:4〜6万円)を確認
- 畳の表替え・襖の張替え:借主負担となる場合の費用を確認
- 鍵交換費用:紛失時だけでなく退去時も借主負担となるケースあり
- エアコンクリーニング:借主負担の特約があるか確認
第7章:よくある質問(FAQ)
まとめ:退去費用の請求書は無視せず、正しく対処しよう
退去費用の請求書を無視することは、延滞金の発生、信用情報への影響、最悪の場合は財産の差押えにつながるリスクがあります。請求金額に納得できなくても、放置せずに適切に対応することが重要です。
この記事のポイント
- 請求書を無視するリスク
- 遅延損害金の加算、保証会社からの督促
- 信用情報への影響で次の契約が困難に
- 最悪の場合、給与・財産の差押え
- 正しい対処法
- 請求内容をガイドラインと照らし合わせて確認
- 納得できない場合は書面で減額交渉
- 解決しなければ消費生活センター・少額訴訟を活用
退去費用の請求書が届いて困っている方は、まず内容を冷静に確認しましょう。ガイドラインに基づけば減額できるケースは少なくありません。一人で悩まず、消費生活センター(188番)に相談することも有効です。無視は最悪の選択。適切に対応すれば、不当な請求から身を守ることができます。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去費用や法的手続きについては、契約書・管理会社・専門家の案内を必ずご確認ください。
- 敷金返還請求権の時効は退去から5年です。交渉が長引く場合は時効に注意してください。