貸主が敷金返還請求を受けたときの対応は?
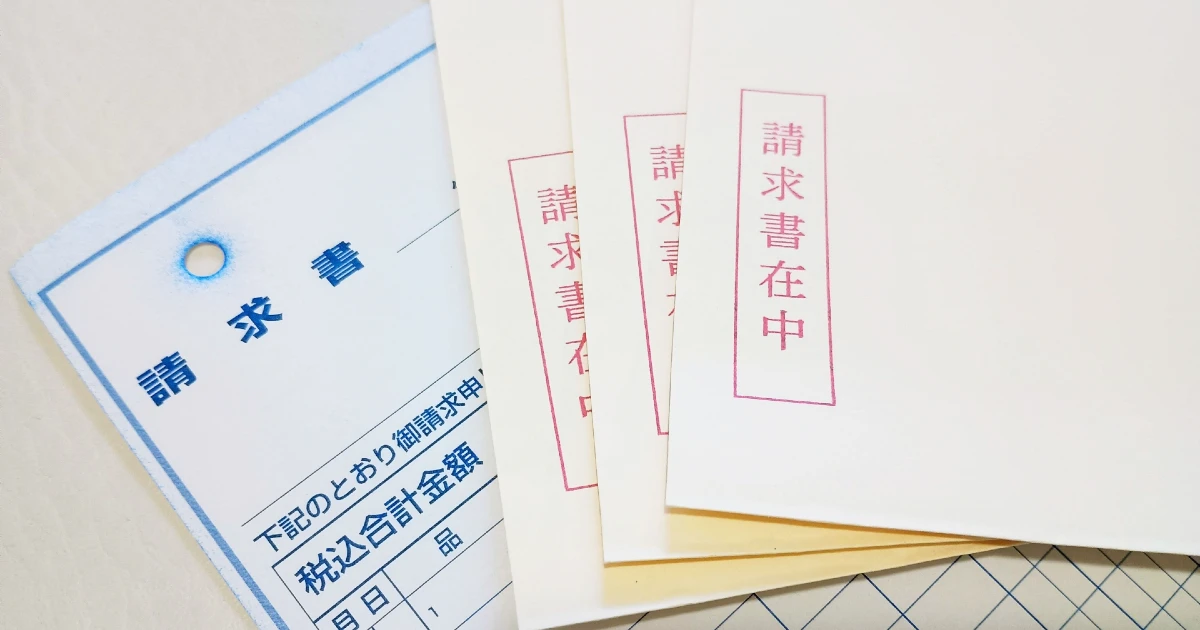
賃貸を管理する貸主にとって、退去時の敷金返還は避けて通れない重要な問題です。
借主から敷金返還請求を受けた際、適切な対応を取らなければ、後々のトラブルに発展する可能性があります。
民法や国土交通省のガイドラインに基づく正しい知識を持つことで、公正かつ円滑な解決が可能になります。
本記事では、敷金返還請求を受けた貸主が取るべき対応方法、よくある間違いとその回避方法、そして実際のトラブル事例を踏まえた実践的なアドバイスをご紹介します。
適切な対応により、借主との良好な関係を保ちながら、法的リスクを最小限に抑えることができるでしょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金返還の基本的な法的仕組みとその法的根拠
敷金返還における責任の所在は、「通常の使用による経年劣化」なのか「賃借人の故意・過失による損傷」なのかによって判断されます。
貸主は法的根拠に基づいて適切な敷金返還を行う義務があります。
民法第622条の2では、敷金返還義務が明文化されており、賃貸借契約終了時に賃借人に対して敷金を返還する義務が規定されています。
ただし、賃借人の債務や原状回復費用がある場合は、これを控除できるとされています。

- 民法第622条の2第1項(敷金)
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。 - 民法第622条の2第2項
賃貸人は、賃借人が賃貸借契約によって負担する費用の償還債務その他の賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務がある場合には、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、賃借人負担となるのは故意・過失による損傷のみであり、通常損耗や経年変化は賃貸人負担が原則とされています。
各設備には具体的な耐用年数が設定されており、壁紙6年、畳表6年、カーペット6年などの基準に基づき、入居期間を考慮した負担割合の計算が必要です。
経年劣化による価値減少分は敷金から控除できません。
つまり、貸主が敷金返還請求を受けた際は、民法とガイドラインに基づいて適正な原状回復費用のみを控除し、残額を速やかに返還することが法的義務となります。
貸主が敷金返還請求を受けたときの対応は?

敷金返還請求を受けたときに間違った対応
敷金返還請求を受けた際の間違った対応は、トラブルの拡大や法的リスクを招く可能性があります。
特に感情的になったり、適切な根拠なく返還を拒否することは避けるべき行為です。
最も多い間違いは、借主からの請求に対して根拠を示さずに一方的に拒否することです。
また、原状回復費用の明細を提示せずに「修繕が必要だから返還できない」と曖昧な説明をすることも問題となります。
さらに、国土交通省のガイドラインを無視して、通常損耗まで借主負担とする主張や、相場を大幅に上回る修繕費用を請求することも法的トラブルを招きます。
借主との連絡を無視したり、返還期限を守らない対応も信頼関係を損ない、最悪の場合は損害賠償請求される可能性があります。
冷静で誠実な対応が求められます。
敷金返還請求を受けたときに正しい対応
敷金返還請求を受けた場合、法的根拠に基づいた冷静で透明性のある対応が重要です。
まずは借主の請求内容を正確に把握し、契約書と照らし合わせて検討することから始めます。
正しい対応手順として、まず入居時と退去時の物件状況を詳細に比較検討し、原状回復が必要な箇所を特定します。
次に、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて、貸主負担と借主負担を明確に分類します。
修繕が必要な場合は、複数の業者から見積もりを取得し、適正価格であることを証明できる資料を準備します。
そして、敷金精算書を作成し、預かり敷金額、修繕費用の内訳、返還額を明記して借主に提示します。
話し合いが必要な場合は、書面でのやり取りを記録し、双方が納得できる解決策を模索することが大切です。
貸主が敷金返還請求を受けたときの対処法と賃貸借契約書に記載する際の注意すべき条項例
将来の敷金トラブルを予防するため、賃貸借契約書には敷金に関する詳細な条項を明記することが不可欠です。
曖昧な表現は後々のトラブルの原因となるため、具体的で明確な記載が求められます。
条項例
- 敷金の使途に関する条項
預託された敷金は、未払い賃料、原状回復費用、その他本契約に基づく借主の債務不履行による損害の補填に充当するものとし、これらの費用を控除した残額があるときは借主に返還する。敷金は賃料の前払いではなく、契約期間中の賃料に充当することはできない。 - 通常損耗負担区分に関する条項
経年変化及び通常の使用による損耗(日照による畳・クロスの変色、家具設置による床・カーペットの凹み、画鋲・ピン等の小さな穴等)については貸主の負担とし、借主の故意・過失・善管注意義務違反による損傷と明確に区別して取り扱うものとする。 - ハウスクリーニング費用特約に関する条項
借主は退去時において、室内の衛生環境を維持し次の入居者への円滑な引き渡しを図るため、専門業者によるハウスクリーニングの実施とその費用負担を行うものとする。本特約は賃料を相場より低額に設定していることを理由として設けるものである。 - 敷金精算手順に関する条項
契約終了時は借主・貸主双方立会いのもと物件状況を確認し、原状回復の要否及び費用負担について協議する。貸主は退去立会い後速やかに敷金精算書を作成し、修繕費用の詳細見積とともに借主に送付するものとする。 - 敷金返還期限に関する条項
貸主は敷金精算完了後、返還すべき金額がある場合は借主指定の口座に速やかに振り込むものとする。精算に異常に長期間を要する場合は、その理由を借主に説明し、概算による仮精算を行うなど借主の不利益とならないよう配慮するものとする。
重要な条項として、敷金の使途を「未払い賃料、原状回復費用、その他契約違反による損害の補填に充当する」と明記し、通常損耗は貸主負担であることを明確に記載します。
また、「借主は退去時に専門業者によるハウスクリーニング費用を負担する」など、特約がある場合は合理的な理由とともに明記する必要があります。
さらに、敷金精算の手順として「退去立会い後30日以内に精算書を送付し、返還額がある場合は60日以内に返金する」といった具体的な期限を設定します。
修繕費用の算定方法や、借主が負担する範囲についても「故意・過失による損傷は借主負担、経年劣化は貸主負担」と明確に区分することが重要です。
敷金返還に関するよくある質問
まとめ
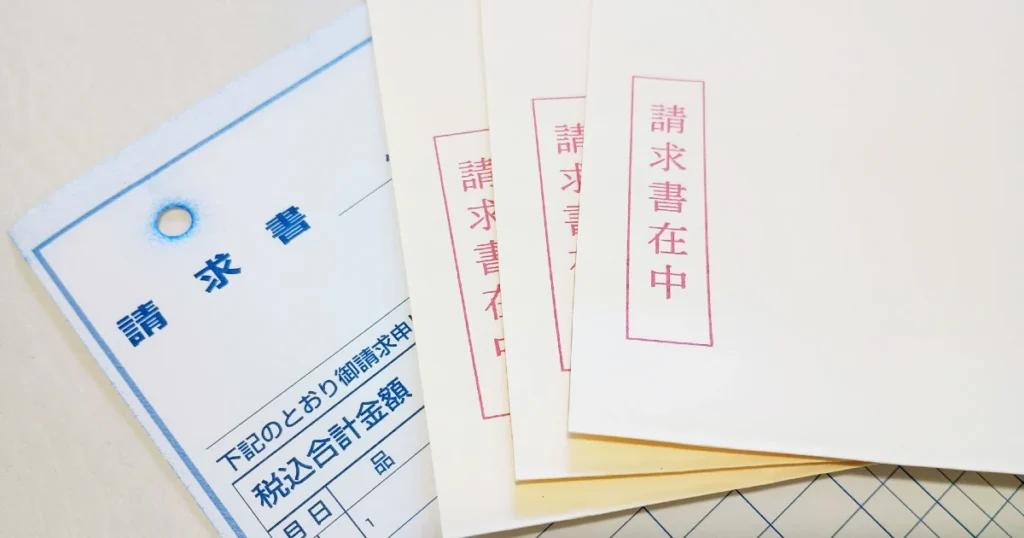
敷金返還請求を受けた貸主は、民法および国土交通省ガイドラインに基づいた適切な対応を取ることが重要です。
感情的な判断ではなく、客観的な根拠に基づいて修繕費用を算定し、借主に対して丁寧な説明を行うことで、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。
日頃から契約時の説明責任を果たし、退去時の記録管理を徹底することで、円滑な敷金返還が実現できるでしょう。
法的知識を正しく理解し、誠実な対応を心がけることが、貸主としての信頼獲得につながります。
- 敷金返還請求に対しては感情的にならず、法的根拠に基づいた冷静な対応が必要
- 修繕費用は国土交通省ガイドラインに従い、適正価格での見積もりを複数取得する
- 敷金精算書は詳細な内訳を記載し、透明性を保って借主に提示する
- 契約書には敷金の使途、精算手順、期限を具体的に明記してトラブルを予防する
- 通常損耗と借主負担の修繕を明確に区分し、書面でのやり取りを記録保存する










