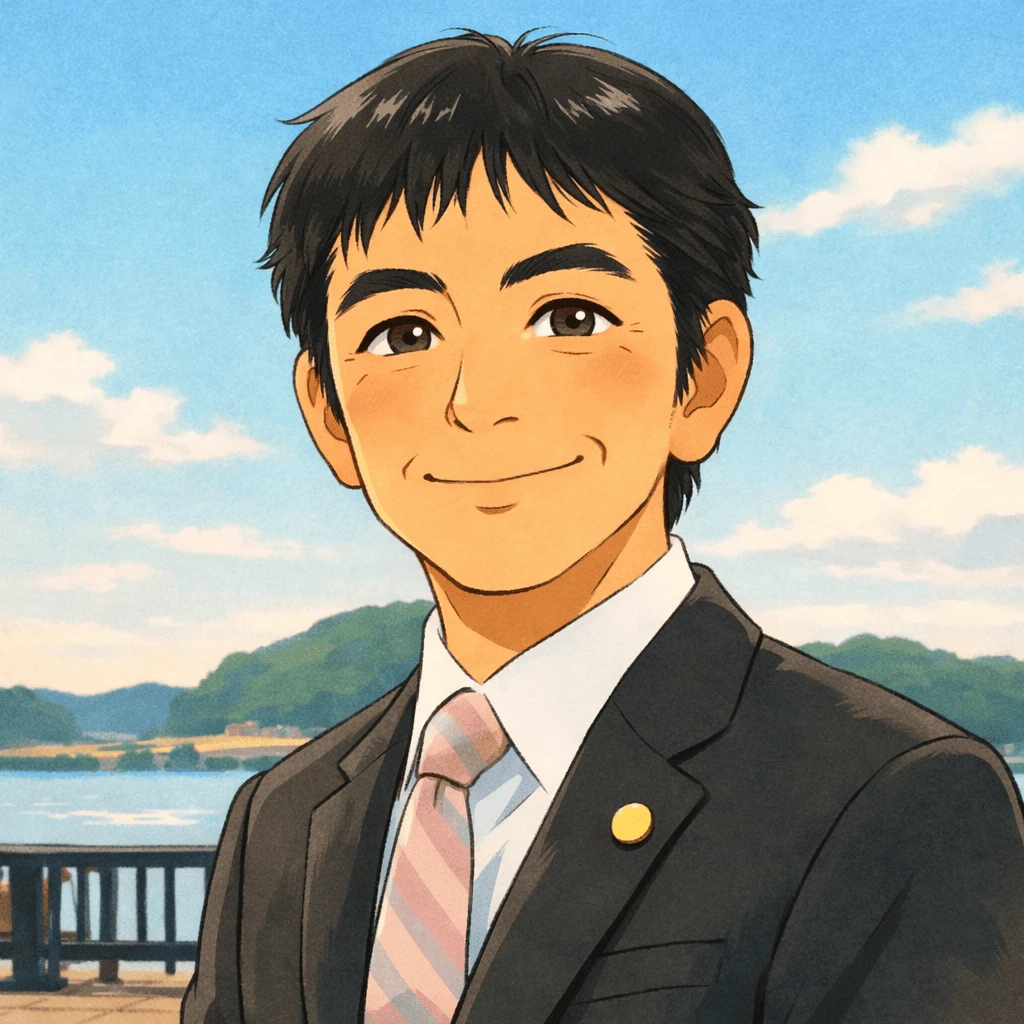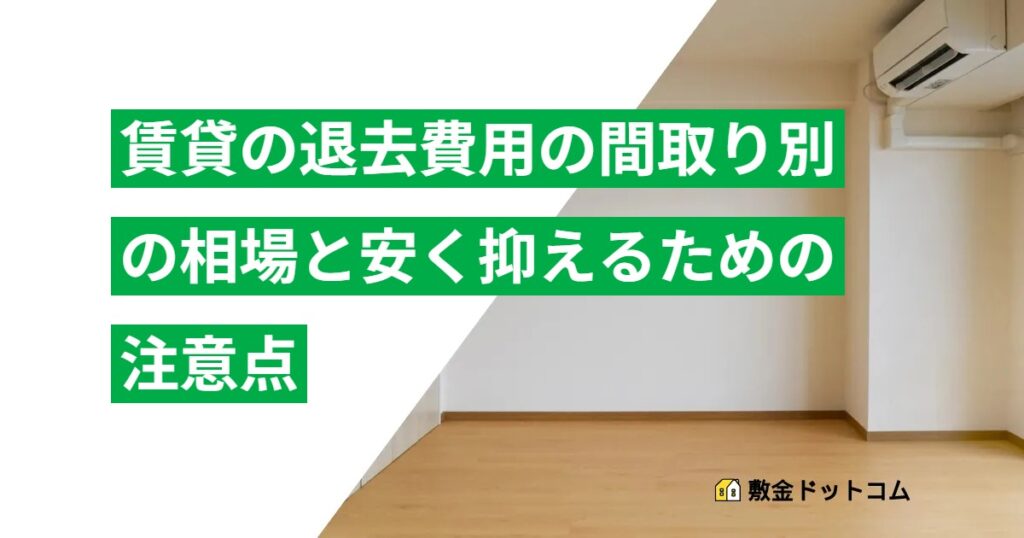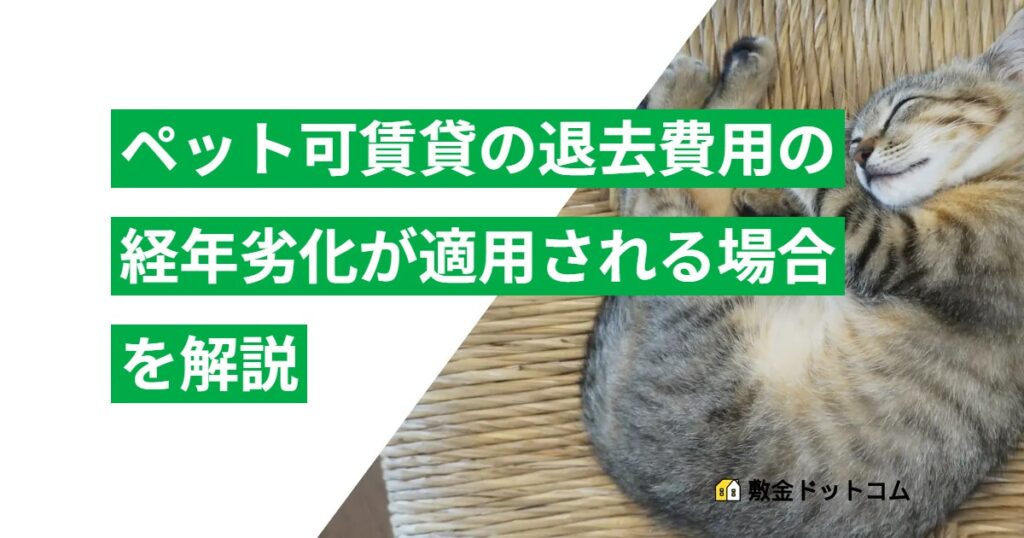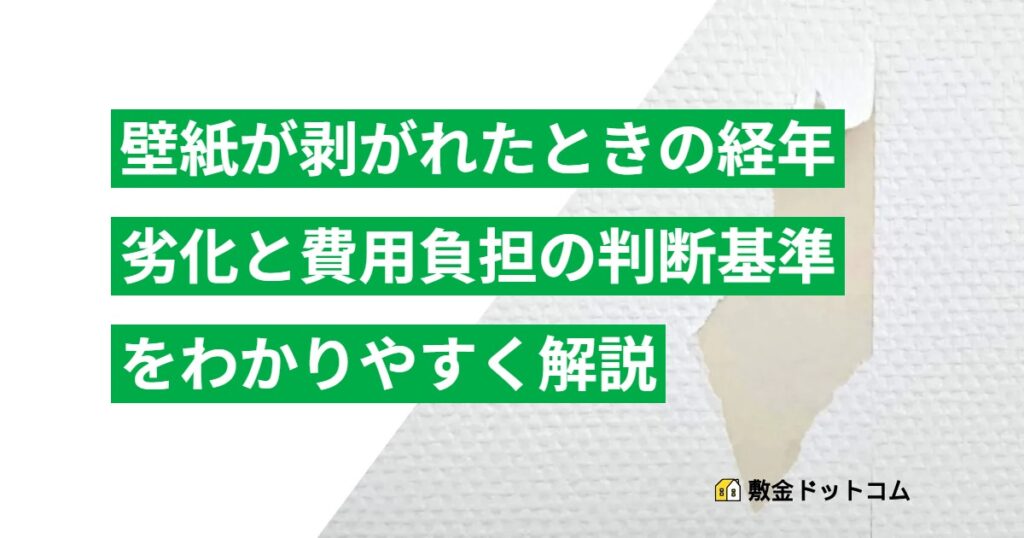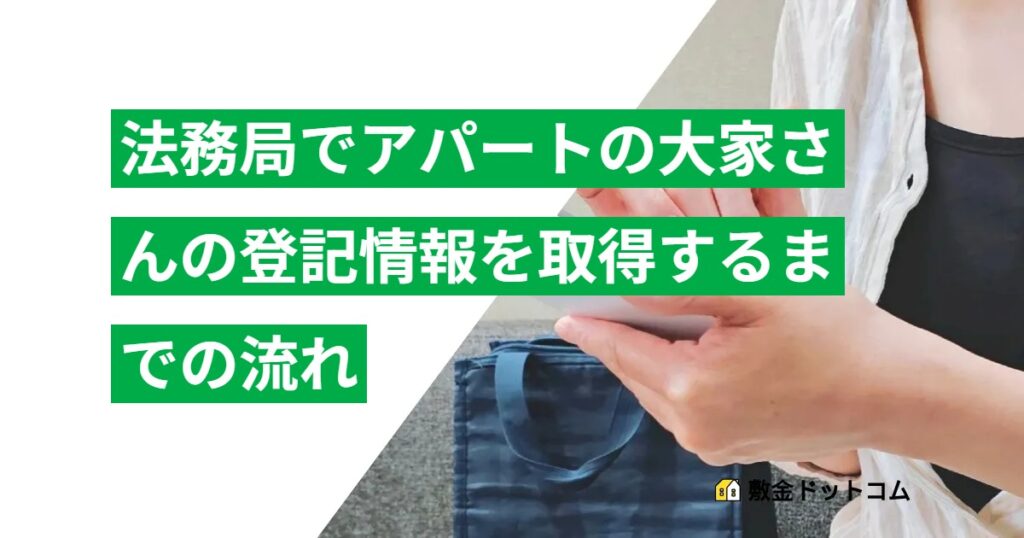2025年– date –
-

【減価償却とは】賃貸物件の退去時における原状回復義務との関係
-

【賃貸のカーペット張替え費用】自分で張り替えや一部だけ取り換えはできる?
-

【賃貸の畳張替えの修繕費用】耐用年数がない畳表替えとの違いと判断基準
-

賃貸の退去費用の間取り別の相場と安く抑えるための注意点
-

賃貸の退去費用はいつ決まる?敷金精算書が届かないときの対処法
-

【ペット可賃貸の退去費用】経年劣化が適用される場合と注意点
-

【フローリングの傷による賃貸の退去費用】耐用年数がない設備の原状回復はどうなる?
-

【賃貸に10~30年】退去費用の相場と耐用年数による負担減の仕組み
-

【壁紙が剥がれたときの退去費用】経年劣化と費用負担の判断基準
-

賃貸アパート7〜10年居住の退去費用と耐用年数ガイドライン
-

【賃貸アパートに1~6年】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?
-

【賃貸アパートに1年未満】設備・内装材の耐用年数と退去費用相場は?
-

敷金AI診断サービス機能強化のお知らせ
-

敷金AI診断サービス 復旧のお知らせ
-

賃貸トラブルで消費者センターの賢い使い方とは?相談から解決までの流れ
-

【アパートの大家さんを調べる方法】法務局で登記情報を取得するまでの流れ
-

【重要事項説明書の注意点】退去費用トラブルを防ぐチェックポイント
-

内見する際にチェックした方がいい項目とは?賃貸の退去トラブルを防ぐ予防策