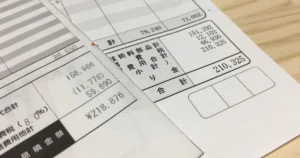【賃貸物件の家具跡】フローリングの傷の修繕費は誰が負担するのか
賃貸物件の退去時に、フローリングの家具跡や傷の修繕費は原則として大家(賃貸人)が負担するものです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、通常の住まい方で発生する家具の設置による床のへこみや軽微な傷は経年劣化・通常損耗として位置づけられており、借主(賃借人)の負担にはなりません。
ただし、家具を引きずって移動させたことで生じた深い傷や、不注意で物を落として作ったへこみなど、故意・過失・注意義務違反による損傷については借主の負担となります。
多くの借主の方は退去時の修繕費について不安を感じておられるでしょう。
適切な知識を身につけることで、不当な費用請求を避け、トラブルのない退去を実現できるようになります。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復義務とは
原状回復義務とは、賃貸物件の退去時に借主が通常の使用を超える損耗や汚損を修繕する責任を負うことを指します。
重要なポイントは「通常の使用を超える」という部分でしょう。
国土交通省のガイドラインでは、故意・過失・注意義務違反による損傷のみが借主の負担対象とされており、普通に住んでいれば発生する傷や汚れは大家の負担となることが明記されています。
通常損耗と故意・過失による損傷の具体的な違い
通常損耗(つうじょうそんもう)とは、普通の住み方をしていても自然に発生する劣化や汚れのことです。
一方、故意・過失による損傷は、借主の不注意や誤った使い方が原因で生じた傷や汚れを意味します。

- 家具の設置による軽微な床のへこみ(通常の重量範囲内)
- 太陽光による自然な色あせや変色
- 普通の歩行による表面の細かなすり傷
- 木材の自然な収縮・膨張による隙間の発生
- 年数経過による艶の減少や光沢の変化
判断基準は「一般的な使用方法であったかどうか」という点になるでしょう。
経年劣化による負担軽減の仕組み
経年劣化とは、時間の経過とともに自然に生じる劣化現象のことです。
住宅設備や内装材は使用していなくても徐々に劣化するものであり、経年劣化による損傷は原則として大家の負担となります。
フローリングの場合、建物の構造部分として建物本体の耐用年数が適用されるため、木造住宅では22年、鉄筋コンクリート造住宅では47年などの長期間にわたって経年劣化が考慮されることになります。
原状回復義務は借主を守るための制度でもあります。適切な知識を持って、不当な請求から身を守りましょう。
フローリングの傷で借主が負担するケースとは?
フローリングの傷について、借主が修繕費を負担する必要があるのは故意・過失・注意義務違反によって生じた損傷のみです。
具体的にどのような傷が借主負担となるのか、実際の事例を見ながら詳しく確認していきましょう。
借主負担となる具体的な損傷事例


- 家具を引きずって移動したことによる深い引っかき傷や溝状の跡
- 重い物を落としたことで生じた大きなへこみや木材の割れ
- 窓の閉め忘れによる雨水侵入で生じた腐食やシミ・カビ
- 飲み物をこぼして放置したことによる変色や板材の膨張
- キャスター付き家具の長期使用による深い溝状の跡や圧痕
注意していただきたいのは、家具を設置したこと自体ではなく、設置や移動の方法に問題があった場合に借主の負担となることです。
たとえば、冷蔵庫やタンスなどの重い家具でも、適切に設置し、保護材を使用していれば、軽微な設置跡は通常損耗として扱われるでしょう。
負担区分の判断における重要な要素
| 判断要素 | 借主負担となるケース | 大家負担となるケース |
|---|---|---|
| 損傷の原因 | 故意・過失・注意義務違反 | 通常使用・経年劣化 |
| 傷の程度 | 深い傷・広範囲の損傷 | 軽微な設置跡・表面的な摩耗 |
| 使用期間 | 短期間での重度損傷 | 長期間居住での自然劣化 |
| 管理状況 | 清掃不良・放置による悪化 | 適切な管理下での劣化 |
判断に迷った場合には、損傷発生の経緯を詳細に記録し、写真などの客観的な証拠を準備することが重要な判断材料となります。
家具を置いたからといって必ず借主負担になるわけではありません。大切なのは使い方や管理の仕方なのです。
フローリングの傷を防ぐ効果的な対策はありますか?
フローリングの傷を防ぐためには、事前の対策が何よりも重要で、適切な保護措置により退去時のトラブルを大幅に減らすことができます。
日常生活の中で簡単に実践できる方法から、本格的な保護対策まで、様々なアプローチが存在するでしょう。
家具による傷を防ぐ具体的な保護方法


- 家具の脚にフェルトクッションやゴムパッドを取り付けて荷重を分散させる
- 重い家具の下にラグやマットを敷いて床面への直接的な負荷を軽減する
- 移動時には必ず持ち上げて運び、引きずり移動を完全に避ける
- 定期的なワックスやコーティング剤の塗布で表面保護を継続する
- 適切な湿度管理で木材の膨張・収縮による損傷を最小限に抑制する
特にキャスター付きの家具については、長期間同じ場所で使用すると深い溝が形成される危険があります。
月に一度程度の位置変更や、厚手の保護マットの使用により、重大な損傷を効果的に防ぐことができるでしょう。
入居時と退去時の記録保管方法
トラブルを避けるためには、入居時と退去時の状況を詳細に記録することが欠かせません。
スマートフォンのカメラで各部屋のフローリング状況を撮影し、日付と時刻の情報も含めて保存しておきましょう。
現況確認書には、発見した傷や汚れの位置、大きさ、程度を具体的に記載し、大家や管理会社との間で認識を確実に共有することが大切です。
予防は治療に勝る、ということですね。少しの手間をかけることで大きなトラブルを回避できます。
修繕費請求の判断基準はどのように決まる?
修繕費の負担区分を判断する際には、損傷の原因、程度、入居期間、使用状況、管理状況などが総合的に考慮されます。
単純に傷があるからといって自動的に借主負担になるわけではなく、ガイドラインに基づいた客観的な判断が行われることになります。
入居年数による負担軽減の計算方法
長期間居住した場合には、経年劣化による価値減少が修繕費から差し引かれる仕組みがあります。
たとえば、10年間居住した借主が家具移動で傷をつけた場合でも、建物の構造部分であるフローリングの経年劣化分を差し引いた金額のみが請求対象となることが多いでしょう。
具体的な計算式は、(修繕費用)×(残存年数÷建物本体の耐用年数)という形で適用され、建物構造に応じて木造22年、鉄筋コンクリート造47年などの長期間が基準となります。
修繕範囲の適切性チェックポイント
請求された修繕範囲が適切かどうかの判断も重要な要素になります。
部分的な補修で済む傷に対して部屋全体のフローリング張り替え費用が請求されるケースも少なくないため、修繕の必要性と範囲を慎重に検証する必要があります。
複数の専門業者から見積もりを取得し、修繕方法や費用の妥当性を比較検討することで、適正な金額を把握できるでしょう。
入居年数が長いほど借主の負担は軽くなります。ガイドラインではこの点も明確に示されているのです。
トラブル発生時の実践的対処法とは?
フローリングの修繕費について大家から請求があった場合、まずは請求の根拠と金額の妥当性を冷静に確認し、ガイドラインに基づいた適切な対応を心がけることが重要です。
感情的にならず、法的根拠に基づいた建設的な話し合いを進めることで、多くのケースで円満な解決が可能になります。
修繕費請求への段階的対応手順


- 請求書の内容詳細確認と修繕対象箇所の具体的特定作業
- 入居時と退去時の写真比較による損傷発生状況の客観的検証
- 国土交通省ガイドラインに基づく負担区分妥当性の論理的検討
- 修繕業者の詳細見積書と施工内容説明書の要求と精査
- 協議による解決困難時の専門家相談と法的手続きの検討開始
相談窓口と法的解決手段
協議では解決できない場合、段階的にいくつかの相談窓口や解決手段があります。
まずは各自治体の消費生活センターや住宅相談窓口で無料相談を受けることから始めましょう。
法的な手続きが必要になった場合には、認定司法書士や弁護士への相談、少額訴訟制度や調停制度の利用により、比較的費用を抑えて解決を図ることも可能です。
一人で悩まず、まずは無料の相談窓口を活用してみてください。専門家の客観的な意見が問題解決の糸口となります。
退去時の立ち会いで注意すべき点はありますか?
退去時の立ち会いは、修繕費負担の最終的な判断が行われる極めて重要な場面であり、適切な準備と対応により公正な判断を受けることができます。
立ち会い時の対応次第で、その後の交渉や解決の方向性が大きく左右されることになるでしょう。
立ち会い当日の準備事項と確認手順


- 入居時の写真と現況確認書の完全な準備と整理
- 国土交通省ガイドラインのコピーとポイント箇所のマーキング
- 室内確認用の懐中電灯や照明器具の準備
- 立ち会い内容の録音・録画機器準備(事前承諾取得必須)
- 客観的判断を支援する第三者同席者の確保
立ち会い時には、各部屋のフローリング状況を順番に確認し、新たに発見された損傷については、発生原因と責任の所在を詳細に話し合うことが重要です。
疑問に感じた点は遠慮なく質問し、納得できる説明が得られるまで粘り強く協議を継続しましょう。
合意書面作成時の重要な記載事項
立ち会いの結果については、必ず詳細な書面で合意内容を確認してください。
口約束だけでは後日重大なトラブルになる可能性があるため、修繕箇所の特定、負担区分の根拠、具体的な金額を明記した合意書を作成することが必要不可欠です。
合意に至らない項目については、協議継続の旨と解決期限を明確に記載し、後日のトラブルを防ぐため立ち会い時の状況写真も併せて保存しておきましょう。
口約束は後々の証拠になりません。面倒でも書面での確認を徹底しましょう。
まとめ
賃貸物件のフローリング修繕費負担については、国土交通省のガイドラインが借主の権利を明確に保護しています。
家具の通常使用による軽微な跡やへこみは大家負担であることが原則であり、借主が過度に心配する必要はありません。
一方で、家具移動時の不注意による深い傷や、清掃不良による汚損については借主の責任となるため、日頃からの適切な管理と注意が重要になります。
最も効果的なトラブル防止策は、入居時から退去時まで一貫した記録の保管と、フローリング保護対策の継続的な実施です。
写真撮影や現況確認書の作成により客観的な証拠を確保し、家具の脚にクッション材を取り付けるなどの基本的な保護対策を実践することで、不当な修繕費請求を効果的に回避できるでしょう。
もしトラブルが発生した場合には、一人で抱え込まずに消費生活センターや専門家への相談を躊躇せずに行ってください。
ガイドラインに基づいた適切な知識と十分な準備があれば、必ず公正な解決に導くことができ、安心して賃貸生活を送ることができるはずです。
- フローリングの家具設置跡は原則として大家負担
- 故意・過失による深い傷や損傷は借主負担
- 事前の保護対策でトラブルを大幅に削減可能
- 入居時と退去時の記録が争点解決の鍵となる
- 不当請求には国土交通省ガイドラインで対抗できる