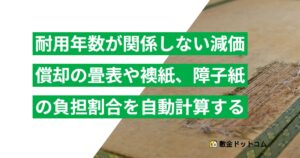賃貸アパート7〜10年居住の退去費用と耐用年数ガイドライン
「7年も住んでいるから退去費用が高くなるのでは?」「10年住んだら壁紙やフローリングの張り替え代を全額請求されるの?」——長く住んだ賃貸アパートを退去する際、こんな不安を感じていませんか?
結論から言えば、7〜10年の長期入居は、退去費用が「高くなる」どころか「安くなる」傾向にあります。その理由は、国土交通省ガイドラインで定められた「耐用年数」と「減価償却」の考え方にあります。
この記事では、7〜10年住んだ賃貸アパートを退去する方に向けて、設備・内装材ごとの耐用年数一覧、居住年数別の借主負担割合の計算方法、実際の退去費用相場、そして高額請求された場合の対処法まで、具体的に解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
7〜10年住むと退去費用が安くなる理由
1-1. 耐用年数と減価償却の基本
賃貸物件の設備や内装材には、それぞれ「耐用年数」が定められています。耐用年数とは、その設備が通常使用できる期間の目安であり、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で具体的に示されています。
例えば、壁紙(クロス)の耐用年数は6年です。これは「6年経過すれば、壁紙の価値は1円になる」という考え方を意味します。つまり、7年以上住んでいれば、たとえ壁紙を汚してしまっても、借主の負担はほぼゼロになるのです。
- 経年劣化分は家賃に含まれている:借主は毎月の家賃で経年劣化分を既に支払っている
- 二重負担の防止:退去時にも経年劣化分を請求すると、借主が二重に支払うことになる
- 残存価値の考え方:設備の価値は年々減少し、耐用年数経過後は価値1円として計算
- 公平性の確保:長期入居者と短期入居者の負担バランスを取るため
1-2. 居住年数による負担割合の変化
借主の負担割合は、以下の計算式で算出されます。
借主負担割合 =(耐用年数 − 入居年数)÷ 耐用年数
例えば、壁紙(耐用年数6年)の張り替え費用が10万円で、入居期間が3年の場合:
借主負担 = 10万円 ×(6年 − 3年)÷ 6年 = 10万円 × 50% = 5万円
一方、入居期間が7年の場合、耐用年数の6年を超えているため:
借主負担 = ほぼ0円(残存価値1円)
7〜10年住んでいる方は、多くの設備・内装材が耐用年数を超えています。そのため、通常の使用による損耗であれば、退去費用の大部分が貸主負担となり、借主の支払いは大幅に軽減されます。
2-1. 6年で耐用年数を迎える設備
7年以上住んでいれば、以下の設備は耐用年数を超えており、借主負担はほぼゼロになります。


| 設備・内装材 | 耐用年数 | 7年居住時の残存価値 | 10年居住時の残存価値 |
|---|---|---|---|
| 壁紙(クロス) | 6年 | 1円 | 1円 |
| カーペット | 6年 | 1円 | 1円 |
| クッションフロア | 6年 | 1円 | 1円 |
| エアコン | 6年 | 1円 | 1円 |
| 流し台 | 5年 | 1円 | 1円 |
| ガスコンロ | 6年 | 1円 | 1円 |
2-2. 耐用年数が長い設備と注意点
一方、耐用年数が長い設備は、7〜10年住んでいても負担が発生する可能性があります。


| 設備・内装材 | 耐用年数 | 7年居住時の負担割合 | 10年居住時の負担割合 |
|---|---|---|---|
| ユニットバス | 15年 | 約53% | 約33% |
| 便器・洗面台 | 15年 | 約53% | 約33% |
| フローリング(木造22年) | 建物と同じ | 約68% | 約55% |
| フローリング(RC47年) | 建物と同じ | 約85% | 約79% |
| 畳表・襖紙 | 経年考慮なし | 100% | 100% |
重要な注意点:フローリングは「部分補修」と「全面張り替え」で扱いが異なります。部分補修は経年劣化が考慮されず全額借主負担となりますが、全面張り替えの場合は建物の耐用年数に応じて減価償却されます。この違いを知っておくことが重要です。
2-3. 経年劣化が考慮されない項目
以下の項目は、入居年数に関係なく借主が全額負担する必要があります。
- 鍵の紛失:交換費用は全額借主負担
- ハウスクリーニング:契約で借主負担と定められている場合
- 畳表・襖紙・障子紙:消耗品扱いで経年考慮なし
- フローリングの部分補修:補修費用は全額借主負担
- 設備の故意による破損:経年劣化とは別に全額請求される場合あり
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
7〜10年居住の退去費用シミュレーション
3-1. 間取り別の退去費用相場
7〜10年の長期入居の場合、多くの設備が耐用年数を超えているため、退去費用は短期入居者より大幅に安くなる傾向があります。


| 間取り | 2〜3年居住の相場 | 7〜10年居住の相場 | 主な費用内訳 |
|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K | 3〜5万円 | 2〜4万円 | ハウスクリーニング代が中心 |
| 1DK・1LDK | 4〜7万円 | 3〜5万円 | クリーニング+消耗品交換 |
| 2DK・2LDK | 6〜10万円 | 4〜7万円 | クリーニング+部分補修 |
| 3DK・3LDK | 8〜15万円 | 5〜10万円 | クリーニング+複数箇所補修 |
※上記は通常の使用による損耗の場合の目安です。故意・過失による破損がある場合は別途費用が発生します。
3-2. 具体的な計算例(8年居住の場合)
2LDKの木造アパートに8年住んだAさんのケースで、退去費用を計算してみましょう。
- 壁紙張り替え(リビング):工事費8万円 → 耐用年数6年超過 → 借主負担0円
- クッションフロア張り替え:工事費4万円 → 耐用年数6年超過 → 借主負担0円
- フローリング部分補修(傷):補修費2万円 → 経年考慮なし → 借主負担2万円
- ハウスクリーニング:契約特約あり → 借主負担4万円
- 合計:借主負担は6万円(工事費総額18万円のうち)
このケースでは、壁紙とクッションフロアは耐用年数を超えているため借主負担ゼロ。一方、フローリングの部分補修は経年劣化が考慮されないため全額負担、ハウスクリーニングは契約特約に基づき負担となっています。耐用年数の知識があれば、12万円分の請求を回避できた計算です。
高額請求されやすい項目と対処法
4-1. 7〜10年居住者が注意すべき請求パターン
長期入居者は「長く住んでいたから傷みが多い」と思い込み、不当な請求を受け入れてしまうケースがあります。以下のような請求には要注意です。
- 壁紙の全額請求:「汚れているから」と全額請求 → 6年超なら借主負担は1円
- 減価償却なしの請求:工事費をそのまま請求 → 入居年数に応じた減額が必要
- 経年劣化の借主負担:日焼けや変色を請求 → 通常損耗は貸主負担
- 全面張り替えの強要:部分補修で済むのに全面張り替え費用を請求
- 入居前からの傷の請求:写真がないと反論が難しくなるケース
4-2. 退去時の写真撮影
7〜10年住んでいると、入居時の写真が残っていないことが多いでしょう。しかし、退去時の写真撮影だけでも大きな効果があります。
- 日付入りで撮影:スマホの設定で日付表示、または新聞と一緒に撮影
- 全体と詳細の両方:各部屋の全景+傷・汚れのアップ写真
- 撮影箇所:壁4面・床・天井・窓・ドア・水回り・収納内部・ベランダ
- 動画も活用:傷の深さや範囲は動画で記録すると説得力が増す
4-3. 契約書の確認ポイント
退去前に必ず賃貸借契約書を読み返し、以下の項目を確認しましょう。
- 原状回復に関する特約:「ハウスクリーニング代は借主負担」等の記載
- 敷金の精算方法:敷金から差し引く費用の範囲
- 解約予告期間:退去の何ヶ月前に通知が必要か
- 特約の有効性:借主に不利な特約が明確に説明されているか
4-4. 立会い時の注意点
- 金額入りの書類にその場でサインしない:「持ち帰って確認します」と伝える
- 会話を録音する:「言った言わない」を防ぐため
- 同伴者を連れていく:第三者がいると強引な対応を抑制できる
- 耐用年数を主張する:「7年住んでいるので壁紙は耐用年数超過では?」と確認
5-1. 7〜10年居住の敷金返還の目安
長期入居の場合、特別な破損がなければ敷金はほぼ全額返還されるのが原則です。多くの設備が耐用年数を超えているため、通常損耗分を差し引かれることはありません。
- 契約特約のハウスクリーニング代:3〜7万円程度(間取りによる)
- 故意・過失による破損の補修費:該当箇所のみ
- 鍵の紛失による交換費:1〜3万円程度
- 畳表・襖紙の交換費:消耗品として全額借主負担の場合あり
5-2. 敷金返還の請求方法
敷金が返還されない、または不当に減額されている場合は、以下の手順で請求できます。
- 精算明細書を請求:敷金から差し引いた費用の内訳を書面でもらう
- 不当な項目を指摘:耐用年数超過分など、減額すべき項目を計算して伝える
- 内容証明郵便で請求:交渉が進まない場合は書面で正式に請求
- 少額訴訟の検討:60万円以下なら簡易裁判所で少額訴訟が可能
原状回復義務の詳しい範囲については、以下の記事で解説しています。
まとめ:7〜10年の長期入居は退去費用で有利
7〜10年という長期間住んだ賃貸アパートを退去する際、「長く住んだから費用が高くなる」という心配は不要です。むしろ、多くの設備が耐用年数を超えているため、通常損耗であれば借主負担は大幅に軽減されます。
この記事のポイント
- 耐用年数を超えた設備は借主負担ほぼゼロ
- 壁紙・クッションフロア・エアコン(6年)は7年以上で負担1円
- ユニットバス・便器(15年)も減価償却で負担軽減
- 高額請求には冷静に対処
- 減価償却を適用した計算を求める
- ガイドラインを根拠に交渉
- 消費生活センターへの相談も有効
長期入居者にとって最も重要なのは、「耐用年数」と「減価償却」の知識を持つことです。この知識があれば、不当な高額請求を回避し、敷金を適切に返還してもらうことができます。退去前には必ずガイドラインを確認し、自分の負担範囲を把握した上で立会いに臨みましょう。わからないことがあれば、消費生活センター(188番)に相談することをお勧めします。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 原状回復費用の相場や耐用年数は、物件や地域によって異なる場合があります。
- 本記事の内容は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいていますが、契約書の特約が優先される場合があります。