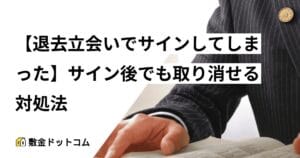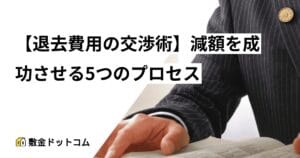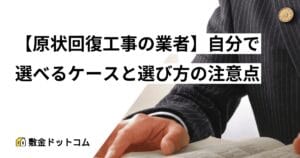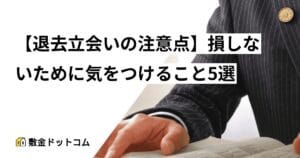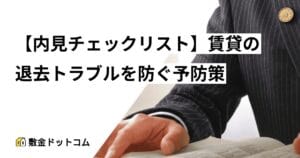退去時の立会いはしたほうがいい?初めての引っ越しで不安な人が知っておきたいポイント
「退去の立会いってしたほうがいいの?」「サインを強要されたらどうしよう」——初めての引っ越しでは、退去時の立会いに不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
結論から言えば、退去立会いは「した方がいい」ケースと「しない方がいい」ケースがあり、一概には言えません。大切なのは、立会いの有無にかかわらず、事前準備をしっかり行うことです。
この記事では、退去立会いの基本的な流れから、立会いをする場合・しない場合のメリットとデメリット、国土交通省ガイドラインに基づく費用負担の考え方、そして初めての退去で不安な方が準備すべきことまで、具体的に解説します。ペットを飼っている方への注意点も含め、退去費用で損をしないためのポイントをお伝えします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
退去立会いとは?基本の流れを知ろう
1-1. 退去立会いの目的
退去立会いとは、賃貸物件を退去する際に、貸主(大家さん)や管理会社の担当者と一緒に部屋の状態を確認する手続きのことです。主な目的は以下の通りです。
- 部屋の損傷・汚れの確認:入居時と比較して、どの程度の損傷や汚れがあるかを確認
- 原状回復費用の算定:借主が負担すべき修繕費用を確定するための基礎資料を作成
- 鍵の返却:すべての鍵(スペアキー含む)を返却
- 残置物の確認:私物の置き忘れがないかをチェック
1-2. 退去立会い当日の一般的な流れ
退去立会いは通常、以下のような流れで進みます。所要時間は30分〜1時間程度が目安です。
- 荷物の搬出完了:立会い前にすべての私物を搬出し、簡単な掃除を済ませておく
- 担当者との合流:約束の時間に管理会社や大家さんの担当者と部屋で合流
- 室内の確認:壁・床・水回り・設備などを一緒にチェック。損傷箇所を確認
- 確認書類への記入:チェックシートや確認書に損傷箇所を記録
- 鍵の返却:すべての鍵を返却し、受領書をもらう
- 退去完了:後日、敷金精算書が届き、費用が確定
退去立会いは法律で義務付けられているわけではありません。「立会いしない方がいい」という意見も見かけますが、それぞれにメリット・デメリットがあります。
2-1. 立会いをする場合
- メリット
- その場で損傷箇所を確認できる:自分が付けた傷かどうかを確認し、入居時からの傷は主張できる
- 認識の相違を防げる:後から「こんな傷があった」と言われるリスクを減らせる
- 交渉の余地がある:経年劣化に該当するものなど、その場で説明・交渉できる
- デメリット
- その場でサインを求められる:冷静に判断できないまま不利な書類にサインしてしまうリスク
- 圧力をかけられる可能性:特に女性一人の場合、強引に同意を求められることも
- 時間の拘束:引っ越し当日に時間を確保する必要がある
2-2. 立会いをしない場合
- メリット
- その場でサインを迫られない:請求書が届いてから冷静に内容を精査できる
- 精神的負担が軽い:対面でのやり取りが苦手な方には負担軽減になる
- 時間の融通が利く:引っ越し当日のスケジュールに余裕ができる
- デメリット
- 一方的に損傷を認定される:自分がいない間にチェックされ、身に覚えのない傷を請求される可能性
- 反論が難しくなる:「現場を見ていない」という弱みになることも
- 写真などの証拠が重要:立会いしない場合は、退去時の写真撮影が必須
立会いをする・しないに正解はありません。ただし、どちらを選んでも「写真による記録」と「契約書の確認」は必須です。立会いをしない場合は特に、退去直前の室内状態を日付入りで撮影しておくことが重要です。
原状回復義務の詳しい範囲については、以下の記事で解説しています。
国土交通省ガイドラインで知る「貸主・借主の負担区分」
3-1. 原状回復の基本的な考え方
退去費用のトラブルを防ぐために、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の基本的な考え方を知っておきましょう。
原状回復とは「入居時の状態に戻す」ことではなく、「借主の故意・過失による損傷を修繕する」ことです。経年劣化や通常の使用による損耗は、原則として貸主(大家さん)の負担となります。


| 損耗の種類 | 具体例 | 負担者 |
|---|---|---|
| 経年劣化 | 日照による壁紙の変色、畳の日焼け | 貸主 |
| 通常損耗 | 家具設置によるカーペットのへこみ、画鋲の穴 | 貸主 |
| 特別損耗(故意・過失) | タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、飲み物をこぼした跡 | 借主 |
| 善管注意義務違反 | 結露を放置したカビ、掃除を怠った油汚れ | 借主 |
3-2. 耐用年数と残存価値の考え方
借主が負担する場合でも、設備の耐用年数に応じて負担額が減額されるのがガイドラインの考え方です。例えば、壁紙(クロス)の耐用年数は6年とされており、6年以上住んでいれば残存価値は1円となり、借主の負担はほぼゼロになります。


| 設備 | 耐用年数 | 備考 |
|---|---|---|
| 壁紙(クロス) | 6年 | 6年経過で残存価値1円 |
| カーペット | 6年 | 同上 |
| クッションフロア | 6年 | 同上 |
| 畳表 | — | 消耗品扱いで経過年数は考慮されない場合あり |
| フローリング | 建物と同じ | 部分補修は経過年数考慮なし |
| エアコン | 6年 | 設備として設置されている場合 |
| ユニットバス・便器 | 15年 | — |
入居期間が長いほど、経年劣化分が考慮されて借主の負担は軽くなります。「6年以上住んでいるのに壁紙の全額交換費用を請求された」という場合は、ガイドラインに基づいて減額交渉ができる可能性があります。
初めての退去で不安な人が準備すべきこと
4-1. 入居時・退去時の写真撮影
退去トラブルを防ぐ最も有効な手段が写真による記録です。理想は入居時の写真ですが、退去時の写真も重要な証拠になります。
- 日付が入る設定で撮影:スマホの設定で日付を表示させるか、新聞などと一緒に撮影
- 全体と詳細の両方を撮る:部屋全体の写真+傷や汚れのアップ写真
- 撮影箇所リスト:壁4面、床、天井、窓、ドア、キッチン、浴室、トイレ、収納内部、ベランダ
- 気になる箇所は動画も:写真では伝わりにくい傷の深さなどは動画で記録
4-2. 契約書・重要事項説明書の確認
退去前に必ず賃貸借契約書と重要事項説明書を読み返しましょう。特に以下の項目をチェックしてください。
- 原状回復に関する特約:「ハウスクリーニング代は借主負担」などの特約があるか
- 敷金の精算方法:敷金から差し引く費用の範囲
- 解約予告期間:退去の何ヶ月前に通知が必要か(通常1〜2ヶ月前)
- ペットに関する特約:ペット可物件の場合、追加の原状回復費用が定められているか
4-3. 同伴者の手配と録音の準備
初めての退去で不安な方、特に女性の一人暮らしの方は、信頼できる人に同伴してもらうことを強くお勧めします。
- 同伴者を連れていく:家族や友人に付き添ってもらう。第三者がいると強引な対応を抑制できる
- 会話を録音する:スマホの録音アプリで会話を記録。「後から言った言わないを防ぐため」と伝えてOK
- 急いでサインしない:「持ち帰って確認します」と言って、その場でサインしない
- 国土交通省ガイドラインを持参:スマホでPDFを見られるようにしておく
5-1. サインを求められた時の対処法
立会いで最も注意すべきなのが、「確認書」や「退去精算同意書」へのサインです。その場でサインを求められても、以下のように対応しましょう。
- 「損傷箇所の確認」のみサイン:「〇〇に傷があった」という事実確認の書類であればサインしてもOK
- 「金額」や「負担割合」が入っている書類は保留:「内容を確認してから後日連絡します」と伝える
- 断り方の例文:「今日は確認だけにして、請求金額が入った精算書は郵送でお願いできますか?」
- 強引に求められたら:「消費者センターに相談してから判断します」と伝える
5-2. 立会い当日の確認チェックリスト
- 持ち物:鍵(すべて)、契約書のコピー、入居時の写真、スマホ(録音・撮影用)、筆記用具
- 事前準備:荷物の搬出完了、簡単な掃除、ライフライン解約手続き
- 確認事項:入居前からの傷は伝える、経年劣化と主張できる箇所を把握、敷金精算の流れを確認
- 心構え:サインを急がない、わからないことは質問、録音していることを伝える
6-1. ペット可物件でも請求されやすい項目
ペット可物件であっても、ペットが原因で生じた損傷は借主負担となります。特に請求されやすい項目を把握しておきましょう。


| 損傷内容 | 具体例 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 壁紙の傷・剥がれ | 猫の爪とぎ、犬がかじった跡 | 1面あたり3〜5万円 |
| 床の傷・汚れ | 爪による引っかき傷、粗相の染み | 部分補修1〜3万円、張替え10万円〜 |
| 柱・建具の傷 | かじり跡、引っかき傷 | 補修1〜3万円 |
| 臭い | ペット臭の染み付き | 消臭・クリーニング1〜5万円 |
| 網戸の破れ | 猫が破った網戸 | 1枚3,000〜5,000円 |
6-2. ペット飼育者が取るべき対策
- 契約時の特約を確認:「ペット飼育に伴う原状回復費用は敷金から充当」などの記載を把握
- 入居時の写真は必須:ペットが付けた傷かどうかの証明に必要
- 退去前に自分で補修できる箇所は対応:市販の補修キットで小さな傷は目立たなくできる
- 消臭対策を徹底:退去前にペット用消臭剤で臭い対策をしておく
- 敷金の増額分を確認:ペット可物件は敷金が1〜2ヶ月分上乗せされていることが多い
ペット可物件でも「ペットが原因の損傷は全額借主負担」という特約が入っていることが多いです。この場合、経年劣化による減額も適用されないことがあるため、契約書の確認は必ず行いましょう。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
まとめ:退去立会いで損をしないために
退去立会いは「した方がいい」「しない方がいい」と意見が分かれますが、どちらを選んでも事前準備が最も重要です。写真による記録、契約書の確認、ガイドラインの理解があれば、不当な請求に対抗できます。
この記事のポイント
- 立会いの有無にかかわらず必須の準備
- 退去時の写真を日付入りで撮影
- 契約書の原状回復特約を確認
- 国土交通省ガイドラインを把握
- 立会い当日のポイント
- 同伴者を連れて行く(特に女性一人の場合)
- 会話を録音する
- その場で金額入りの書類にサインしない
初めての退去で不安な方は、一人で抱え込まず、家族や友人に相談してみましょう。立会いに同伴してもらうだけでも心強いですし、客観的な視点でアドバイスをもらえます。また、請求内容に納得できない場合は、消費生活センター(188番)に相談することも有効です。事前準備をしっかり行えば、退去費用で大きく損をすることは避けられます。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 原状回復費用の相場や耐用年数は、物件や地域によって異なる場合があります。