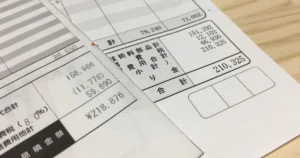【賃貸のふすま・障子の破損はいくら】耐用年数がない、ふすま・障子が破れた場合の退去費用はどうなる?
賃貸住宅でふすまや障子が破れた場合、退去時の修繕費用負担は破損の原因によって大きく変わります。
国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、自然損耗(経年劣化)による破損は貸主負担、借主の過失による破損は借主負担という基本原則が明確に示されています。
ふすまや障子の場合、明確な耐用年数は設定されていませんが、通常の使用による消耗や日焼けは自然損耗として扱われるため、修繕費用を請求される心配はありません。
ただし、故意または重大な過失によって破損させた場合は、修繕費用の負担が必要になることもあるでしょう。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
賃貸でふすま・障子が破れた場合の負担区分
賃貸住宅におけるふすまや障子の破損については、原状回復ガイドラインに基づいた明確な判断基準が存在します。
原状回復とは、借主が借りた当時の状態に戻すことを意味しますが、すべての損耗を借主が負担するわけではありません。
自然損耗による破損は貸主負担
ふすまや障子の表面に生じる軽微な汚れや日焼け、通常使用による小さな穴や破れは、自然損耗として貸主が負担する修繕費用に該当します。
具体的には、開閉による摩擦で生じる擦り傷、日光による色あせ、湿度の変化による軽微なたわみなどが自然損耗として認められるでしょう。
借主の過失による破損は借主負担
一方で、故意または重大な過失によって生じた破損については、借主が修繕費用を負担する必要があります。
例えば、物をぶつけて大きな穴を開けた場合、ペットが引っかいて破った場合、タバコの火で焼いた場合などは、明らかに借主の責任による破損として修繕費用の負担対象になります。
破損の原因が自然損耗か過失によるものかの判断は、契約書の内容とガイドラインの基準を照らし合わせて慎重に行う必要があります。
ふすま・障子の修繕費用相場
ふすまや障子の修繕費用は、破損の程度や修繕方法によって大きく変動します。
適正な費用を把握しておくことで、不当な請求を避けることができるでしょう。
ふすまの修繕費用


- ふすま紙の張り替え:1枚あたり3,000円~8,000円
- ふすま本体の交換:1枚あたり15,000円~30,000円
- 部分的な補修:1箇所あたり1,000円~3,000円
- 引手の交換:1個あたり500円~2,000円
障子の修繕費用


- 障子紙の張り替え:1枚あたり2,000円~5,000円
- 障子枠の修理:1箇所あたり2,000円~5,000円
- 障子本体の交換:1枚あたり12,000円~25,000円
- 部分的な紙の補修:1箇所あたり300円~800円
修繕費用は地域や業者によって差があるため、複数の見積もりを取得することが重要でしょう。
修繕費用の請求を受けた場合は、見積書の詳細を確認し、適正な価格かどうか慎重に判断することをお勧めします。
破損状況の判断基準を具体例
ふすまや障子の破損について、具体的な判断基準を理解することで適切な対応ができます。
原状回復ガイドラインでは、建具の消耗について詳細な基準が示されているため、判断に迷った際は参考にしましょう。
自然損耗と認められる具体例
| 破損の種類 | 判断基準 |
|---|---|
| 表面の軽微な汚れ | 日常生活による手垢や軽微な汚れは自然損耗 |
| 日焼けによる色あせ | 太陽光による自然な変色は経年劣化として扱う |
| 開閉による摩擦傷 | 通常使用による引手周辺の擦り傷は自然損耗 |
| 湿度による軽微な変形 | 季節による自然な膨張収縮は経年変化 |
借主負担となる具体例
| 破損の種類 | 判断基準 |
|---|---|
| 故意による大きな穴 | 物をぶつけるなど明らかな過失による破損 |
| ペットによる引っかき傷 | 飼育による明確な損傷は借主の責任 |
| タバコによる焦げ跡 | 喫煙による火傷は過失として扱われる |
| 落書きや意図的な汚れ | 故意による汚損は借主が修繕費用を負担 |
判断に迷う場合は、賃貸借契約書の特約条項や管理会社との協議によって決定されることもあります。
破損の状況を写真で記録し、原因を明確にしておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
修繕費用を抑える方法と注意点
借主の過失による破損の場合、修繕方法の選択によって費用を大幅に抑えることが可能です。
ただし、賃貸物件では修繕方法について事前に管理会社や大家との合意が必要でしょう。
費用を抑える選択肢


- 複数業者からの相見積もり取得による適正価格の確認
- 部分補修による最小限の修繕範囲での対応
- DIY修繕(管理会社承諾後)による材料費のみでの対応
- 修繕時期の調整による工事費用の最適化
修繕における注意事項
費用を抑えようとして不適切な修繕を行うと、退去時にかえって高額な追加修繕費用を請求される可能性があります。
また、賃貸借契約書に修繕に関する特約がある場合は、その内容に従う必要があるため事前確認が重要です。
修繕業者選定の際は、賃貸物件での実績がある業者を選ぶことで、適切な品質での修繕が期待できるでしょう。
修繕方法や業者選定に迷った場合は、管理会社に推奨業者を確認することで、適切な品質と価格での修繕が可能になります。
トラブル回避のための対処法と相談先
ふすまや障子の破損をめぐるトラブルを避けるためには、適切な手順と相談先を知っておくことが重要です。
特に高額な修繕費用を請求された場合は、冷静に対応することが求められます。
入居時と退去時の記録作成
トラブル防止の最も効果的な方法は、入居時と退去時の状況を詳細に記録することです。
ふすまや障子の状態を写真撮影し、既存の傷や汚れを管理会社と共有しておくことで、後々の責任の所在を明確にできるでしょう。
契約書と特約条項の確認
賃貸借契約書には、原状回復に関する特約条項が記載されている場合があります。
ガイドラインに反する不当な特約は無効とされる可能性が高いため、契約内容を詳しく確認することが大切です。
専門家への相談


- 消費生活センター:無料相談と適切なアドバイス
- 法テラス:法的手続きに関する情報提供
- 認定司法書士:賃貸トラブルの専門的な対応
- 弁護士:複雑な法的問題の解決
法的な手続きが必要になった場合は、認定司法書士や弁護士への相談を検討しましょう。
早期の相談により、トラブルの拡大を防ぎ、適切な解決策を見つけることができます。一人で悩まず、専門家のサポートを活用してください。
まとめ
賃貸住宅におけるふすまや障子の破損については、原状回復ガイドラインに基づいた適切な判断が重要です。
通常の使用による自然損耗は貸主負担、故意や重大な過失による破損は借主負担という基本原則を理解し、適切な対応を心がけましょう。
修繕費用の相場を把握し、必要に応じて複数の見積もりを取得することで、適正な費用での修繕が可能になります。
トラブルを避けるためには、入居時からの記録作成と契約内容の確認が不可欠でしょう。
判断に迷った場合や不当な請求を受けた場合は、消費生活センターや法律の専門家に相談することをお勧めします。
- ふすま・障子の自然損耗は貸主負担、過失による破損は借主負担
- 修繕費用の相場を把握し、複数見積もりで適正価格を確認
- 破損状況の記録と契約書の特約条項の確認が重要
- DIY修繕は事前承諾を得て品質に注意して実施
- トラブル時は専門家への早期相談で適切な解決を図る