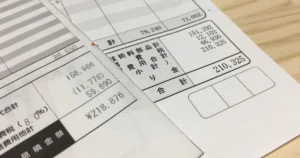「敷金が返ってこないのは普通」。貸主に敷金返還請求をするまでの流れ
賃貸住宅を退去する際に、敷金が思うように返ってこない経験をされた借主の方は多いのではないでしょうか。
実際の調査データによると、東京では敷金が「100%」返還された割合はわずか12%に過ぎず、平均返還率は42%にとどまっているのが現実です。
つまり、敷金の大部分が戻ってこないのは、残念ながら珍しいことではありません。
しかし、適切な知識と準備があれば、敷金返還のトラブルを予防したり、適正な返還を求めることは可能です。
本記事では、敷金が返ってこない理由から具体的な返還請求の方法、そして事前にできる予防策まで、行政書士の視点から詳しく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
敷金が返ってこないケースは実際に多いのでしょうか?
敷金が満額返還されないケースは、実は非常に多いのが現実です。
調査結果によると、東京における敷金の平均返還率は42%となっており、2ヶ月分の敷金を支払っても、実際に戻ってくるのは1ヶ月分に満たないというのが実態です。
さらに詳しく見てみると、敷金の返還状況は以下のような分布になっています。

- 100%返還:わずか12%
- 50%〜100%未満の返還:41.3%
- 50%未満の返還:15.5%
- 0%(全額没収):31%
この数字を見ると、約3割の借主が敷金を一円も返してもらえない状況に置かれていることがわかります。
海外の都市と比較すると、アメリカ、イギリス、フランスなどでは敷金(セキュリティ・デポジット)の返還率が平均80%前後となっており、日本の42%という数字がいかに低いかが明確になります。
敷金が戻ってこないという状況は「よくあること」として諦められがちですが、借主の権利を理解し適切に対応すれば改善できる可能性があります。
敷金が返ってこないのは「普通」ではありません。適正な根拠なく敷金を没収されている可能性も十分にあるため、まずは返還されない理由を正確に把握することが重要です。
参照元:リクルート住宅総研 NYC, London, Paris & TOKYO 賃貸住宅生活実態調査
敷金返還を拒否される理由にはどのようなものがあるのでしょうか?
敷金が返還されない理由は、大きく分けて3つのパターンに分類されます。
入居後の傷や汚れが原状回復費用として請求される場合
最も多い理由が、入居中に発生した傷や汚れの修繕費用として敷金が充当されるというものです。
ただし、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、借主が負担すべき範囲と貸主が負担すべき範囲が明確に分けられています。
| 借主負担 | 貸主負担 |
|---|---|
| 故意・過失による破損 | 通常の使用による損耗 |
| 喫煙によるヤニ汚れ | 日照による畳の変色 |
| ペットによる柱の傷 | 家具設置による床のへこみ |
| 釘穴(下地ボード交換必要) | 画鋲穴(下地ボード交換不要) |
「壁に釘の1本も打てない」という認識が一般的ですが、実際には下地ボードの張替えが必要な程度でなければ原状回復義務はないとされています。
契約書の特約事項による負担が発生する場合
賃貸借契約書に記載された特約事項により、本来は貸主負担とされる項目も借主負担となるケースがあります。
よくある特約事項としては以下のようなものが挙げられます。


- ハウスクリーニング費用は借主負担
- 畳の表替え費用は借主負担
- 壁紙の張替え費用は借主負担
- 鍵の交換費用は借主負担
ただし、特約事項であっても借主に著しく不利な内容や、消費者契約法に抵触する条項については無効となる可能性があります。
管理会社や貸主の不適切な対応による場合
残念ながら、適正な根拠なく敷金を返還しない管理会社や貸主も存在しているのが現実です。
借主の知識不足を利用して、本来は貸主負担である項目まで借主に請求したり、明細を明確にせずに「原状回復費用」として一括で請求するケースも見受けられます。
特に、退去立ち会いの際に詳細な説明がなく、後日一方的に請求書が送られてくるような場合は注意が必要でしょう。
敷金返還を拒否される理由が適正かどうかを判断するためには、まず明細書の提示を求めることが大切です。曖昧な説明しかない場合は、詳細な根拠を確認しましょう。
敷金返還請求の具体的な方法とは?
敷金が不当に返還されない場合、段階的に対応を進めていくことが効果的です。
争いごとを避け円満解決を目指すため、まずは話し合いから始めて、必要に応じて法的手段を検討しましょう。
第1段階:管理会社・貸主との話し合い
最初に行うべきは、管理会社や貸主との直接的な話し合いによる解決を試みることです。
この段階では、以下の点を明確にして交渉を進めます。


- 敷金返還の詳細な明細書の提示を求める
- 国土交通省ガイドラインに基づく負担区分の確認
- 入居時と退去時の写真による現状確認
- 特約事項の適法性についての検討
電話での交渉だけでなく、後々の証拠として残るよう、書面やメールでのやり取りを記録に残すことをお勧めします。
第2段階:内容証明郵便による請求
話し合いによる解決が困難な場合、内容証明郵便を使って正式な敷金返還請求を行う方法があります。
内容証明郵便は法的な効力はありませんが、借主の本気度を示すとともに、相手方へのプレッシャーとして機能することが期待できます。
内容証明郵便には以下の内容を記載します。
・敷金返還請求の根拠(国土交通省ガイドライン等)
・具体的な返還要求額
・回答期限(通常1〜2週間程度)
・今後の対応方針(法的措置も検討していることを示唆)
内容証明郵便の作成については、行政書士などの専門家に依頼することで、より効果的な文書を作成することができるでしょう。
第3段階:少額訴訟等の法的手続き
内容証明郵便でも解決しない場合、法的手続きによる解決を検討する必要があります。
敷金返還請求の場合、以下のような手続きが利用できます。
| 手続き名 | 対象金額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 少額訴訟 | 60万円以下 | 1回の審理で判決、弁護士不要 |
| 民事調停 | 制限なし | 話し合いによる解決、費用が安い |
| 通常訴訟 | 制限なし | 証拠調べが充実、時間がかかる |
敷金返還請求の場合、少額訴訟が最も利用しやすい手続きとなります。
ただし、法的手続きは専門的な知識が必要になるため、複雑なケースでは認定司法書士や弁護士への相談をお勧めします。
法的手続きを検討する前に、まずは話し合いと内容証明郵便による解決を試みることをお勧めします。円満解決が最も望ましい結果だからです。
敷金返還トラブルを未然に防ぐためにできることは?
敷金返還のトラブルは、事前の準備と適切な対応により大部分を予防することができます。
以下の予防策を実践することで、退去時のトラブルを大幅に減らすことができるでしょう。
入居時の記録と写真撮影
入居時に部屋の状況を詳細に記録することは、最も重要な予防策の一つです。
具体的には以下の項目を記録し、写真に残しておきましょう。


- 壁・天井・床の傷や汚れの有無
- 設備の動作状況(エアコン、給湯器等)
- 畳・壁紙・カーペットの状態
- 窓ガラスの傷やヒビ
- 水回りの水垢や汚れ
写真撮影の際は、日付が入るよう設定し、全体写真と詳細写真の両方を撮影することが大切です。
また、入居時に管理会社の担当者と一緒に確認を行い、気になる箇所があれば書面で記録を残してもらいましょう。
契約書の特約事項の事前確認
賃貸借契約を締結する前に、特約事項の内容を詳細に確認し、疑問点は契約前に質問して明確にすることが重要です。
特に以下の項目については要注意です。


- ハウスクリーニング費用の負担区分
- 畳・壁紙の交換費用負担の条件
- 通常損耗と借主負担の範囲
- 鍵交換費用の負担者
不明確な表現や過度に借主に不利な条項がある場合は、契約前に修正を求めることも検討しましょう。
退去時の立ち会いへの参加
退去時の立ち会いは、敷金返還額を決定する重要な機会です。
立ち会いの際は以下の点に注意して対応しましょう。


- 入居時の写真と現在の状況を比較しながら確認
- 指摘された箇所について理由と負担区分を確認
- 納得できない項目は具体的な根拠を求める
- 立ち会い内容を書面で記録してもらう
- 退去時の部屋の状況も写真撮影する
管理会社の担当者との意見が分かれる場合は、その場で即答せず、後日検討してから回答する旨を伝えることも一つの方法です。
日常的な部屋の管理
入居中の日常的な管理も、敷金返還に大きく影響します。
以下の点に注意して生活することで、退去時の負担を最小限に抑えることができるでしょう。


- 定期的な清掃と換気
- カビや結露の防止対策
- 設備の適切な使用方法の遵守
- 傷つきやすい箇所の保護対策
特に水回りは汚れが蓄積しやすいため、こまめな清掃を心がけることが重要です。
予防策の中でも、入居時の記録作成は特に重要です。少し手間はかかりますが、後のトラブル防止を考えると必ずやっておくべき作業と言えるでしょう。
まとめ
敷金が返ってこないという状況は、残念ながら日本の賃貸住宅市場では珍しいことではありません。
しかし、適切な知識と準備があれば、多くのトラブルは予防でき、不当な請求に対しては適正な対抗手段を講じることができます。
重要なポイントは、入居時からの準備、契約内容の正確な把握、そして問題が発生した際の段階的な対応です。
まずは話し合いによる円満解決を目指し、それが困難な場合には専門家のサポートを受けながら、内容証明郵便や法的手続きも視野に入れて対応することが大切でしょう。
敷金は借主の大切な財産です。
泣き寝入りをせず、適正な権利行使により、本来返還されるべき敷金の回収を目指しましょう。
- 敷金の平均返還率は42%と低く、全額返還は12%に過ぎない
- 国土交通省ガイドラインで借主・貸主の負担区分が定められている
- 話し合い→内容証明→法的手続きの段階的対応が効果的
- 入居時の記録作成と契約書確認でトラブルの多くは予防できる
- 複雑なケースでは専門家への相談が重要である