【保証金返還の可否に関する判例】通常使用損耗でないため保証金返還なし
公営住宅や区民住宅における原状回復義務は、一般的な賃貸住宅とは異なる法的枠組みの中で判断されることがあります。
通常、長期間の居住により生じた損耗は「通常使用による自然損耗」として扱われることが多いですが、本事例は11年間の居住期間にも関わらず、発生した損傷がすべて「通常の使用によって生じたものとは言えない」と判断された特異なケースです。
今回ご紹介する東京地方裁判所平成22年2月2日判決は、大田区民住宅における保証金返還請求事件で、賃借人の管理状況が極めて不適切であったため、長期居住にも関わらず全額の賠償責任が認められました。
この判例は、居住期間の長さだけでは「通常損耗」の判断基準とならないことを示す重要な事例として注目されています。
本記事では、この特殊な判例の詳細な分析を通じて、適切な住宅管理の重要性と、原状回復義務の判断における具体的な基準について解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
概要

- 物件
大田区民住宅(公営住宅) - 使用期間
平成10年5月〜平成21年4月(約11年間) - 月額使用料
15万7200円 - 保証金
31万4400円(全額返還されず)
本事例は、大田区民住宅条例に基づく公営住宅の使用許可契約における保証金返還を巡る争いです。
平成10年4月27日に締結された使用許可は、月額使用料15万7200円で約11年間継続し、平成21年4月26日に終了しました。
退去時、賃借人には未納の使用料及び共益費13万9500円があり、さらに大田区民住宅条例25条2項に基づく賠償金として29万5020円の支払義務が発生していました。
賃貸人(大田区)は、これらの債務と保証金31万4400円を相殺した結果、返還すべき保証金はないと主張しました。
一方、賃借人は11年という長期間の居住により生じた損耗は「社会通念上通常の使用により発生した相応の損耗」であるとして、保証金全額の返還を求めて提訴しました。
契約内容と特約の詳細
本件は大田区民住宅条例に基づく使用許可契約であり、一般的な賃貸借契約とは法的性格が異なります。

- 契約の基本条件
- 大田区民住宅条例に基づく使用許可
- 使用期限の定めなし
- 月額使用料:15万7200円
- 保証金:31万4400円(使用料の2ヶ月分)
- 適用法令
- 大田区民住宅条例25条2項(賠償責任規定)
- 公営住宅法の関連規定
- 一般法としての民法の適用
大田区民住宅条例25条2項は、使用者の責めに帰すべき事由による損傷について賠償責任を定めており、この規定により29万5020円の損害賠償が請求されました。
公営住宅の使用許可契約は、住宅確保要配慮者への住宅供給を目的とした公的制度であり、一般的な賃貸借契約よりも使用者の適切な管理責任が重視される傾向があります。
また、月額使用料15万7200円に対して保証金が31万4400円(約2ヶ月分)と比較的少額に設定されているのも、公営住宅の特徴といえます。
本件では、11年間という長期使用にも関わらず、使用者の管理状況が極めて不適切であったことが、後の判決で詳細に認定されています。
賃貸人・賃借人の主張のポイント
本件では、11年間という長期使用期間における損耗の性質が主要な争点となりました。
| 争点 | 賃貸人(大田区)側の主張 | 賃借人側の主張 |
|---|---|---|
| 損耗の性質 | 使用者の不適切な管理による特別損耗 | 11年間の長期使用による通常損耗 |
| 賠償責任の根拠 | 大田区民住宅条例25条2項に基づく賠償義務 | 社会通念上の通常使用範囲内 |
| 保証金の取扱い | 未納使用料・賠償金との相殺により返還額なし | 通常損耗のため保証金全額返還 |
| 管理責任 | 使用者の善管注意義務違反 | 通常の居住使用による相応の損耗 |
賃貸人である大田区は、発生した損傷が使用者の不適切な管理に起因する特別損耗であり、大田区民住宅条例に基づく賠償責任の対象になると主張しました。
具体的には、フローリング材の剥がれ、襖の破損、設備の紛失、無断での器具取付けなど、通常使用の範囲を超える損傷が多数発生していると指摘しました。
一方、賃借人側は11年間という長期居住期間を重視し、この間に生じた損耗は「社会通念上通常の使用により発生した相応の損耗」であると主張しました。
賃借人は、経年変化による自然な劣化の範囲内であり、特別な賠償責任は発生しないとして、保証金全額の返還を求めていました。
裁判所の判断と法的根拠
裁判所は、各損傷項目を個別に検証し、すべてが通常使用の範囲を超えると判断しました。
| 損傷項目 | 損害額 | 裁判所の判断 |
|---|---|---|
| バルコニー出入口フローリング材剥がれ | 18万4000円 | 通常使用によるものではない |
| 襖の破損・穴・しみ | 1万3800円 | 管理不良による損傷 |
| 台所洗面金具(浄水器付き) | 3万5200円 | 無断設置による設備変更 |
| 各種フック取付け跡 | 1万9800円 | 原状変更による損傷 |
| 鍵の紛失 | 7020円 | 管理義務違反 |
最も重要な判断は、11年間という長期使用期間にも関わらず、「証拠に照らせばいずれも通常の使用によって生じたものとは言えない」との認定でした。
裁判所は、単に居住期間が長いことだけでは「通常損耗」の根拠とならず、実際の損傷の性質と原因を個別に判断すべきとの法理を示しました。
特に、フローリング材の剥がれ、襖への穴、無断での器具取付け、設備の紛失などは、使用者の善管注意義務違反による特別損耗であると判定されました。
最終的に、未納使用料・共益費13万9500円と賠償金29万5020円の合計43万4520円が賃借人の負担となり、保証金31万4400円を超過するため、返還すべき保証金はないとの判決に至りました。
判例から学ぶポイント
この判例は、居住期間の長さと通常損耗の関係について重要な教訓を提供します。
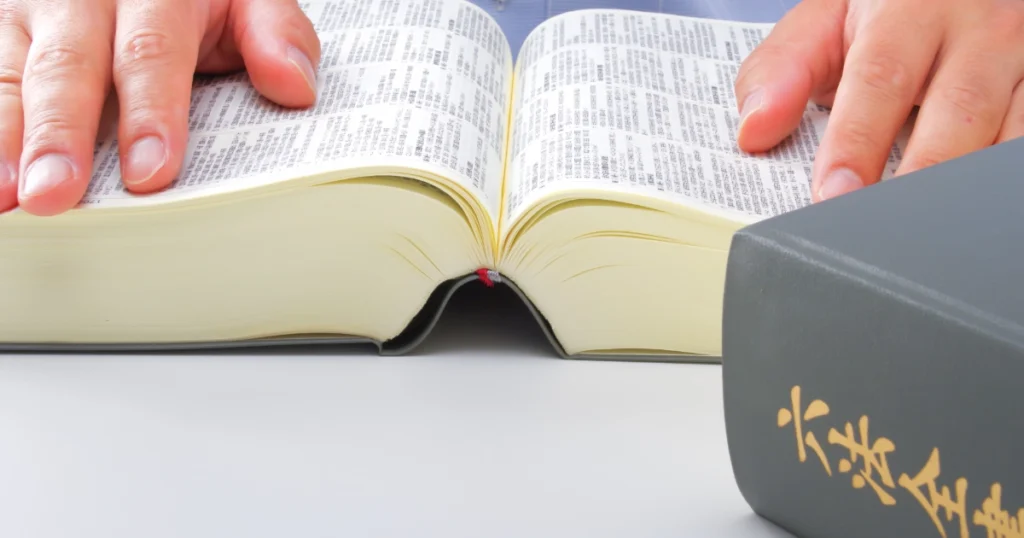
通常損耗判断の重要な原則
- 期間だけでは判断されない
長期居住でも損傷の性質により特別損耗と認定される - 個別具体的な検証
各損傷項目について原因と性質を詳細に判断 - 管理責任の重視
適切な管理義務の履行が重要な判断要素
最も重要な教訓は、「居住期間の長さ」だけでは通常損耗の判断基準とならないという点です。
11年間という長期間であっても、使用者の管理が不適切であれば、発生した損傷は特別損耗として扱われることが明確になりました。
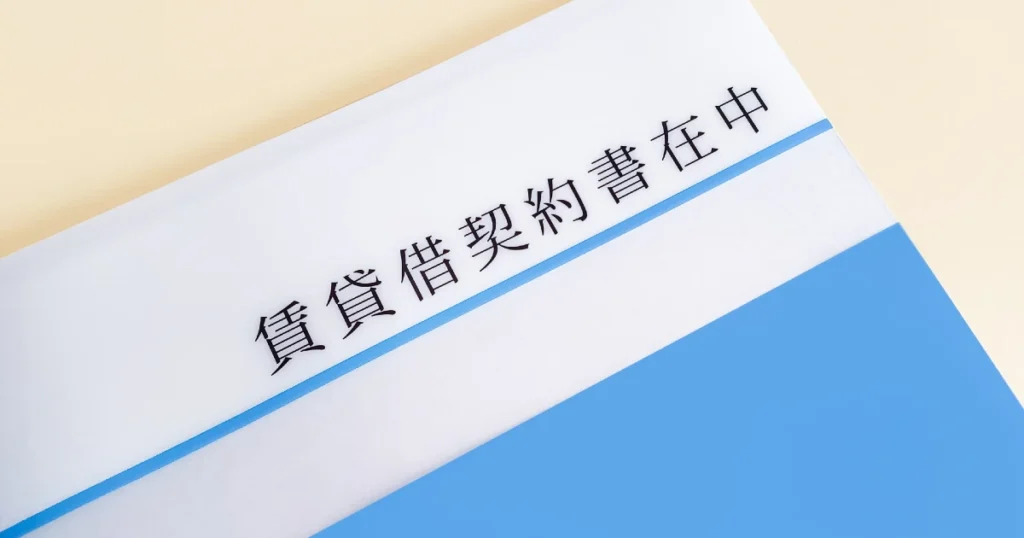
実務への重要な影響
- 公営住宅でも一般賃貸住宅と同様の善管注意義務が適用
- 設備の無断変更や器具の取付けは原状回復義務の対象
- 鍵の紛失等の管理ミスも賠償責任を伴う
また、公営住宅においても民間賃貸住宅と同等の管理責任が求められることも重要なポイントです。
この判例により、適切な住宅管理の重要性と、長期居住における継続的な注意義務の必要性が確認されました。
賃貸借契約における実践的対策
この事例を踏まえ、適切な住宅管理と退去時のトラブル防止のための対策をお伝えします。

契約期間中の注意点
- 設備の無断変更や器具の取付けは事前相談
- 鍵の管理は厳重に行い、紛失時は速やかに報告
- 定期的な清掃と適切なメンテナンスの実施
借主の皆様にとって最も重要なのは、日常的な適切な管理と使用です。
特に、浄水器の取付けやフックの設置など、「ちょっとした便利のため」の変更でも、無断で行えば原状回復義務の対象となることを理解しておく必要があります。
また、襖に穴を開ける、フローリングを傷つけるなどの行為は、たとえ長期居住であっても「通常使用」の範囲を超えると判断される可能性が高いです。
契約書には「善良な管理者の注意をもって使用する」旨の条項が記載されており、この義務を怠ると事例39のような結果となりかねません。
日頃から丁寧な住まい方を心がけ、設備に関する変更は必ず事前に相談することで、退去時のトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ

東京地方裁判所の本判決は、長期居住における適切な管理責任の重要性を明確に示した重要な判例です。
11年間という長期使用期間にも関わらず、発生した損傷がすべて「通常の使用によって生じたものとは言えない」と判断されたことは、居住期間の長さだけでは通常損耗の根拠とならないことを示しています。
この判例により、適切な住宅管理と善管注意義務の履行が、公営住宅・民間住宅を問わず重要であることが確認されました。
実務においては、日常的な丁寧な使用と、設備変更時の事前相談により、退去時のトラブルを予防することが可能です。
賃貸住宅の適正な利用と管理は、借主と貸主双方の利益につながる重要な要素であり、この判例はその指針を明確に示しています。
- 長期居住期間であっても、損傷の性質により特別損耗と判断される場合がある
- 善管注意義務の履行は公営住宅・民間住宅を問わず重要な責任である
- 設備の無断変更や器具の取付けは原状回復義務の対象となる
- 鍵の紛失や設備の破損等の管理ミスも賠償責任を伴う
- 日常的な丁寧な使用と事前相談により、退去時トラブルの予防が可能である
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) – [事例 39]通常の使用によって生じた損耗とは言えないとして未払使用料等含めて保証金の返還金額はないとされた事例






