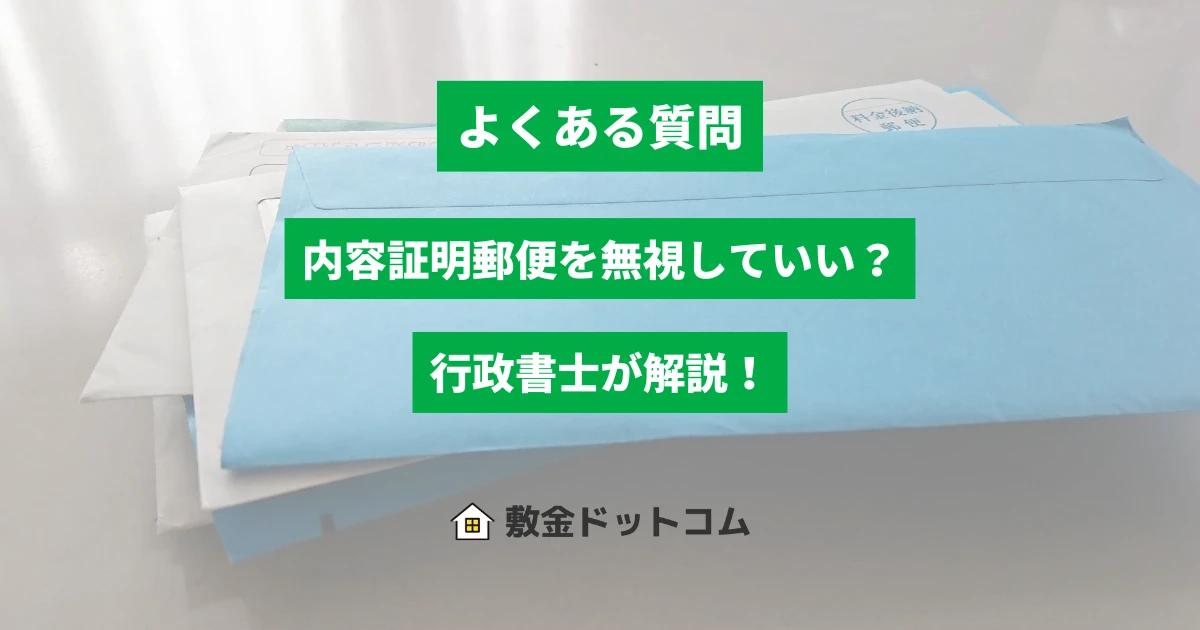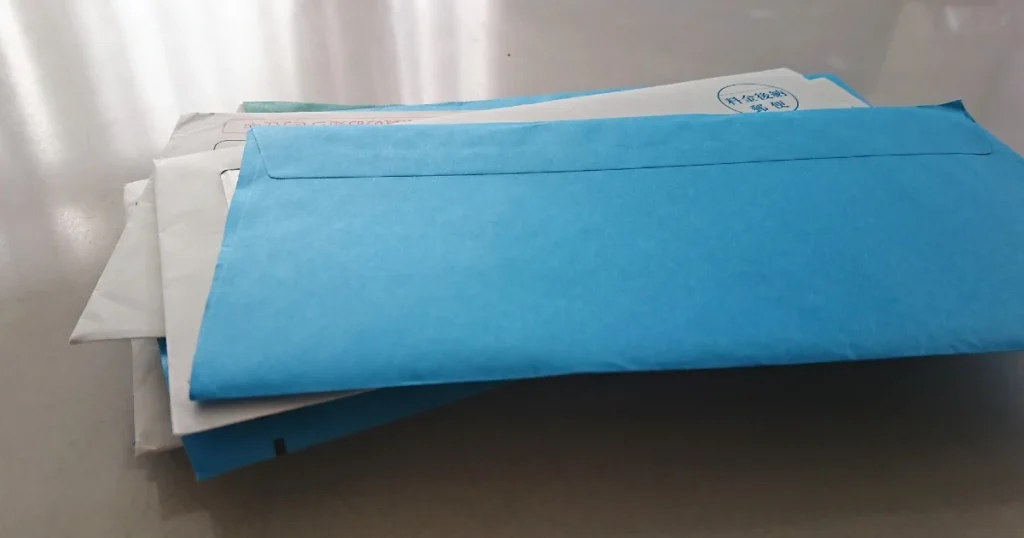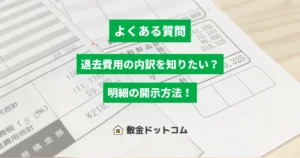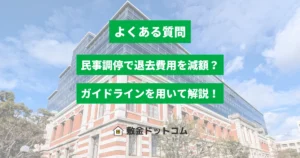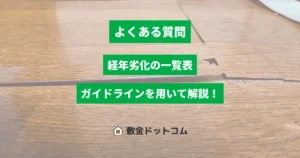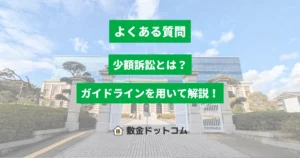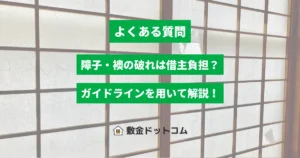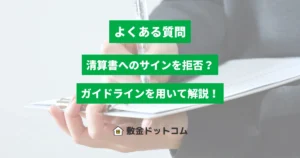賃貸物件を退去した後、「想定外の高額な請求」や「内容証明郵便」が届いて困惑している方は少なくありません。
「支払いたくない」「無視してもいいのでは?」と考える気持ちは理解できます。
しかし、内容証明郵便を単に無視することはリスクを伴います。
本記事では、賃貸退去時の費用トラブルについて、特に内容証明郵便が届いた場合の適切な対応方法を行政書士の視点から解説します。
法的知識と実践的なアドバイスで、あなたの不安を解消し、適切な対応ができるようサポートします。
内容証明郵便を無視してもいいのか、それともどう対応すべきなのか、明確な道筋を示します。
 行政書士 松村 元
行政書士 松村 元
監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
目次
内容証明郵便とは何か
 内容証明郵便は裁判などでの証拠能力を高める効果がある
内容証明郵便は裁判などでの証拠能力を高める効果がある
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったかを日本郵便が証明する特殊な郵便サービスです。
法的な通知や請求においてよく利用され、後の裁判などでの証拠能力を高める効果があります。
賃貸退去費用の請求では、貸主(大家さんや不動産会社)が借主に対して支払いを求める正式な手段として送付されることが多いです。
民法の原状回復義務の範囲をめぐる争いが背景にあり、「通常の使用による劣化・経年変化」は貸主負担、「故意・過失による損傷」は借主負担という原則に基づいています。
内容証明は法的手続きの前段階として送られることが多く、これを無視すると訴訟に発展するリスクが高まります。
内容証明が届いたときの対応法
内容証明郵便を受け取った場合、絶対に「無視」してはいけません。
適切な対応方法は以下のとおりです。
- 請求内容、金額、支払期限などをメモしておく
- 入居時・退去時の写真や契約書、重要事項説明書など関連書類を集める
- 不当な請求と思われる場合は、消費生活センターや弁護士、行政書士などに相談する
- 請求に対する自分の立場(全額支払う、一部支払う、支払わない)を明確にし、できれば内容証明で返信することが望ましい
特に注意すべきは、放置すると督促状の送付、少額訴訟、裁判所からの呼び出しへと事態がエスカレートする可能性が高いことです。
コミュニケーションを途絶えさせず、誠実に対応することが問題解決の鍵となります。
まとめ
賃貸退去時の費用トラブルと内容証明郵便への対応についてまとめました。
最も重要なのは、内容証明郵便を「無視しない」ということです。
無視は問題解決につながらず、むしろ事態を悪化させるリスクがあります。
請求内容に納得できない場合でも、まずは書面で自分の立場を明確にし、必要に応じて専門家のアドバイスを求めましょう。
「国土交通省のガイドライン」や「消費者契約法」などを参考に、不当な請求に対しては毅然とした態度で交渉することも大切です。
最終的には、双方が納得できる解決策を見つけることが理想です。
適切な知識と冷静な対応で、退去費用のトラブルを上手に乗り越えましょう。
参照元:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
あわせて読みたい
賃貸の退去費用に対するガイドライン【原状回復ガイドラインのまとめ】
賃貸物件を退去する際、退去費用の相場はどの程度か気になる方も多いでしょう。退去費用は、賃貸契約書に記載された原状回復の規定や、物件の経年劣化、損耗の程度によって大きく変わります。一般的には、敷金から原状回復費用や清掃費用が差し引かれて返還されますが、修繕が必要な場合は追加で費用が請求されることもあります。国土交通省のガイドラインによると、通常の使用による損耗は賃貸人が負担し、故意・過失や通常の使用を超える損耗は賃借人が負担するのが原則です。例えば、壁紙の一部が傷んだ場合、その部分だけを修復する費用は賃借人の負担となりますが、部屋全体の壁紙を張り替える必要がある場合は賃貸人が負担すべきとされています。また、経過年数や入居年数を考慮して負担割合が調整されるため、長期間住んでいた場合の負担は軽減される傾向にあります。退去費用の相場を把握するためには、契約内容や物件の状態をしっかり確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。