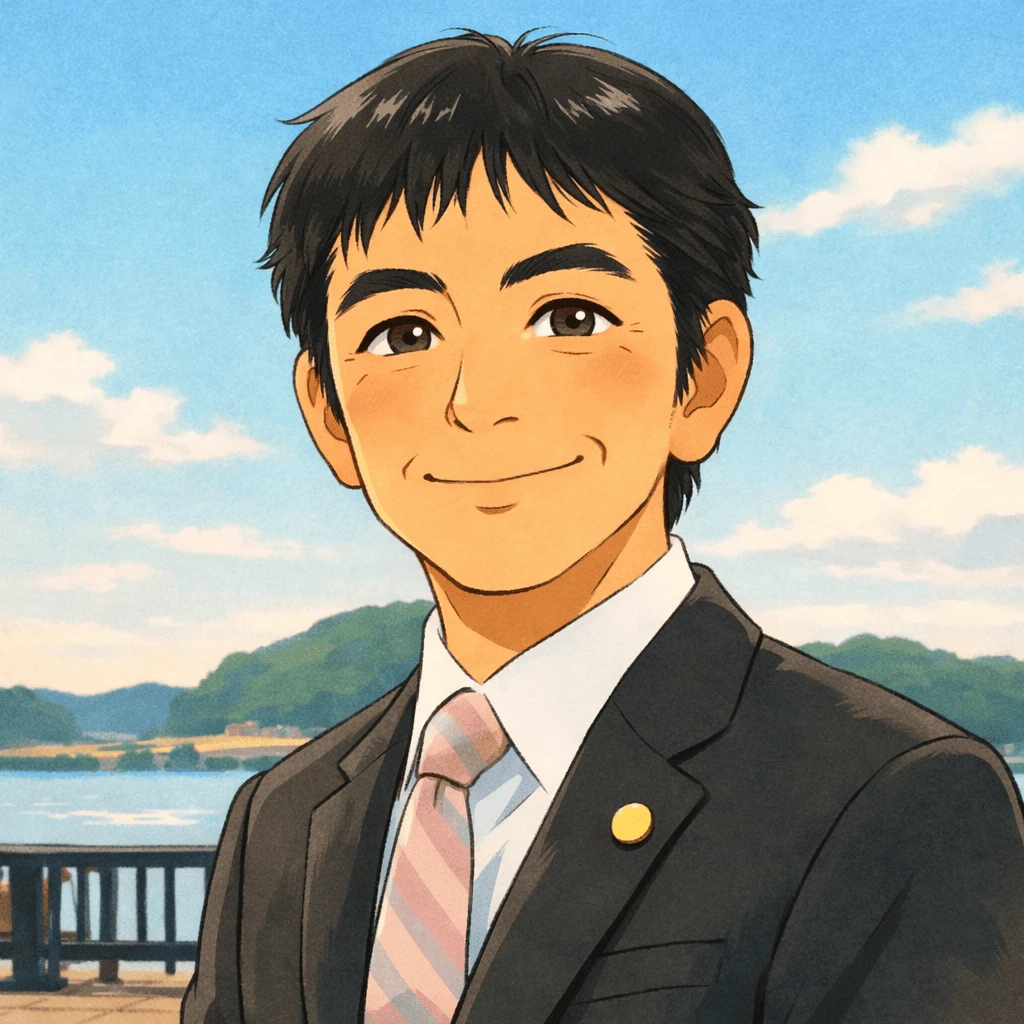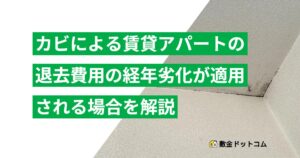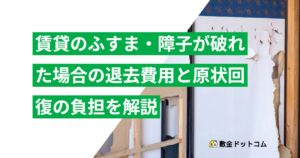【消費者契約法9条とは】中途解約に伴う違約金が無効になる可能性
「契約期間の途中で退去したら違約金を請求された」「違約金として家賃2ヶ月分は妥当なの?」——賃貸物件の中途解約に伴う違約金と、原状回復費用の不当条項。この2つの問題に対応する法律として、消費者契約法の9条と10条をご存知でしょうか?
結論から言えば、消費者契約法9条は「平均的な損害」を超える違約金を無効に、10条は借主に一方的に不利な契約条項を無効にする規定です。どちらも賃貸トラブルで借主を守る重要な武器ですが、対象や効果が異なるため正しく使い分ける必要があります。
この記事では、消費者契約法9条と10条の違いを軸に、中途解約の違約金が無効になる条件、「平均的な損害」の判断基準、退去時に違約金を請求されたときの対処法までを比較しながら解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
消費者契約法9条と10条の基本的な違い
消費者契約法9条と10条はどちらも消費者を保護する規定ですが、規制の対象・効果・適用場面が明確に異なります。まずは両者の違いを正確に理解しましょう。
1-1. 消費者契約法9条の内容と対象
消費者契約法9条1項1号は、消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金の定めについて、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分を無効とする規定です。
- 対象:契約の解除に伴う違約金・損害賠償額の予定
- 効果:「平均的な損害」を超える部分のみ無効
- 賃貸での適用:中途解約時の違約金が主な対象
- 立証責任:2023年改正により事業者側に転換
1-2. 9条と10条の比較一覧
賃貸借契約のトラブルでは9条と10条が混同されがちです。以下の表で両者の違いを明確に比較します。
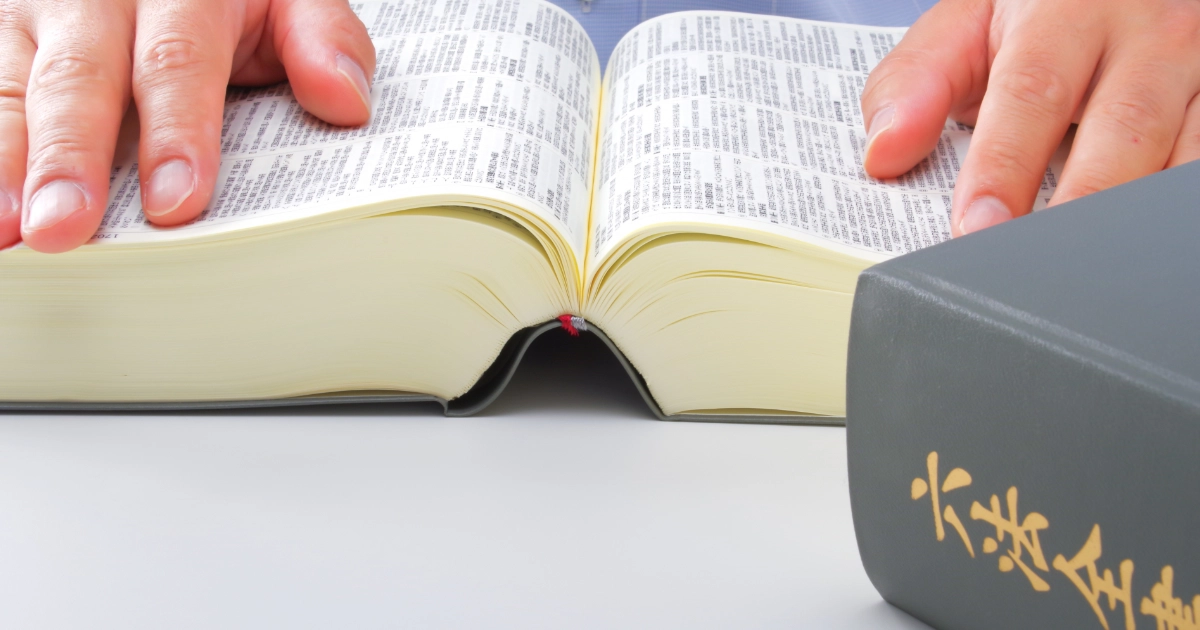
| 比較項目 | 消費者契約法9条 | 消費者契約法10条 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 違約金・損害賠償額の予定 | 消費者の権利制限・義務加重条項全般 |
| 無効の範囲 | 「平均的な損害」を超える部分のみ | 条項全体が無効 |
| 賃貸での主な適用 | 中途解約の違約金 | 原状回復特約 |
| 判断基準 | 「平均的な損害」との比較 | 信義則に反して消費者の利益を一方的に害するか |
| 立証責任 | 事業者側(2023年改正後) | 消費者側 |
賃貸物件を契約期間の途中で解約する場合、契約書に定められた違約金を請求されるケースがあります。ここでは、消費者契約法9条における「平均的な損害」の考え方と、賃貸借契約での具体的な判断基準を解説します。
2-1. 賃貸における「平均的な損害」の判断基準
「平均的な損害」とは、同種の契約が解除された場合に事業者に通常生じる損害の平均額を意味します。賃貸借契約の場合、以下の要素が考慮されます。
- 次の入居者が決まるまでの期間:地域の空室率や物件の人気度による再募集期間
- 再募集にかかる費用:広告費や仲介手数料などの実費
- 解約予告期間:契約書に定められた予告期間(通常1ヶ月前)の有無
- 物件の所在地・条件:都市部か地方か、築年数、間取りなど
2-2. 違約金が無効になるケース・有効なケース
具体的にどのような違約金が有効または無効と判断されるのか、典型的なケースを比較します。

| ケース | 違約金の内容 | 判断 |
|---|---|---|
| 1年未満の短期解約 | 家賃1ヶ月分の違約金 | 有効とされやすい(再募集費用として妥当) |
| 1年未満の短期解約 | 家賃3ヶ月分以上の違約金 | 無効の可能性(平均的な損害を超過) |
| 予告期間を守った解約 | 違約金の請求 | 無効の可能性(損害が発生していない) |
| 定期借家の途中解約 | 残存期間の賃料相当額 | 一部無効の可能性(全額は過大) |
| フリーレント期間後の解約 | フリーレント分の返還 | 有効とされやすい(実質的な割引の返還) |
 ゲン
ゲン2023年の消費者契約法改正で、9条の「平均的な損害」の立証責任が事業者側に転換されました。これにより、違約金の妥当性を事業者が証明できなければ、その部分は無効になりやすくなっています。
各設備の耐用年数と負担割合の詳細は、以下の記事で確認できます。
原状回復特約と消費者契約法10条の適用
中途解約の違約金は9条の問題ですが、退去時の原状回復費用に関する不当条項は10条の問題です。ここでは、10条が原状回復特約にどのように適用されるかを解説します。
3-1. 消費者契約法10条で無効になる原状回復特約
消費者契約法10条は、民法の原則と比べて消費者の権利を制限・義務を加重する条項で、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものを無効とします。原状回復の場面では、以下のような特約が無効と判断される可能性があります。
- 通常損耗を借主負担とする特約:負担範囲が包括的で、個別の説明・合意がないもの
- 減価償却を無視した特約:経過年数に関係なく新品交換費用を全額請求するもの
- 相場を超える定額特約:ハウスクリーニング等の金額が相場を大幅に上回るもの
3-2. 9条と10条の使い分け方
退去時のトラブルでは、問題の内容によって9条と10条を使い分けることが重要です。場合によっては両方を同時に主張することもできます。


| トラブルの内容 | 適用条文 | 主張のポイント |
|---|---|---|
| 中途解約の違約金が高額 | 9条 | 「平均的な損害」を超える部分は無効 |
| 通常損耗を借主負担とする特約 | 10条 | 信義則に反し消費者の利益を一方的に害する |
| 高額な敷引特約 | 9条または10条 | 金額が過大であれば9条、条項自体が不当なら10条 |
| 短期解約の違約金+原状回復費用の二重請求 | 9条+10条 | 違約金は9条、原状回復は10条で併用主張 |
違約金を請求されたときの対処法
実際に中途解約の違約金や不当な退去費用を請求された場合、どのように対処すればよいのでしょうか。ここでは段階的な対応手順を解説します。
4-1. 請求内容を確認するチェックポイント
まずは請求内容の妥当性を冷静に確認しましょう。以下のチェックポイントに照らして、不当な請求がないかを検証します。
- 違約金の根拠:契約書に違約金条項が明記されているか確認
- 金額の妥当性:家賃1ヶ月分を超える違約金は「平均的な損害」を超過する可能性
- 予告期間の遵守:契約書の予告期間を守って解約したかどうか
- 二重請求の有無:違約金と原状回復費用が重複して請求されていないか
- 原状回復費用の内訳:通常損耗まで借主負担とされていないか
4-2. 交渉から法的手続きまでの流れ
不当な請求と判断した場合は、段階的に対応を進めましょう。多くのケースでは書面での交渉段階で解決します。



違約金と原状回復費用を同時に請求された場合は、それぞれ別の法的根拠で対抗できます。違約金は9条で「平均的な損害」を超える部分の無効を、原状回復費用は10条で不当な特約の無効を主張しましょう。
退去時のトラブルは契約時の確認で大幅に防げます。消費者契約法の知識を活かして、入居前に確認すべきポイントを押さえましょう。
5-1. 契約書で確認すべき条項
賃貸借契約を結ぶ前に、以下の条項を必ず確認してください。不明点があれば契約前に質問し、納得できない特約は修正を求めることも可能です。
- 中途解約条項:違約金の有無、金額、適用期間を確認
- 解約予告期間:何ヶ月前に通知が必要か(通常1ヶ月前)
- 原状回復特約:借主の負担範囲が具体的に明示されているか
- 敷金返還条件:敷引の有無と金額、返還までの期間
- ハウスクリーニング特約:金額と負担者が明記されているか
5-2. 証拠保全と記録の重要性
万が一のトラブルに備え、契約から退去まで一貫して記録を残すことが最大の予防策です。
- 契約書・重要事項説明書のコピーを保管し、特約部分に目印をつけておく
- 入居時に部屋の状態を日付入りの写真・動画で記録する
- 管理会社とのやり取りは、メール・書面など記録が残る方法で行う
- 退去立会い時の指摘内容はその場でメモを取り、即署名しない
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
まとめ:9条と10条を正しく使い分けて退去費用トラブルに備えよう
消費者契約法9条と10条は、賃貸退去時の不当な請求に対抗する借主の重要な法的武器です。違約金の問題には9条を、原状回復特約の問題には10条を、状況に応じて使い分けましょう。
この記事のポイント
- 消費者契約法9条と10条の違い
- 9条は違約金の「平均的な損害」超過部分を無効にする
- 10条は不当な契約条項全体を無効にする
- 違約金は9条、原状回復特約は10条で対抗
- 2023年改正で立証責任が事業者側に転換
- トラブル予防と対処のポイント
- 契約前に違約金条項と原状回復特約を確認する
- 契約書・やり取りの記録を保管しておく
- 不当な請求には書面で法的根拠を示して交渉
- 解決しない場合は消費生活センターや法テラスに相談



消費者契約法は借主を守るための法律です。退去時に想定外の請求を受けた場合は、まず契約書を確認し、9条と10条のどちらが使えるかを冷静に判断してください。一人で悩まず、専門家への相談も積極的に活用しましょう。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 消費者契約法の適用判断は個別の事情により異なります。具体的な案件については弁護士や行政書士など専門家にご相談ください。