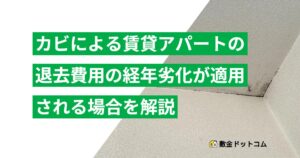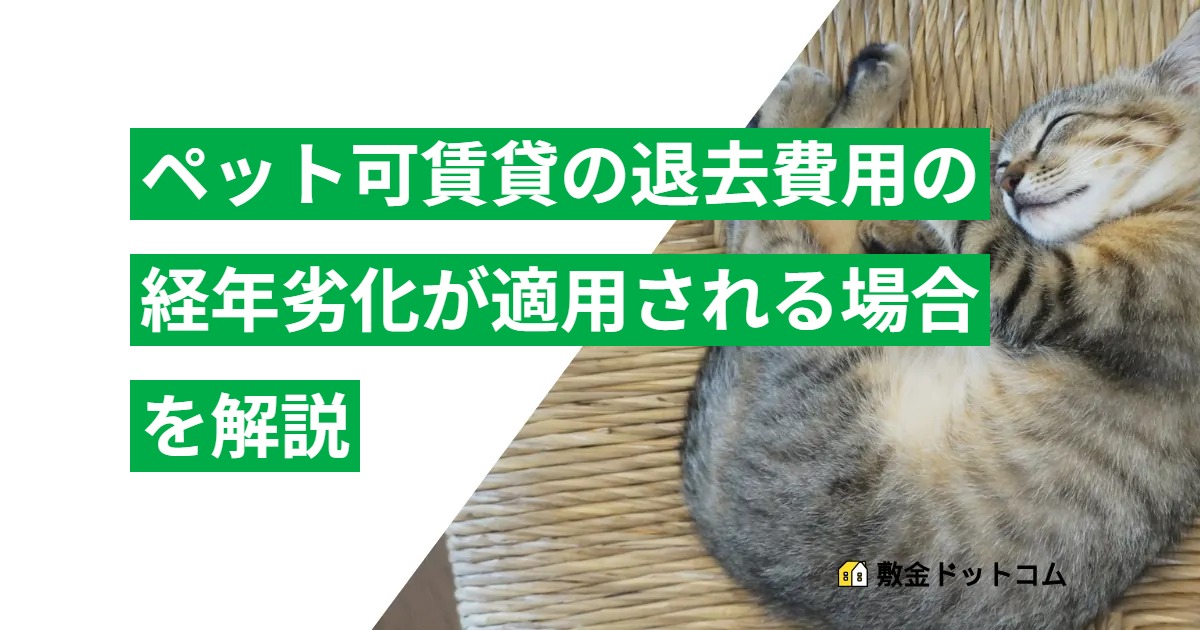
【ペット可賃貸の退去費用】経年劣化が適用される場合と注意点
ペット可賃貸物件を退去する際、「ペットがいたから」という理由で高額な原状回復費用を請求されるケースが増えています。しかし、ペット可物件であっても、すべての損耗が借主負担になるわけではありません。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、ペット可物件として貸し出している以上、通常想定される範囲のペット損耗には経年劣化の考え方が適用されるとされています。経年劣化とペット特有の損耗を正しく区別することが、適正な費用負担の第一歩です。
この記事では、ペット可賃貸の退去費用における経年劣化の適用範囲、借主負担の判断基準、契約時の確認事項、トラブル時の対処法、さらにペット不可物件での無断飼育リスクまでを体系的に解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
ペット可賃貸の退去費用とは?基本的な費用の仕組みを知ろう
ペット可賃貸物件の退去費用は、通常の賃貸物件と比べて複雑になりがちです。まずは、原状回復ガイドラインに基づく費用負担の基本原則と、ペット可物件ならではの考え方を確認しましょう。
1-1. 原状回復費用の基本原則
原状回復ガイドラインでは、借主は故意・過失による損耗のみを負担し、通常の使用による損耗(経年劣化)は貸主負担が原則です。ペット可物件でもこの原則は変わりません。
- 壁紙・床材の傷:ひっかき傷や噛み跡による建材の損傷
- 臭いの付着:ペットの体臭や排泄物による室内の臭い
- 毛・汚れ:抜け毛の付着やペットの汚れによる清掃費用
- フローリングの変色:排泄物や水分による床材の変色・腐食
1-2. ペット可物件における「通常の使用」の範囲
ペット可物件として賃貸に出している以上、貸主はペット飼育による一定の損耗を想定しているはずです。原状回復ガイドラインの考え方に基づけば、通常想定される範囲内のペット損耗は「通常の使用」に含まれると解釈できます。
ただし、「通常の使用」の範囲は物件や契約内容によって異なるため、契約時の特約内容を確認することが重要です。
退去時に最も問題となるのが、「この損耗は経年劣化か、ペットの行動による特別損耗か」という区別です。ガイドラインに基づく判断基準を正しく理解しておきましょう。
2-1. 経年劣化として認められる範囲
ペット可物件であっても、以下の損耗は原則として経年劣化(貸主負担)として扱われます。
- 壁紙の自然な変色:日焼けや湿気による黄ばみ・色褪せ
- フローリングの摩耗:日常的な歩行による自然な擦り減り
- 畳の日焼け:日光による変色やい草の自然な劣化
- 設備の経年故障:給湯器やエアコンの自然な劣化・故障
2-2. 借主負担となるペット損耗の判断基準
一方で、明らかにペットの行動によって生じた特殊な損耗は、借主負担となる場合があります。ただし、借主負担が発生する場合でも減価償却の考え方が適用されます。

| 損耗の種類 | 具体例 | 負担者 |
|---|---|---|
| 深い爪とぎ跡・噛み跡 | 柱や壁の下地ボードまで達するひっかき傷 | 借主 |
| 排泄物による腐食 | 床材の変色・膨らみ、畳の腐食 | 借主 |
| 強い臭いの付着 | 消臭では除去できないペット臭の染み込み | 借主 |
| 通常使用の軽微な汚れ | 抜け毛の付着、軽い足跡汚れ | 貸主 |
| 壁紙の自然な摩耗 | ペットが触れる高さの軽微な汚れ | 貸主 |
ペット損耗で借主負担が発生する場合でも、壁紙の耐用年数は6年です。3年間住んでいれば借主負担は残存価値の約50%のみとなりますので、減価償却の計算根拠を必ず確認しましょう。
退去費用の交渉を専門家に依頼する方法は、以下の記事で解説しています。
退去費用を抑えるための注意点は?
ペット可賃貸の退去費用は、契約時の確認と居住中の対策によって大きく抑えることができます。ここでは、契約時と居住中の2つの段階で押さえるべきポイントを解説します。
3-1. 契約時の確認事項
ペット可物件の契約時には、原状回復に関する特約条項を必ず確認しましょう。特約の内容次第で退去時の費用負担が大きく変わるため、契約前の段階で疑問点を解消しておくことが重要です。
- ペット飼育に関する特約の内容:原状回復の範囲と費用負担の具体的な取り決め
- 敷金の返還条件:ペット飼育を理由とした敷金追加や返還制限の有無
- 退去時の清掃義務:ハウスクリーニング費用の負担範囲
- 飼育頭数・種類の制限:契約で許可されたペットの条件
- 損害保険の加入義務:ペット損害に備えた保険加入の要否
3-2. 居住中の予防対策
居住中の適切な管理は、退去費用を大幅に抑える効果があります。以下の対策を日常的に実践しましょう。
- 爪とぎ対策:壁や柱に保護シートを貼り、爪とぎ用品を設置する
- 床の保護:フローリングにマットやカーペットを敷き、傷・汚れを防止
- 排泄物の即時処理:粗相があった場合はすぐに清掃し、染み込みを防ぐ
- 定期的な換気・消臭:ペット臭が染み付く前にこまめな換気と消臭を行う
- 入居時の写真撮影:既存の傷や汚れを記録し、退去時の証拠とする
トラブル発生時の対処法はどうすればよい?
退去時にペットの損耗を理由とした高額な請求を受けた場合、冷静に対処することが重要です。明細書の確認方法と、相談窓口の活用方法を解説します。
4-1. 退去費用の明細書確認方法
退去費用の請求を受けたら、まず明細書の開示を書面で求め、各項目の内訳を一つずつ確認しましょう。
- 損傷箇所の特定:ペットによる損耗と経年劣化が区別されているか
- 減価償却の適用:居住年数に応じた経過年数計算がされているか
- 修繕範囲の妥当性:損傷箇所のみの修繕か、不必要な範囲まで含まれていないか
- 単価の相場確認:クロス張替えやクリーニング費用が相場と乖離していないか
4-2. 相談窓口と解決手続き
管理会社との交渉が難航する場合は、以下の手順で段階的に対処しましょう。
ペットの損耗を理由に高額な請求を受けた場合、まずは「その損耗は本当にペットが原因か」「経年劣化は考慮されているか」を確認してください。感情的にならず、ガイドラインと契約書を根拠に冷静に交渉することが大切です。
ペット不可物件で無断でペットを飼育していた場合、退去時のリスクは非常に大きくなります。ここでは、無断飼育が発覚した際に想定される影響を確認しておきましょう。
5-1. 無断飼育で発生するリスク
ペット不可物件での無断飼育は契約違反に該当し、通常よりも厳しいペナルティが課される可能性があります。
- 契約解除(強制退去):重大な契約違反として賃貸借契約を解除される可能性
- 原状回復費用の全額請求:経年劣化の主張が認められにくくなる
- 違約金の請求:契約書に無断飼育の違約条項がある場合
- 損害賠償請求:近隣住民への被害が生じた場合の賠償責任
ペット不可物件での無断飼育は、退去費用が高額になるだけでなく、経年劣化の主張が通りにくくなるという重大なデメリットがあります。ペットを飼いたい場合は、必ずペット可物件を選びましょう。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
まとめ:ペット可賃貸の退去費用は経年劣化と損耗の区別が鍵
ペット可賃貸の退去費用は、経年劣化とペット特有の損耗を正しく区別することが適正な費用負担の第一歩です。通常想定される範囲のペット損耗は貸主負担、明らかなペットの行動による特別損耗は借主負担がガイドラインの基本的な考え方です。
この記事のポイント
- 経年劣化とペット損耗の基本ルール
- 通常想定される範囲のペット損耗は貸主負担
- 深い爪とぎ跡や臭いの染み込みは借主負担
- 借主負担でも減価償却で負担額は軽減される
- ペット不可物件の無断飼育は重大リスク
- 費用を抑える実践ポイント
- 契約時にペット関連の特約を必ず確認する
- 入居時に写真・動画で部屋の状態を記録する
- 爪とぎ対策・床の保護など日常的な予防が有効
- 高額請求は消費生活センターに相談する
ペット可賃貸の退去費用トラブルを防ぐには、契約時の特約確認と入居時の写真記録が最も効果的です。退去時に請求を受けた場合は、ガイドラインと契約書を照合し、経年劣化が正しく考慮されているかを冷静に確認してください。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は法的拘束力を持つものではありませんが、裁判や調停では重要な判断基準として参照されています。