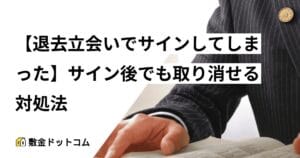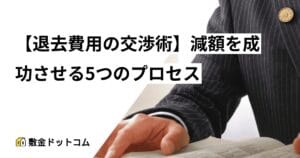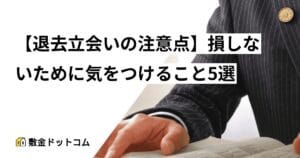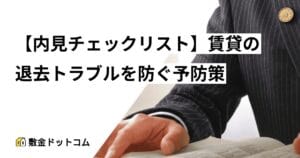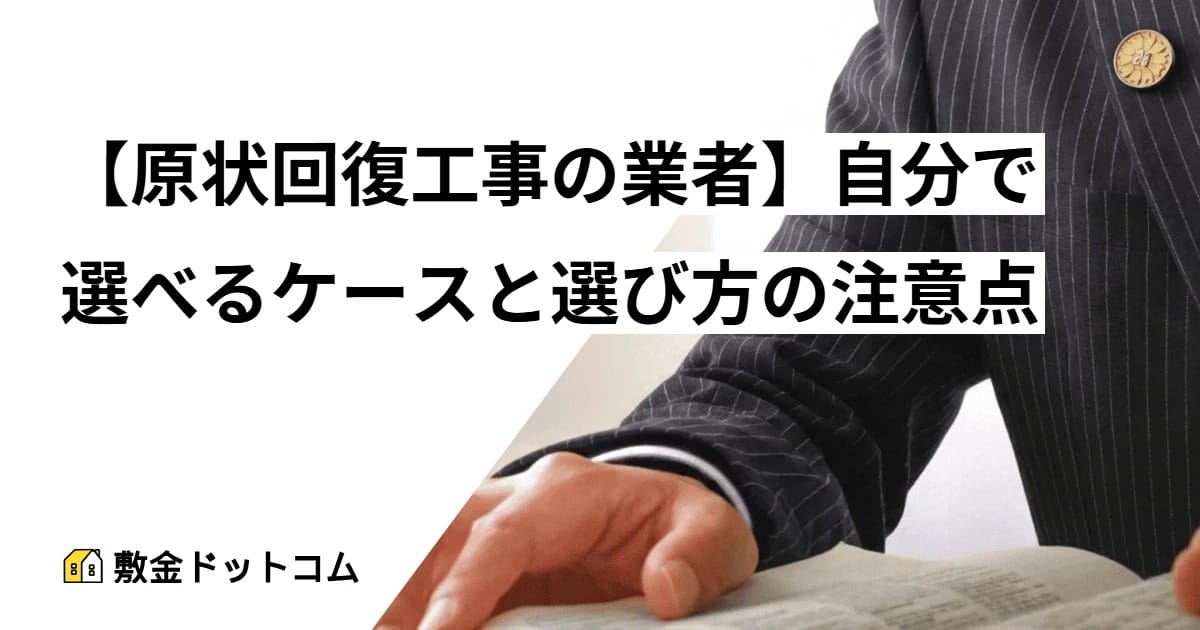
【原状回復工事の業者】自分で選べるケースと選び方の注意点
「原状回復工事の業者は管理会社が指定するもの」——このように思い込んでいませんか?実は、管理会社指定の業者と自分で選んだ業者では、工事費用に数万円以上の差が出ることがあります。
賃貸物件の原状回復工事において、業者を自分で選べるかどうかは契約内容によって異なります。この記事では、指定業者と自己選定業者の違いを明確にし、自分で業者を選べるケース・選べないケース、業者選びの注意点までを比較しながら解説します。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
第1章:管理会社指定業者と自己選定業者の違い
1-1. それぞれの特徴を比較する
原状回復工事の業者選定には、大きく分けて「管理会社指定業者」と「借主が自分で選ぶ業者」の2つのパターンがあります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、違いを理解したうえで判断することが重要です。

| 比較項目 | 管理会社指定業者 | 自分で選ぶ業者 |
|---|---|---|
| 費用 | 相場より高い傾向(中間マージンが上乗せ) | 相場通りまたは安い傾向 |
| 品質 | 管理会社が品質を担保 | 自分で品質を確認する必要あり |
| 手間 | 管理会社が手配(借主は楽) | 自分で探す手間がかかる |
| トラブル時 | 管理会社が窓口になる | 業者と直接やりとり |
1-2. 費用差が生まれる仕組み
管理会社指定業者の見積もりが高くなりやすい理由は、管理会社が業者との間で中間マージン(紹介料・手数料)を受け取っている場合があるためです。これは違法ではありませんが、借主にとっては余計なコストになります。
第2章:自分で業者を選べるケース・選べないケース
2-1. 選べるケース
以下のような場合は、自分で原状回復業者を選べる可能性があります。
- 契約書に業者指定の条項がない:特約で業者が指定されていなければ自由に選べる
- 指定業者の費用が不当に高額:相場と比べて著しく高い場合は交渉の余地あり
- 大家が直接管理している物件:大家との交渉で柔軟に対応してもらえる場合がある
2-2. 選べないケース
一方で、契約書に業者指定の特約がある場合は、原則として指定業者に依頼する義務があります。ただし、指定業者の見積もりが不当に高額な場合は、その特約自体の有効性を争える可能性があります。
契約書に業者指定の特約があっても、それが「借主に一方的に不利な内容」であれば、消費者契約法により無効と判断されることがあります。指定業者の見積もりが相場の2倍以上であれば、一度専門家に相談することをおすすめします。
第3章:自分で業者を選ぶ際のチェックポイント
3-1. 業者選びで確認すべき5項目
自分で原状回復業者を選ぶ場合は、費用の安さだけでなく、品質・実績・保証の3点も重視することが重要です。安い業者に依頼して工事品質が低かった場合、大家から追加の修繕を求められるリスクがあります。
- 賃貸原状回復の実績:賃貸物件専門の業者が望ましい
- 見積もりの透明性:項目別の詳細な見積もりを出してくれるか
- 施工保証の有無:施工後に不具合があった場合の対応を確認
- 口コミ・評判:実際の利用者の声を確認する
- 対応エリアと納期:退去日までに工事が完了するか確認
3-2. 複数業者から見積もりを取る
最低でも3社以上から見積もりを取ることをおすすめします。相見積もりを取ることで費用の相場が把握でき、不当に高い見積もりを見抜くことができます。また、見積もりは必ず書面(メール可)でもらいましょう。
第4章:指定業者の費用が高額な場合の交渉法
4-1. 交渉の進め方
指定業者の見積もりが相場より高い場合、他社の見積もりを証拠として管理会社に交渉することが有効です。「他社ではこの金額で対応可能」と具体的な数字を示すことで、減額や業者変更に応じてもらえる可能性があります。
- 指定業者の見積もり内訳を取得:項目別の費用明細を要求する
- 他社から相見積もりを取得:同じ工事内容で3社以上から見積もりを取る
- 書面で交渉を開始:相見積もりを添付し、費用の根拠を確認する
- 交渉不成立なら第三者に相談:消費生活センターや宅建協会に相談
4-2. 自分で修理する選択肢
小さな傷やクロスの汚れであれば、DIYで修繕することも選択肢の一つです。ただし、必ず事前に管理会社の承諾を得ること、そして修繕の品質が原状回復の基準を満たすことが条件です。無断でDIY修繕を行うと、追加費用を請求される可能性があります。
第5章:トラブルを防ぐための契約時の確認事項
5-1. 入居時に確認すべき契約書のポイント
退去時の業者トラブルを防ぐ最善策は、入居時に契約書の原状回復条項を詳細に確認しておくことです。特に以下の3点は必ず確認しましょう。
- 業者指定の特約の有無:「原状回復は当社指定業者が行う」等の文言がないか確認
- 原状回復の範囲と負担:借主が負担する範囲が具体的に明記されているか
- 費用の上限や算定基準:「実費精算」「定額」などの費用算定方法
5-2. 入居時の記録を残す重要性
入居時に部屋の状態を写真・動画で記録し、管理会社にも共有しておくことが退去時の業者トラブルを防ぐ最大の武器になります。特に既存の傷や設備の不具合は、日付入りの写真で記録しておきましょう。
原状回復工事の業者選びは、費用に直結する重要なポイントです。「管理会社に任せれば安心」という思い込みを捨て、契約書を確認し、必要に応じて相見積もりを取りましょう。知識と準備が、適正な費用での退去を実現します。
第6章:よくある質問(FAQ)
まとめ:業者選びは契約書の確認と相見積もりが鍵
原状回復工事の業者選びは、契約書の特約確認・相見積もりの取得・品質チェックの3つが鍵です。指定業者に不満がある場合は、冷静に証拠を揃えて交渉しましょう。
この記事のポイント
- 業者を選べるかの判断基準
- 契約書に業者指定の特約があるか確認
- 特約がなければ自分で業者を選べる
- 不当に高額な指定業者は交渉で変更可能
- 業者選びの実践ポイント
- 最低3社以上から相見積もりを取る
- 賃貸原状回復の実績と保証を確認
- 入居時に部屋の状態を写真で記録
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の原状回復工事については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 業者選定や費用交渉については個別の契約内容や状況により判断が異なります。具体的な対応は弁護士等の専門家にご相談ください。