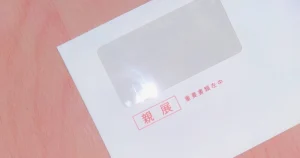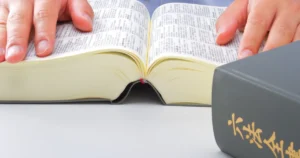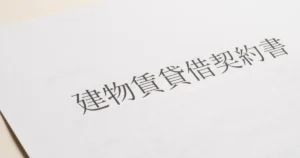【不動産の転貸とは】バレた時のリスクをわかりやすく解説
不動産の転貸借とは、賃借人が貸主の同意を得て第三者に物件を又貸しする契約形態であり、無断で行った場合には契約解除や損害賠償のリスクが発生します。
転貸借は一般的に「また貸し」として知られており、賃貸人、賃借人、転借人の三者間で複雑な法律関係が生まれるでしょう。
賃貸物件でトラブルが発生した借主にとって、転貸借の法的な仕組みを理解することは、将来的な法的リスクを回避するために極めて重要になります。
本記事では、国土交通省が発行している原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)に基づき、転貸借の法的な取り扱いとバレた時のリスクについて詳しく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
不動産転貸借とはどのような契約形態なのか?
転貸借契約とは、賃借人が賃貸人から借りた物件を第三者に貸し出す法的な契約関係を指します。
通常の賃貸借契約では、賃貸人(物件オーナー)と賃借人(借主)の二者間で契約が成立しますが、転貸借では新たに転借人(また借りする人)が加わり、三者間の関係になるでしょう。
転貸借における三者の法律関係
転貸借契約では、賃貸人(A)、賃借人(B)、転借人(C)の間に異なる契約関係が発生します。
賃貸人(A)と賃借人(B)の間には原契約である賃貸借契約が存在し、賃借人(B)と転借人(C)の間には転貸借契約が結ばれることになります。
さらに、賃貸人(A)と転借人(C)の間には直接的な契約関係はないものの、法律上特別な関係が認められる点が重要でしょう。
転貸借とサブリースの違い
転貸借と混同されやすいのがサブリース契約ですが、両者には明確な違いがあります。
サブリースは不動産会社が物件オーナーから建物全体を一括で借り上げ、管理・運営を行いながら入居者に転貸するシステムになります。
サブリースでは家賃保証制度により、空室があってもオーナーに安定した収入が保証される特徴があるでしょう。
転貸借は個人間でも発生する契約関係ですが、法的な複雑さから専門家への相談をお勧めします。
転貸借の契約方法にはどのような種類があるのか?
転貸借契約を行う方法には、主に「転貸借方式」と「代理委託方式」の二つのアプローチが存在します。
それぞれの方式には異なるメリットとデメリットがあり、どちらを選択するかによって法的な責任の所在や運営方法が大きく変わるでしょう。
転貸借方式による契約
転貸借方式では、賃借人が直接転借人に物件を貸し出し、賃料設定や契約条件の決定権を持ちます。
この方式では賃借人が転貸経営の主体となるため、収益性を高められる可能性がある一方で、運営に関する責任も全て負うことになるでしょう。


- 賃貸人からの明確な承諾を事前に取得する
- 転借人との契約条件を詳細に決定する
- 原契約の期間内で転貸期間を設定する
- 転借人への管理責任を明確にする
- 賃料回収と支払いの責任を負う
代理委託方式による契約
代理委託方式では、賃貸人が不動産会社に物件の管理・運営を委託し、専門的な知識とノウハウを活用します。
不動産会社が入居者募集、契約手続き、日常管理を代行するため、賃貸人の負担を大幅に軽減できる一方で、管理手数料が発生するでしょう。
この方式では法的な責任は基本的に賃貸人にありますが、実務的な運営は不動産会社が担当するため、専門的なトラブル対応が期待できます。
どちらの方式を選択する場合でも、契約書面の作成と法的要件の確認が不可欠です。
無断転貸が発覚した場合のリスクとは何か?
無断転貸が発覚した場合、賃貸借契約の解除、損害賠償請求、強制退去などの深刻な法的リスクが発生します。
民法では、賃借人は賃貸人の承諾を得ずに転貸を行うことを禁じており、違反した場合には信頼関係の破綻として契約解除事由になるでしょう。
契約解除のリスク
無断転貸は賃貸借契約における重大な違反行為として扱われ、賃貸人は契約解除権を行使できます。
ただし、判例では賃貸人と賃借人間の信頼関係が完全に破綻している場合に限り契約解除が認められており、軽微な転貸であれば解除が否定される場合もあるでしょう。
裁判所は個別の事情を総合的に判断して、解除の可否を決定するため、画一的な基準はありません。
損害賠償請求のリスク
無断転貸により賃貸人に損害が生じた場合、賃借人は民法上の債務不履行責任や不法行為責任を負う可能性があります。
損害賠償の範囲には、物件の価値低下、修繕費用、失われた家賃収入、法的手続き費用などが含まれることになるでしょう。


- 契約解除通知の受領
- 損害賠償額の算定
- 退去期限の設定
- 法的手続きの開始
- 強制執行の可能性
無断転貸のリスクは非常に高いため、必ず事前に賃貸人の承諾を得ることが重要です。
転貸借リスクを軽減するための対策方法とは?
転貸借に関するリスクを軽減するためには、事前の十分な準備と適切な契約手続きが不可欠になります。
特に賃貸人との事前協議、契約条項の明確化、専門家への相談が重要な対策となるでしょう。
賃貸人との事前協議
転貸を検討する場合、最初に行うべきは賃貸人との詳細な協議です。
転貸の目的、期間、転借人の属性、賃料設定などについて包括的に説明し、書面による明確な承諾を取得することが必須でしょう。
口約束ではなく、承諾書や覚書などの書面で記録を残すことにより、後日のトラブルを防止できます。
契約条項の明確化
転貸借契約では、権利義務関係を明確にするため、詳細な契約条項の設定が重要になります。
| 契約条項 | 明確化すべき内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 原契約の期間を超えない設定 |
| 賃料設定 | 適正な市場価格の調査 |
| 管理責任 | 修繕・清掃の責任分担 |
| 解約条件 | 中途解約の要件と手続き |
契約書には転借人の身元確認、連帯保証人の設定、原状回復義務なども詳細に規定する必要があるでしょう。
契約書の作成では法的な専門知識が必要なため、行政書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
民泊事業における転貸借活用の注意点とは?
近年、民泊事業での転貸借活用が注目されていますが、住宅宿泊事業法や旅館業法などの特別な法規制が適用されるため、より慎重な対応が必要です。
民泊事業では不特定多数の利用者が物件を使用するため、通常の転貸借よりも高いリスクが伴うでしょう。
賃貸人からの明確な許可取得
民泊事業を目的とした転貸借では、一般的な転貸承諾だけでなく、民泊事業に対する明確な許可が必要になります。
多くの賃貸借契約では民泊利用が禁止されているため、事前に契約書の確認と賃貸人との詳細な協議が不可欠でしょう。
民泊許可の取得、近隣住民への配慮、管理体制の整備なども同時に検討する必要があります。
専門会社への委託検討
民泊事業における転貸借は法的・実務的に複雑なため、専門知識を持つ不動産会社への委託も有効な選択肢です。
専門会社では民泊事業の許可申請、運営管理、法令順守などを包括的にサポートしており、リスクを大幅に軽減できるでしょう。
委託費用は発生しますが、法的トラブルの回避と効率的な運営を考慮すると、費用対効果の高い選択になります。
民泊事業では法的手続きが複雑になるため、認定司法書士や弁護士への相談も検討されることをお勧めします。
まとめ
不動産の転貸借は賃借人が第三者に物件を又貸しする契約形態であり、適切な手続きを踏めば有効な活用方法となります。
しかし、無断転貸を行った場合には契約解除、損害賠償請求、強制退去などの深刻なリスクが発生するでしょう。
転貸借を安全に行うためには、賃貸人からの事前承諾取得、詳細な契約条項の設定、専門家への相談が不可欠になります。
特に民泊事業での転貸借活用では、住宅宿泊事業法などの特別法規制も考慮しなければなりません。
転貸借は複数の当事者が関わる複雑な法律関係であるため、契約内容を明確にし、リスクを理解した上で適切に運用することが重要です。
法的手続きが複雑な場合には、認定司法書士や弁護士などの専門家のサポートを積極的に活用することをお勧めします。
- 転貸借は賃貸人の承諾が必要で、無断で行うと契約解除のリスクがある
- 三者間の法律関係が複雑になるため事前の詳細な取り決めが重要
- 転貸借方式と代理委託方式では責任の所在が異なる
- 民泊事業では特別法規制の順守が必要になる
- 複雑な法的手続きでは専門家への相談が効果的である