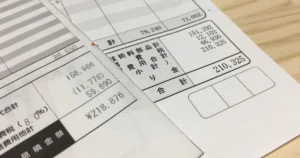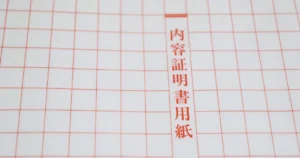国土交通省 賃貸住宅の原状回復ガイドラインをわかりやすく解説!退去時の費用負担はどうなる?
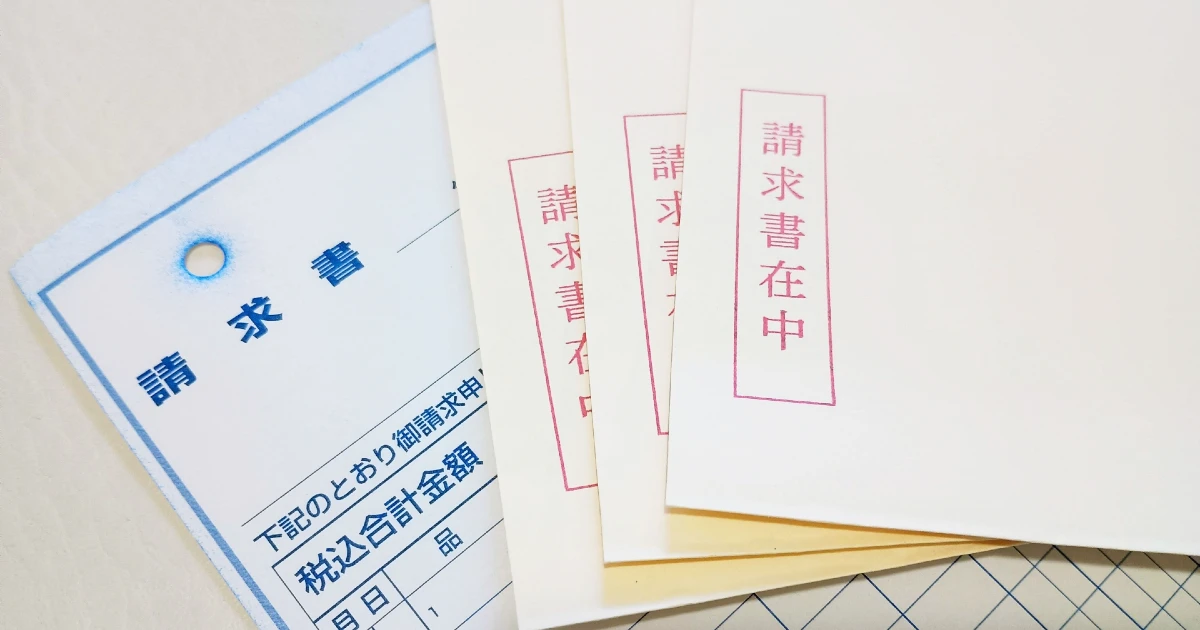
賃貸物件を退去する際、「原状回復費用」という名目で高額な請求を受けている借主は少なくありません。
「これって本当に払う必要があるの?」と疑問に思ったことのある方も多いでしょう。
実は、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という指針を公表しており、これに基づけば不当な請求から身を守ることができます。
このガイドラインは、賃貸住宅の退去時における原状回復の費用負担のルールを明確にしたもので、借主と貸主の間で生じやすいトラブルを未然に防ぐことを目的としています。
最新版では、経年劣化や通常使用による損耗については借主に修繕費用の負担義務がないことがはっきりと示されています。
この記事では、原状回復ガイドラインの内容をわかりやすく解説し、耐用年数や経年劣化、減価償却の考え方、そして退去時の費用負担の割合について詳しく説明します。
これを理解することで、退去時のトラブルを避け、不当な請求から自分を守るための知識を得ることができます。

監修者
サレジオ学院高等学校を昭和57年に卒業後、法曹界への志を抱き、中央大学法学部法律学科へと進学。同大学では法律の専門知識を着実に積み重ね、昭和62年に卒業。
その後、さまざまな社会経験を経て、より専門的な形で法務サービスを提供したいという思いから、平成28年に行政書士試験に挑戦し、合格。この資格取得を機に、平成29年4月、依頼者の皆様に寄り添った丁寧なサービスを提供すべく「綜合法務事務所君悦」を開業いたしました。
長年培った法律の知識と実務経験を活かし、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えできるよう、日々研鑽を重ねております。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
原状回復の意味と基礎知識

原状回復とは、賃借人(借主)が賃貸物件を借りた当時の状態に戻すことを指します。
しかし、すべてを元の状態に戻す必要があるわけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されています。
- 日常生活で生じる自然な劣化(経年劣化)や通常の使用による損耗は借主負担ではない
- タバコのヤニや落書き、ペットによる傷などは「通常の使用を超える損耗」として借主負担となる
- ガイドラインは法的拘束力はないが、裁判の判断基準として用いられることが多い
設備の経年劣化の判断基準

経年劣化とは、時間の経過とともに物件の価値が自然に減少していく現象を指します。
国土交通省のガイドラインでは、この経年劣化部分については貸主負担とすることが明確に示されています。
しかし、何をもって経年劣化と判断するかが問題になるケースが多いのです。
経年劣化の判断基準として重要なのは「使用期間」と「物件の状態」です。
例えば、クロスの変色や日焼け、浴室やキッチンの水垢、畳の日焼けや退色などは、通常の生活を送っていれば必然的に発生するものであり、経年劣化として扱われます。
- 経年劣化は貸主負担と明確に示されている
- 設備機器や内装材には一般的な「耐用年数」があり、これを経過した設備の交換費用は原則として貸主負担
- 経年劣化と判断される例:日照による壁紙の変色、通常使用による設備の劣化、家具による床の凹みなど
主な設備の耐用年数の一覧

賃貸物件の設備や内装材には、それぞれ一般的な耐用年数が設定されています。
国土交通省のガイドラインでは、これらの耐用年数を基準に、修繕費用の負担割合を算出する方法が示されています。
- 主な設備・内装材の耐用年数(目安)
- 壁紙(クロス):6年
- フローリング:15年
- 畳:6年
- ふすま・障子:6年
- 浴槽・風呂釜:15年
- 給湯器:8年
- エアコン:10年
- 流し台(キッチン):10年
- 便器:15年
- 耐用年数を超えた設備の修繕・交換費用は基本的に貸主負担
- 借主の故意・過失による破損の場合は、経過年数に応じて負担割合が決まる
設備の減価償却の計算方法

減価償却とは、時間の経過とともに設備や内装材の価値が減少していくことを数値化したものです。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、この減価償却の考え方を用いて、借主の負担額を計算することを推奨しています。
- 減価償却の基本的な計算式:借主負担額 = 修繕費用 × (1 – 経過年数 ÷ 耐用年数)
- 経過年数が耐用年数を超えている場合は、原則として借主の負担はゼロ
- 「定額法」が一般的な減価償却の方法としてガイドラインで推奨されている
例えば、耐用年数6年の壁紙を4年間使用した後、借主の過失で修繕が必要になった場合
借主負担額 = 修繕費用 × (1 - 4 ÷ 6) = 修繕費用 × 1/3つまり、修繕費用の約33%が借主の負担となります。残りの67%は経年劣化分として貸主の負担です。
退去時の主な原状回復費用の項目

退去時にかかる費用は大きく分けて「原状回復費用」と「クリーニング費用」、そして「その他の費用」に分類されます。
国土交通省のガイドラインでは、これらの費用の負担区分について明確な指針が示されています。
- 原状回復費用の主な項目:壁紙の張替え、フローリングの修繕、畳の表替え、設備機器の修理など
- 通常の清掃(ハウスクリーニング)は原則として借主負担
- 特殊清掃(タバコのヤニ除去など)は、原因によって負担者が決まる
- 「精算書」の内容を必ず確認し、不明点は説明を求める
- 退去時の立会いと写真・動画による記録保存がトラブル防止に有効
注意すべきポイントとして、「精算書」の内容を必ず確認することが重要です。
退去時に貸主または管理会社から提示される精算書には、修繕内容や費用、そして借主負担額の根拠が明記されているはずです。
不明な点や疑問がある場合は、必ず説明を求めましょう。
退去費用の負担割合の決まり方

国土交通省のガイドラインでは、原状回復費用の負担割合について詳細な表が示されています。
この負担割合表は、「経過年数」と「借主の使用状況」を基に、貸主と借主の負担割合を明確にするものです。
- 負担割合を決める主な要素:設備の耐用年数、経過年数、損傷の原因と程度
- 通常の使用による汚れや変色は貸主負担100%
- 借主の故意・過失による損傷は借主負担が基本だが、経過年数に応じて按分される
- 修繕費用の見積もりは複数の業者から取得することが望ましい
- 入居時に「原状回復特約」の内容を確認することがトラブル防止につながる
例えば、壁紙の負担割合について考えてみましょう。
| 損傷の種類 | 借主負担割合 | 貸主負担割合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常の使用による汚れや変色 | 0% | 100% | 経年劣化として貸主負担 |
| 家具の設置による黒ずみ | 0% | 100% | 通常使用の範囲内 |
| 壁に釘やネジを打った跡 | 経過年数により変動 | 経過年数により変動 | 経過年数÷耐用年数(6年)で按分 |
| タバコのヤニや落書き | 100% | 0% | 借主の故意・過失による損傷 |
このように、ガイドラインを理解しておくことで、不当な請求から自身を守ることができます。
退去時に疑問を感じたら、上記の基準を参考にして、貸主や管理会社と冷静に話し合いましょう。
また、地域の消費生活センターや法律相談窓口などの第三者機関に相談するという選択肢もあります。
賃貸契約においては、知識が最大の武器になります。
まとめ

国土交通省の原状回復ガイドラインは、賃貸住宅の退去時における費用負担のルールを明確にした重要な指針です。
このガイドラインによれば、経年劣化や通常の使用による損耗については借主の負担とはならず、借主の故意・過失による損傷のみが借主負担となります。
設備や内装材には耐用年数が設定されており、これを基に減価償却計算が行われます。
例えば、壁紙の耐用年数は6年、フローリングは15年などと定められており、経過年数に応じて借主の負担割合が減少していきます。
耐用年数を超えた設備の修繕費用は、原則として借主負担はゼロです。
退去時には、敷金精算書の内容をしっかりと確認し、不明点があれば説明を求めることが大切です。
また、退去時の立会いや写真による記録は、後のトラブル防止に有効です。
原状回復をめぐるトラブルを防ぐためには、入居前に契約内容をよく確認し、退去時の費用負担について理解しておくことが重要です。
国土交通省のガイドラインは法的拘束力はありませんが、裁判の判断基準として用いられることが多く、自分の権利を守るための強力な味方となります。
賃貸住宅に関するトラブルは、知識があれば多くは防ぐことができます。
このガイドラインの内容を理解し、必要に応じて専門家に相談することで、不当な請求から自分を守り、適正な費用負担で退去手続きを進めることができるでしょう。