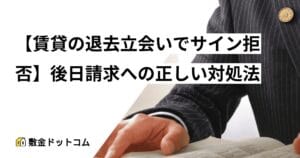【少額訴訟とは】退去費用を減額する際の注意点
賃貸物件の退去時に高額な原状回復費用を請求されて困っている借主の方へ。
少額訴訟は60万円以下の金銭トラブルを迅速かつ低コストで解決できる制度であり、退去費用の減額交渉が決裂した場合の有効な手段となります。
しかし、少額訴訟にはメリットとデメリットがあるため、国土交通省の原状回復ガイドラインを正しく理解したうえで慎重に判断する必要があるでしょう。
本記事では、行政書士として多くの賃貸トラブル相談を受けた経験から、少額訴訟を活用する際の注意点と具体的な対応方法について詳しく解説いたします。

監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
少額訴訟とは
少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払いを求める民事訴訟を簡易・迅速に解決するための特別な裁判手続きになります。
通常の民事訴訟では判決まで数か月から1年以上かかることが多いものの、少額訴訟では原則として1回の審理で判決が下されるでしょう。
少額訴訟の基本的な特徴

- 請求額は60万円以下に限定される
- 原則として1回の審理で判決が確定する
- 手続きが簡素化されており自分で行うことも可能
- 訴訟費用が通常の民事訴訟より安価
- 和解による解決も積極的に推進される
退去費用のトラブルでは、管理会社や大家から請求される原状回復費用が国土交通省のガイドラインに反している場合、少額訴訟による解決が効果的です。
少額訴訟は「小さな額の大きな正義」を実現する制度として設計されており、個人でも利用しやすい仕組みになっています。
退去費用で少額訴訟を活用できるケース
賃貸物件の退去時における少額訴訟の活用は、国土交通省の原状回復ガイドラインに明らかに反する不当な費用請求を受けた場合に特に有効でしょう。
具体的な活用場面
原状回復ガイドラインでは、経年変化や通常使用による損耗は貸主負担とされており、借主が費用を負担する必要はありません。


- 日照によるクロスや畳の変色費用を請求された場合
- 家具設置による床のへこみ跡の修繕費を求められた場合
- 通常使用範囲内の汚れに対する清掃費を要求された場合
- エアコン等の設備の経年劣化による交換費用を請求された場合
- 敷金の返還を不当に拒否された場合
実際にガイドラインに掲載されてある事例では、畳、襖、クロス(壁紙)、クッションフロアの張替え並びに清掃費用として48万2350円を請求された借主が、最終的に19万8000円まで減額できたケースがあります。
少額訴訟を検討すべきタイミング
管理会社や大家との交渉が決裂し、ガイドラインに基づく合理的な根拠を示しても費用請求が変わらない場合、少額訴訟の検討時期といえるでしょう。
ただし、訴訟前には必ず内容証明郵便による最終通告を行い、和解の余地を探ることが重要になります。
経験上、内容証明郵便を送付した段階で相手方が態度を軟化させ、和解に応じるケースも少なくありません。
少額訴訟の手続きと流れは?
少額訴訟の手続きは簡素化されており、個人でも比較的容易に行うことができるでしょう。
ただし、確実な勝訴を目指すためには事前準備が重要であり、国土交通省のガイドラインに基づく適切な主張と証拠の整理が必要になります。
訴訟提起までの準備


- 賃貸借契約書の内容確認と写真撮影
- 入居時・退去時の物件状況確認書の整理
- 管理会社からの請求書と見積書の分析
- ガイドラインに基づく反駁資料の作成
- 交渉経緯を示すメールや書面の保管
特に重要なのは、入居時の物件状況と退去時の状況を客観的に比較できる証拠を整えることです。
訴状作成のポイント
少額訴訟の訴状は定型書式を使用するため、記載内容を明確にすれば作成可能でしょう。
請求の趣旨では「敷金○○万円の返還」または「過払い原状回復費用○○万円の返還」を明記し、請求の原因では国土交通省ガイドラインに反する請求である旨を具体的に記載することが重要になります。
訴訟費用は請求額に応じて決まり、10万円の請求であれば1,000円、30万円の請求であれば3,000円程度と低額に設定されています。
訴状作成に不安がある場合は、裁判所の窓口で相談することもできますし、認定司法書士や弁護士に依頼することも可能です。
少額訴訟のメリット・デメリットとは?
少額訴訟は迅速性と低コストが魅力的な制度ですが、利用前にメリットとデメリットを十分に理解しておく必要があるでしょう。
少額訴訟のメリット
| メリット項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 迅速性 | 原則1回の審理で判決、2-3か月で解決 |
| 低コスト | 訴訟費用が安く、弁護士費用も不要 |
| 簡便性 | 手続きが簡素で個人でも対応可能 |
| 和解推進 | 裁判所が積極的に和解を勧めてくれる |
特に退去費用のトラブルでは、ガイドラインという明確な基準があるため、主張が認められる可能性が高く、相手方も早期和解に応じやすい傾向があります。
少額訴訟のデメリット


- 請求額が60万円以下に限定される
- 控訴ができず判決が確定してしまう
- 相手方が通常訴訟への移行を求める可能性がある
- 証拠調べが制限され十分な審理ができない場合がある
- 敗訴した場合の心理的ダメージが大きい
特に注意すべきは、相手方が通常訴訟への移行を申し立てた場合、少額訴訟から通常の民事訴訟に変更されてしまう点でしょう。
通常訴訟になると審理期間が長期化し、弁護士費用も必要になる可能性が高まります。
デメリットを理解したうえで、費用対効果を慎重に検討することが重要です。場合によっては、弁護士に相談してから判断することをお勧めします。
被告側の対応と成功事例は?
少額訴訟を提起された管理会社や大家の対応パターンを理解しておくことで、より戦略的にアプローチすることが可能になるでしょう。
相手方の典型的な対応パターン
管理会社や大家が少額訴訟を提起された場合、多くのケースで以下のような対応を取る傾向があります。


- まず和解による早期解決を模索する
- 特約条項を根拠に反論を展開する
- 通常訴訟への移行を申し立てる
- 弁護士を代理人として立てる
- 請求額の一部のみ認める部分和解を提案する
実際の事例では、訴訟提起後に相手方から「ガイドラインに準拠した再計算を行いたい」という和解提案がなされることが多く、この段階で大幅な減額が実現するケースが少なくありません。
一般的な解決事例
退去費用トラブルの一般的な解決事例として、以下のようなケースが報告されています。
賃借期間が約3年8か月のマンションを退去する際、管理会社からカーペットの敷替え、壁・天井クロス(壁紙)の張替え等の原状回復工事費用として65万6785円の支払いを求めて提訴されたケースがありました。
国土交通省ガイドラインに掲載された判例では、原状回復工事の適正範囲について具体的な判断が示されています。
カーペット敷替えや畳取替えなどの過度な工事が否定され、クロス張替えについても下地調整費用等が減額されるなど、賃借人負担の適正化が図られました。
また、室外クリーニングについては「契約の合意項目にない」として負担義務が否定されています。最終的に認定された費用は合計35万8682円となりました。
このような判例は、原状回復費用の適正化において重要な指針となっています。
書類作成の観点から申し上げると、ガイドラインの正確な理解と適切な証拠の整理が重要です。具体的な戦略については認定司法書士や弁護士にご相談ください。
まとめ
賃貸物件の退去費用トラブルにおいて、少額訴訟は迅速かつ低コストで問題解決を図れる有効な手段といえます。
ただし、国土交通省の原状回復ガイドラインを正しく理解し、適切な証拠を整理したうえで慎重に判断することが成功の条件でしょう。
訴訟提起前の交渉段階でも、ガイドラインに基づく論理的な主張により、多くのケースで費用減額が実現できます。
実際の手続きについては、司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、より確実な解決を目指すことができるでしょう。
退去費用でお困りの際は、まずガイドラインの内容を確認し、請求の妥当性を検証することから始めてみてください。
- 少額訴訟は60万円以下の退去費用トラブルに有効な解決手段
- 国土交通省のガイドラインが強力な根拠となる
- 訴訟前の交渉段階でも大幅な費用減額が期待できる
- メリット・デメリットを十分理解して慎重に判断する
- 専門家への相談により成功確率を高められる