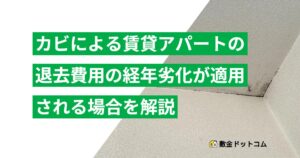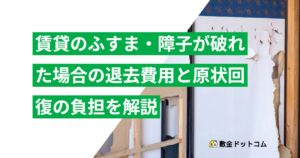【少額訴訟とは】退去費用を減額する際の注意点を行政書士が解説
「少額訴訟と通常訴訟の違いをご存知ですか?」——退去費用の請求額に納得がいかず、管理会社や貸主との交渉が平行線のまま進まないケースは少なくありません。
結論から言えば、少額訴訟は60万円以下の金銭トラブルを原則1回の審理で解決できる制度であり、退去費用の減額交渉が決裂した場合の有効な手段となります。通常の民事訴訟に比べて手続きが簡素化されており、弁護士に依頼せず個人でも申し立てが可能です。
この記事では、少額訴訟と通常訴訟の違いを項目別に比較しながら、退去費用トラブルにおける具体的な活用方法、手続きの流れ、メリット・デメリット、そして相手方の対応パターンまで詳しく解説します。
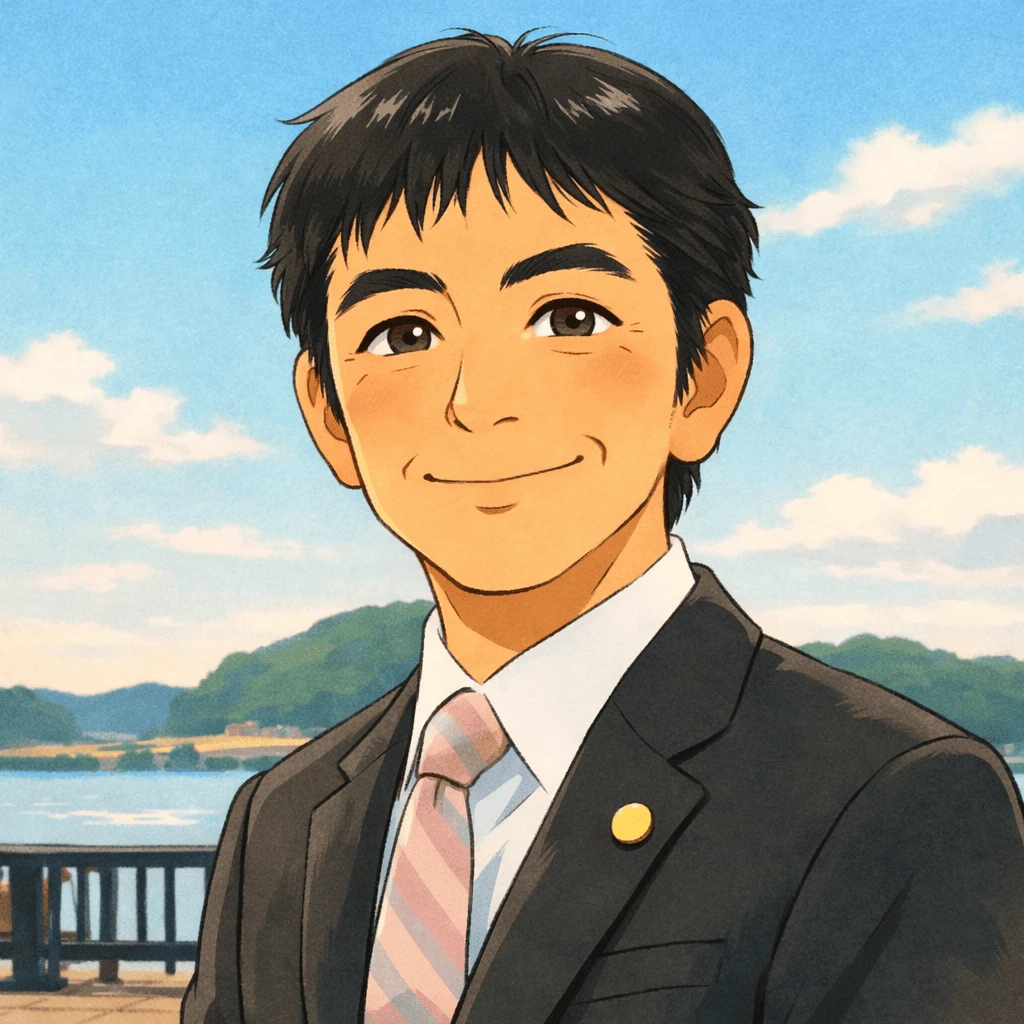
監修者
1982年にサレジオ学院高校を卒業後、中央大学法学部法律学科に進学し1987年に卒業。法曹界を志し、様々な社会経験を経た後、2016年に行政書士試験に合格。2017年4月に「綜合法務事務所君悦」を開業。法律知識と実務経験を活かし、国際業務を中心に寄り添ったサービスを提供している。
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会所属
登録番号 第17090472号
少額訴訟とは?通常訴訟との比較
少額訴訟は、民事訴訟法第368条に基づく簡易裁判所の特別手続きです。60万円以下の金銭支払いを求める場合にのみ利用でき、通常の民事訴訟とは大きく異なる特徴を持っています。
1-1. 少額訴訟の基本的な仕組み
少額訴訟は、原則として1回の審理で判決が下される迅速な裁判手続きです。通常訴訟のように何度も裁判所に足を運ぶ必要がなく、証拠調べから判決まで1日で完結します。
- 請求額の上限:60万円以下の金銭支払い請求に限定
- 審理回数:原則1回の期日で審理・判決
- 利用回数:同一の簡易裁判所で年10回まで
- 証拠方法:即時に取り調べ可能な証拠に限定
1-2. 少額訴訟と通常訴訟の比較表
退去費用トラブルの解決手段を選ぶ際には、少額訴訟と通常訴訟の違いを正確に把握しておくことが重要です。以下の比較表で主な違いを確認しましょう。
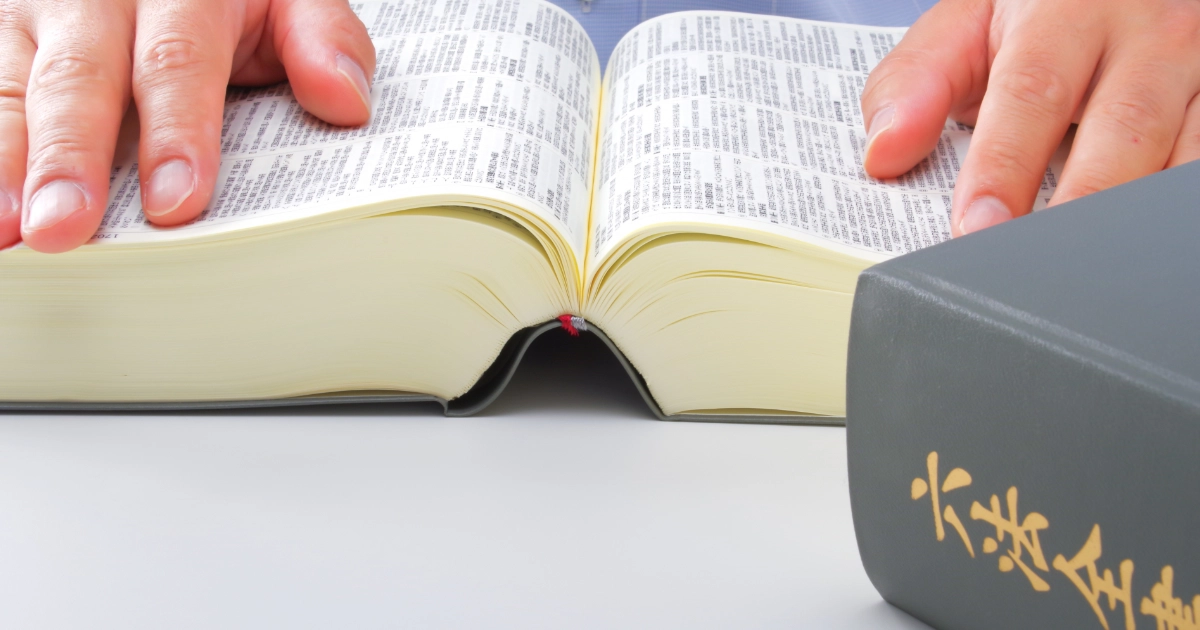
| 比較項目 | 少額訴訟 | 通常訴訟 |
|---|---|---|
| 請求額 | 60万円以下 | 制限なし |
| 審理回数 | 原則1回 | 複数回(数か月〜1年以上) |
| 訴訟費用 | 数千円程度 | 数万円〜 |
| 弁護士の必要性 | 不要(本人訴訟可能) | 事実上必要 |
| 控訴 | 不可(異議申立てのみ) | 可能 |
| 管轄裁判所 | 簡易裁判所 | 地方裁判所(140万円超) |
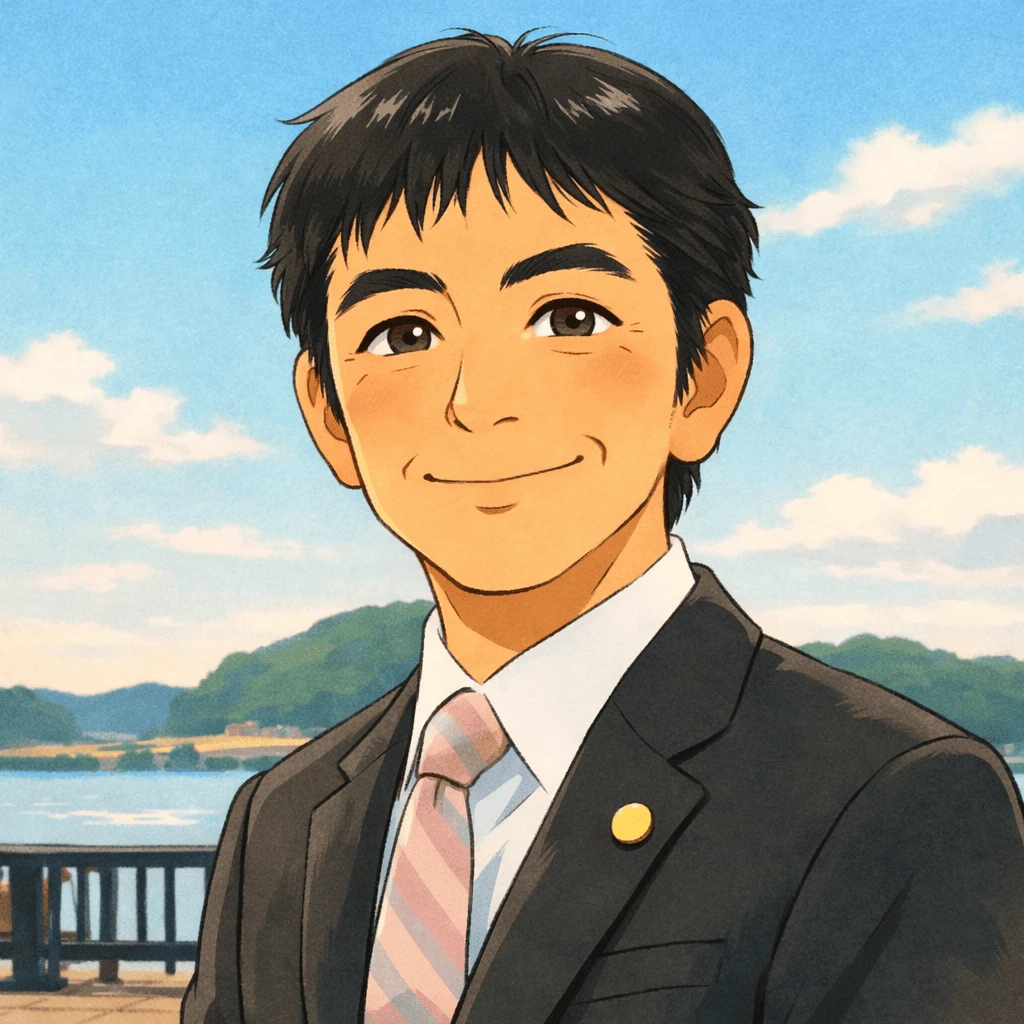 ゲン
ゲン退去費用のトラブルは請求額が60万円以下に収まるケースがほとんどです。まずは少額訴訟の要件に該当するかどうかを確認しましょう。
少額訴訟は退去費用のあらゆるトラブルに使えるわけではありません。国土交通省のガイドラインに明らかに反する不当な請求を受けた場合に、特に有効な手段となります。
2-1. 具体的な活用場面
ガイドラインでは、経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担とされています。以下のようなケースで請求を受けた場合は、少額訴訟による解決が効果的です。
- 経年劣化の請求:日照によるクロスの変色や畳の日焼けを借主負担とされた
- 通常損耗の請求:家具設置による床の凹み跡の修繕費を求められた
- 耐用年数の無視:6年以上居住しているのに壁紙の全額張替え費用を請求された
- 敷金の不返還:正当な理由なく敷金の返還を拒否された
2-2. 少額訴訟を検討すべきタイミング
少額訴訟はいきなり提起するものではなく、段階的な交渉を経ても解決しない場合の最終手段として位置づけるべきです。
- 書面での減額交渉:ガイドラインを根拠に不当な項目を書面で指摘する
- 内容証明郵便の送付:減額や返還を正式に請求する
- 消費生活センターへの相談:第三者機関を通じた解決を試みる
- 少額訴訟の検討:上記の手段で解決しない場合に訴訟を検討する
退去費用の交渉を専門家に依頼する方法は、以下の記事で解説しています。
少額訴訟の手続きと流れ
少額訴訟の手続きは通常訴訟に比べて簡素化されていますが、事前の準備が勝敗を左右します。ここでは訴訟提起から判決までの具体的な流れを解説します。
3-1. 訴訟提起までの準備
少額訴訟を提起する前に、証拠書類をしっかりと整理しておくことが成功の鍵です。原則1回の審理で全ての証拠を提示する必要があるため、事前準備の質が結果を大きく左右します。
- 賃貸借契約書:敷金の金額や特約の内容を確認
- 退去時の精算書:管理会社から受け取った原状回復費用の明細
- 入居時・退去時の写真:部屋の状態を証明する記録
- 交渉の経緯:メールやLINEのやり取り、内容証明郵便の控え
- ガイドラインの該当箇所:請求が不当である根拠の資料
3-2. 訴状作成から判決までの流れ
少額訴訟の手続きは以下の流れで進みます。訴状の書式は裁判所のホームページからダウンロードでき、窓口で記載方法の説明を受けることも可能です。


| 手順 | 内容 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 訴状の作成 | 簡易裁判所の定型書式に記入し、証拠書類を添付 | 1〜2週間 |
| 2. 訴状の提出 | 被告の住所地を管轄する簡易裁判所に提出・手数料納付 | 1日 |
| 3. 期日の指定 | 裁判所が審理の期日を決定し、被告に訴状を送達 | 2〜4週間 |
| 4. 審理・判決 | 双方の主張と証拠を審理し、即日判決または和解 | 1日(期日当日) |
少額訴訟のメリット・デメリット
少額訴訟には迅速・低コストという利点がある一方で、制度上の制約も存在します。退去費用トラブルの解決手段として選ぶ前に、双方を正しく理解しておきましょう。
4-1. 少額訴訟のメリット
- 手続きが簡単:定型書式があり、弁護士なしでも手続き可能
- 費用が安い:訴訟費用は数千円程度で済む
- 迅速な解決:原則1回の審理で判決が出る
- 和解も可能:審理の中で裁判官が和解を勧めることも多い
- 請求額の制限:60万円を超える請求には使えない
- 控訴不可:判決に不服でも上級裁判所への控訴ができない
- 通常訴訟への移行:被告の申述により通常訴訟に移行される場合がある
- 証拠の制約:即時に取り調べ可能な証拠のみ使用できる
4-2. 少額訴訟の費用目安
少額訴訟にかかる費用は、通常訴訟と比べて非常に低額です。合計1万円前後で訴訟を提起できるため、退去費用の減額分を考慮すれば費用対効果は高いと言えます。
- 収入印紙代:請求額に応じて1,000円〜6,000円(例:30万円の請求で3,000円)
- 切手代:約3,000〜5,000円(裁判所による)
- 書類準備費用:コピー代・交通費など数百円〜数千円
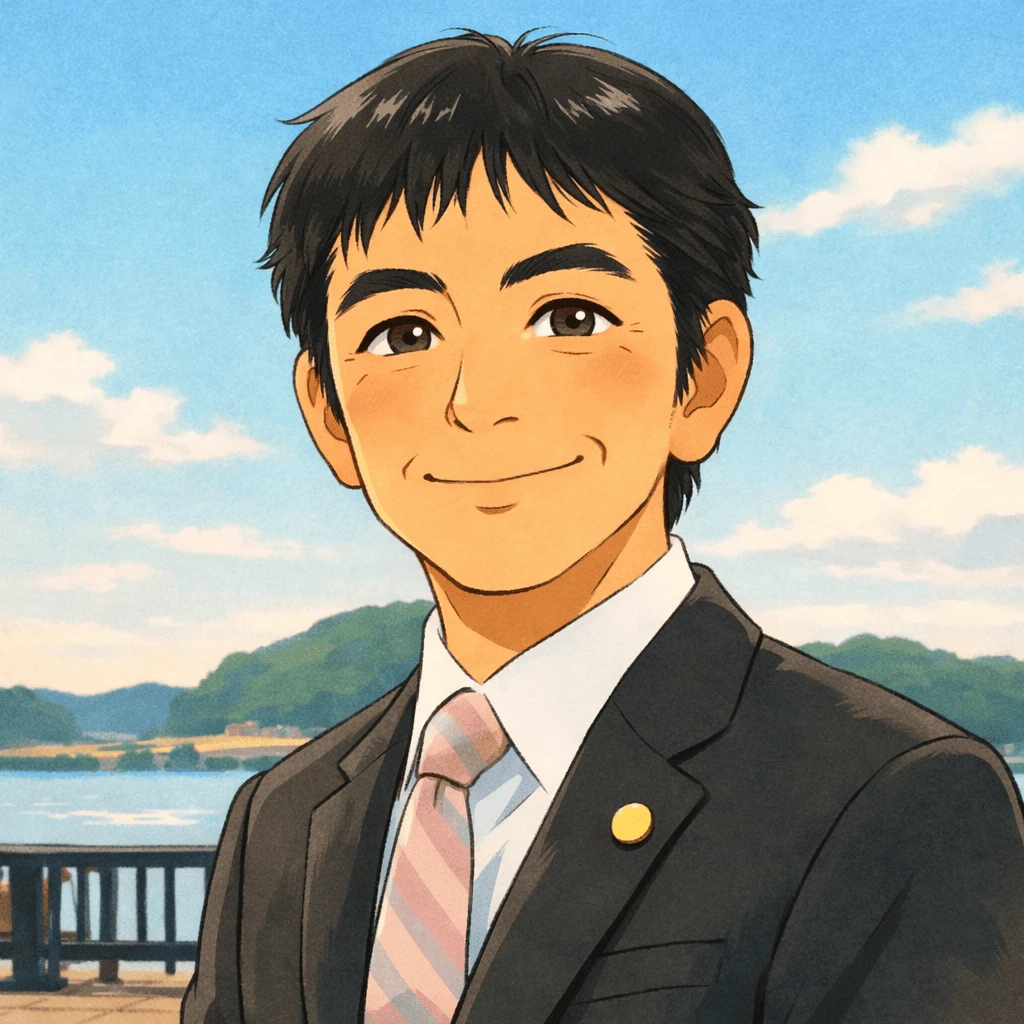
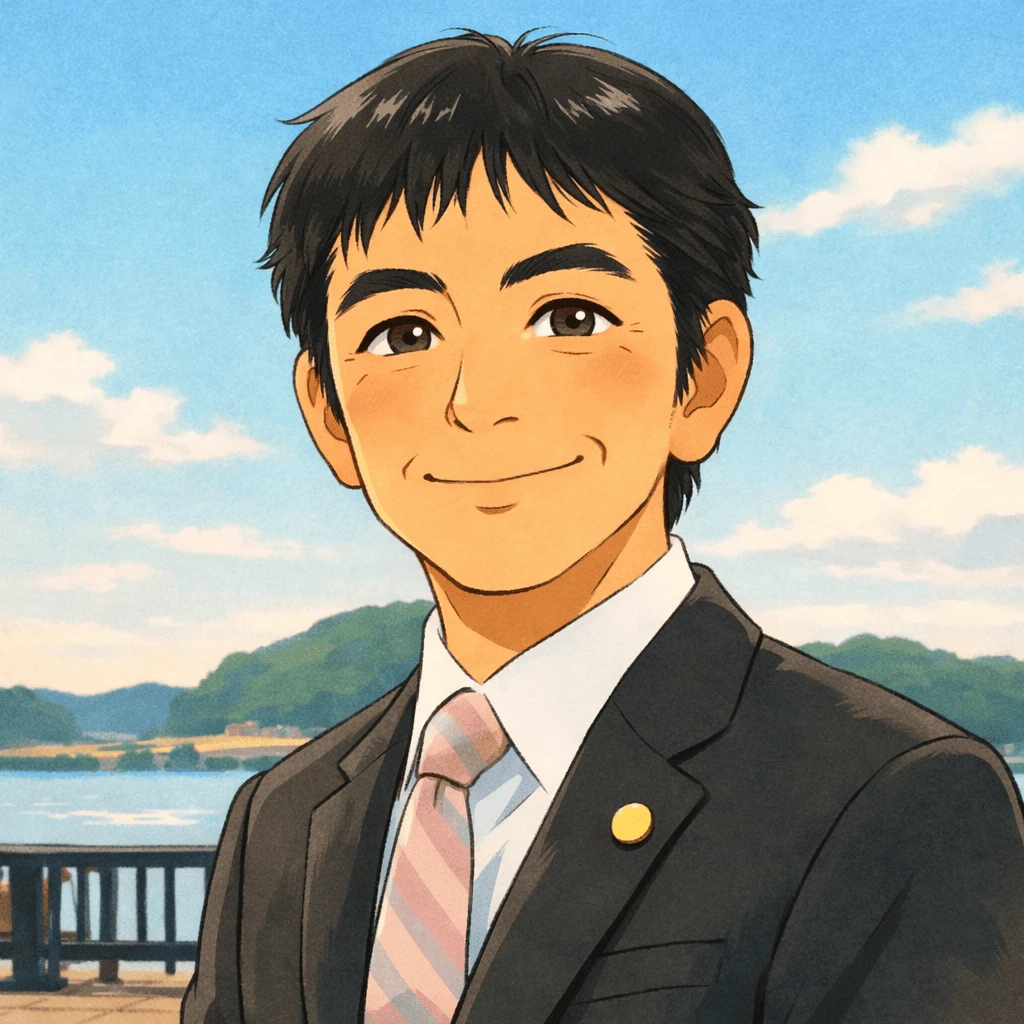
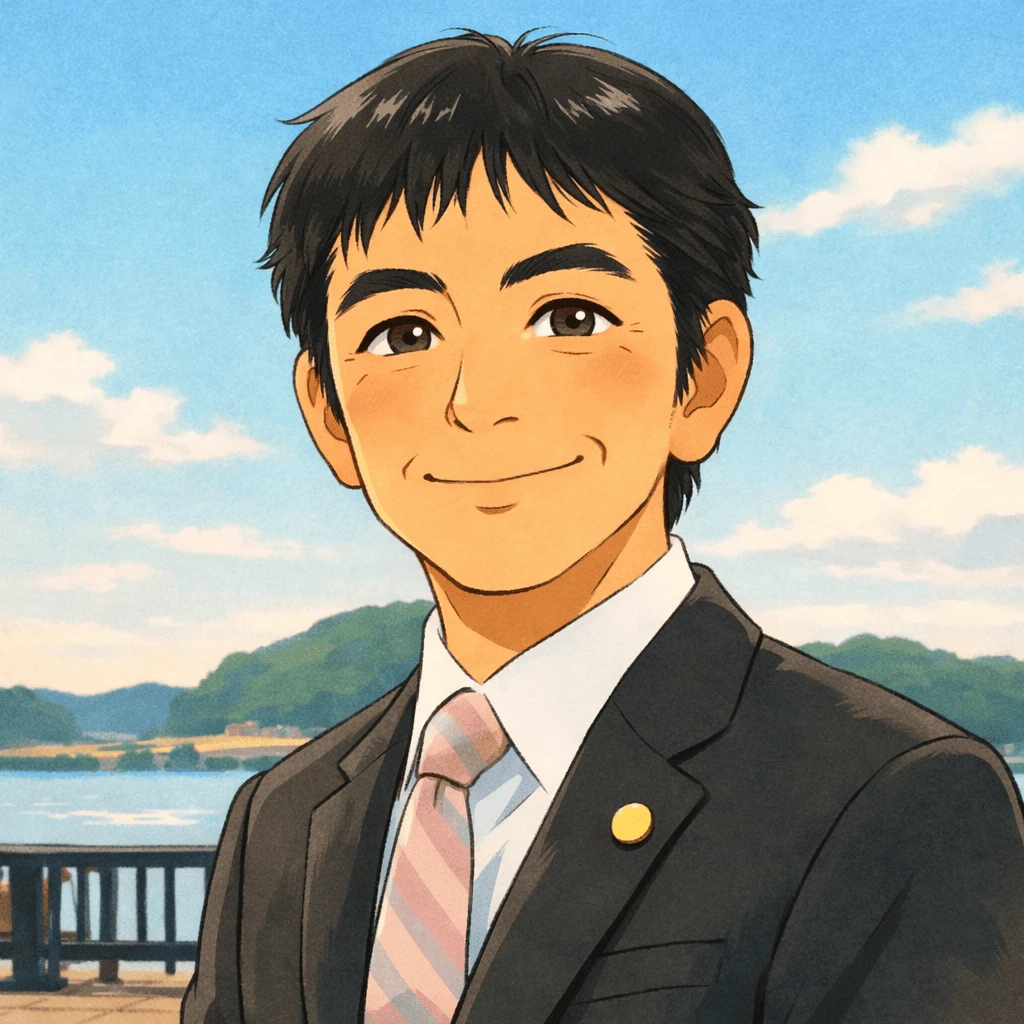
少額訴訟の最大の注意点は、被告(管理会社や貸主)が「通常訴訟への移行」を申し出た場合、自動的に通常訴訟に切り替わることです。大手管理会社は顧問弁護士がいるため、この移行を申し出るケースもあります。
少額訴訟を提起した場合、相手方(管理会社・貸主)はどのような対応を取るのでしょうか。一般的な対応パターンと、退去費用トラブルの典型的な解決事例を紹介します。
5-1. 相手方の典型的な対応パターン
少額訴訟を提起された被告側の対応は、主に以下の3パターンに分かれます。
- 訴訟前の和解:訴状が届いた時点で減額に応じ、裁判前に示談が成立する
- 通常訴訟への移行申述:被告が少額訴訟を拒否し、通常の民事訴訟への移行を求める
- 審理当日の和解:裁判官の勧めにより、審理当日に和解が成立する
5-2. 一般的な解決事例
退去費用トラブルで少額訴訟を活用した場合の典型的な解決パターンをまとめました。実際には訴訟提起の段階で相手方が減額に応じるケースが多いため、訴訟まで至らずに解決する場合も少なくありません。


| ケース | 請求内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 経年劣化の壁紙請求 | 8年居住後に壁紙全面張替え費用15万円を請求 | ガイドラインに基づき耐用年数超過を主張、全額免除 |
| 通常損耗の床修繕 | 家具設置跡の修繕費8万円を請求 | 通常損耗に該当するとして請求取り下げ |
| 敷金の不当控除 | 敷金20万円から清掃費・修繕費として18万円を控除 | 和解により12万円の返還で合意 |
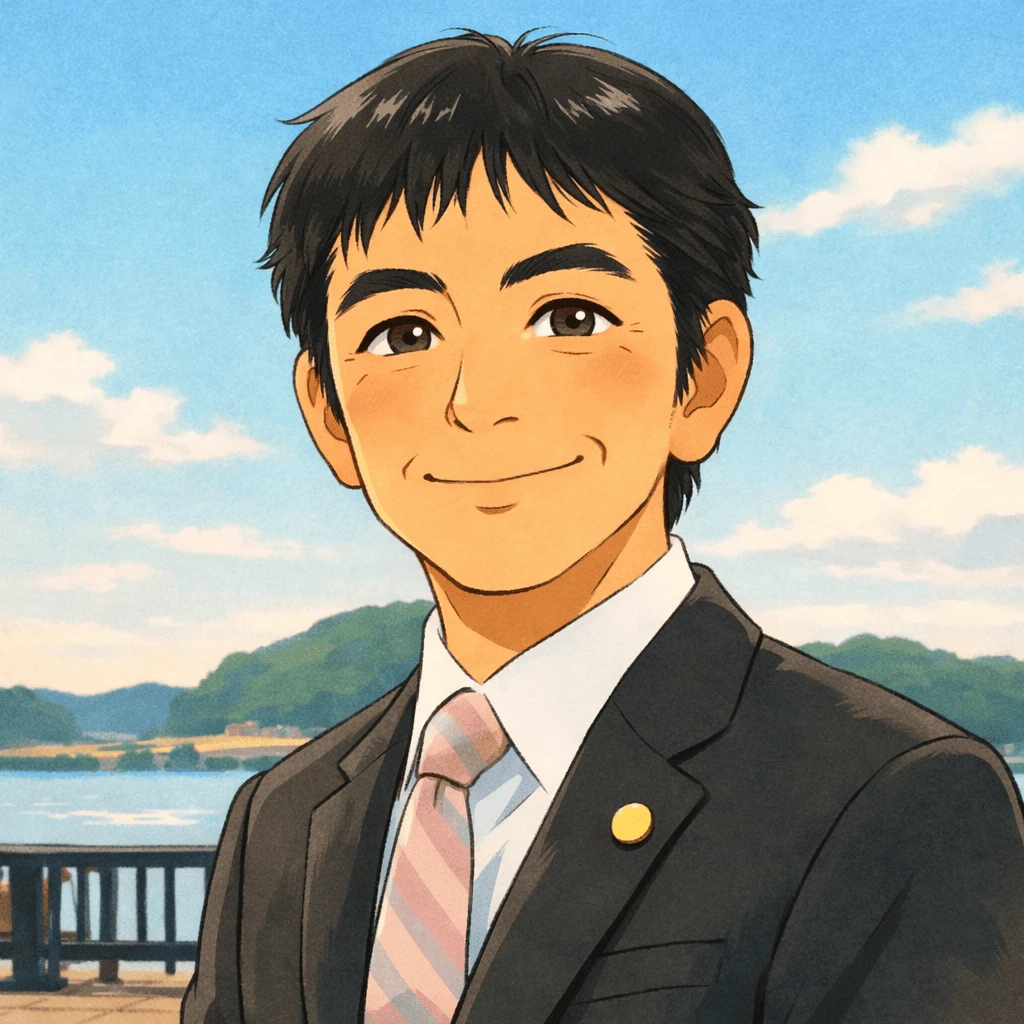
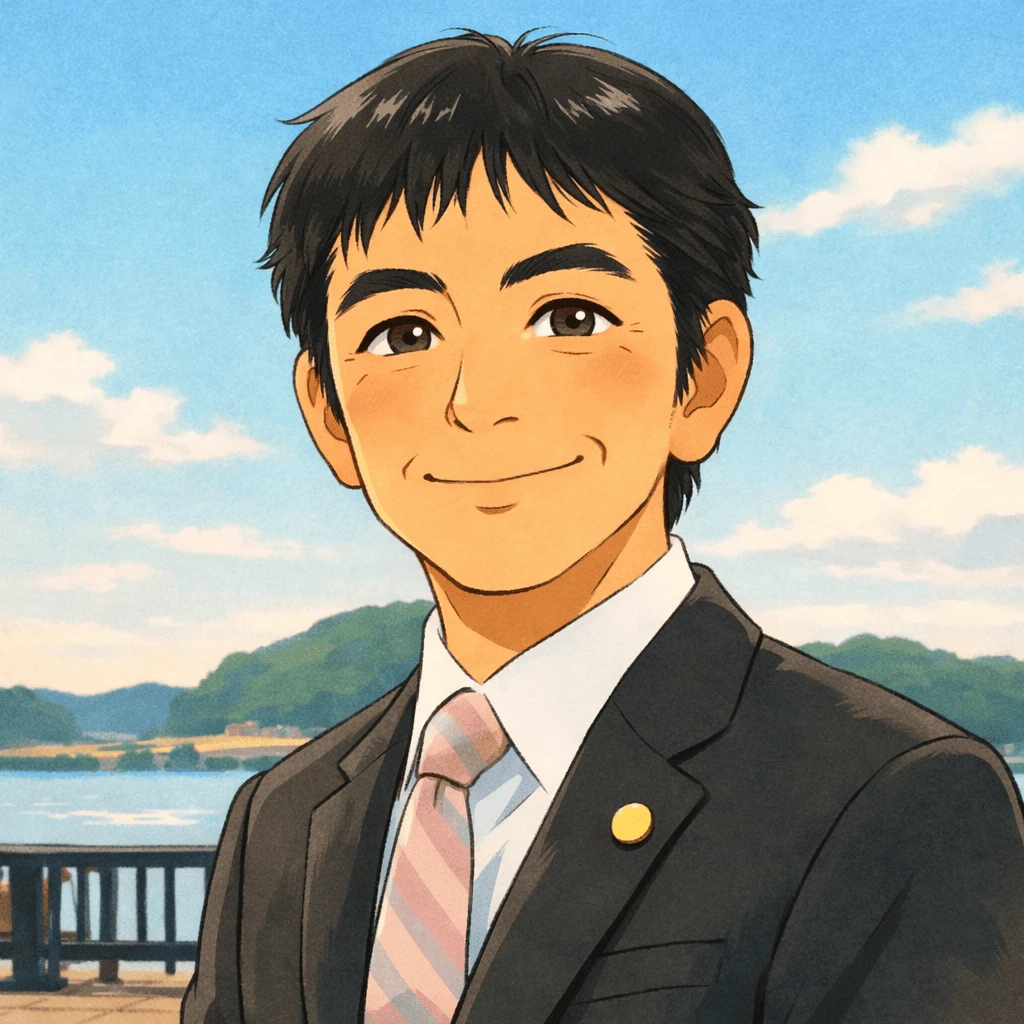
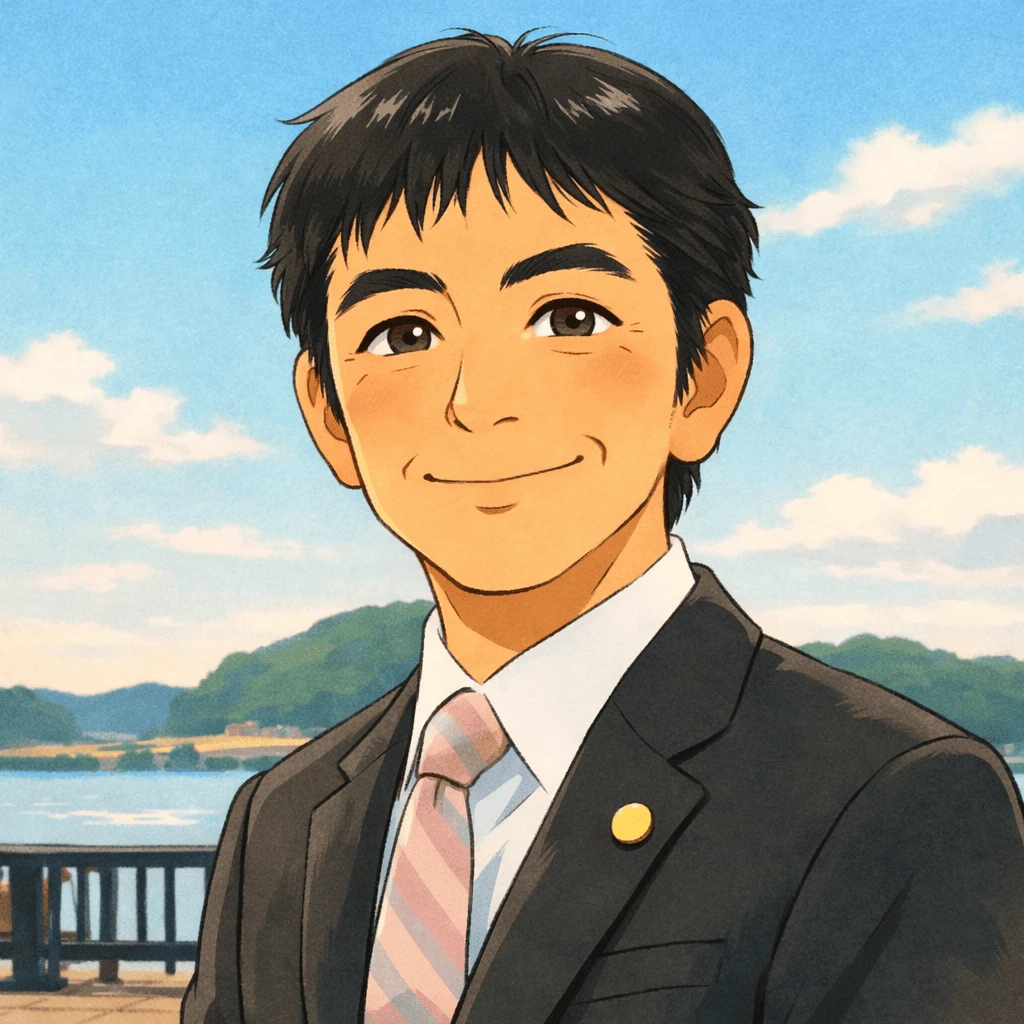
少額訴訟は「訴訟を提起した」という事実そのものが交渉力になります。訴状が届いた時点で相手方が態度を軟化させ、和解に応じるケースも多く見られます。
具体的な負担割合は、以下のガイドライン負担割合表で確認できます。
まとめ:少額訴訟の特徴を理解して退去費用トラブルに備えよう
少額訴訟は60万円以下の金銭トラブルを迅速かつ低コストで解決できる制度であり、退去費用の不当請求に対する有効な最終手段です。ただし、通常訴訟への移行リスクや控訴不可といった制約があるため、事前にメリット・デメリットを比較して判断することが大切です。
この記事のポイント
- 少額訴訟の基本と手続き
- 60万円以下の金銭トラブルを原則1回の審理で解決
- 弁護士なしでも手続き可能で費用は約1万円
- 訴状は裁判所の定型書式で作成できる
- 被告が通常訴訟への移行を申述できる点に注意
- 退去費用トラブルへの活用ポイント
- ガイドラインに反する不当請求が訴訟の対象
- まずは書面・内容証明での交渉を優先する
- 訴状送達の段階で和解に至るケースも多い
- 証拠書類の事前準備が勝敗を左右する
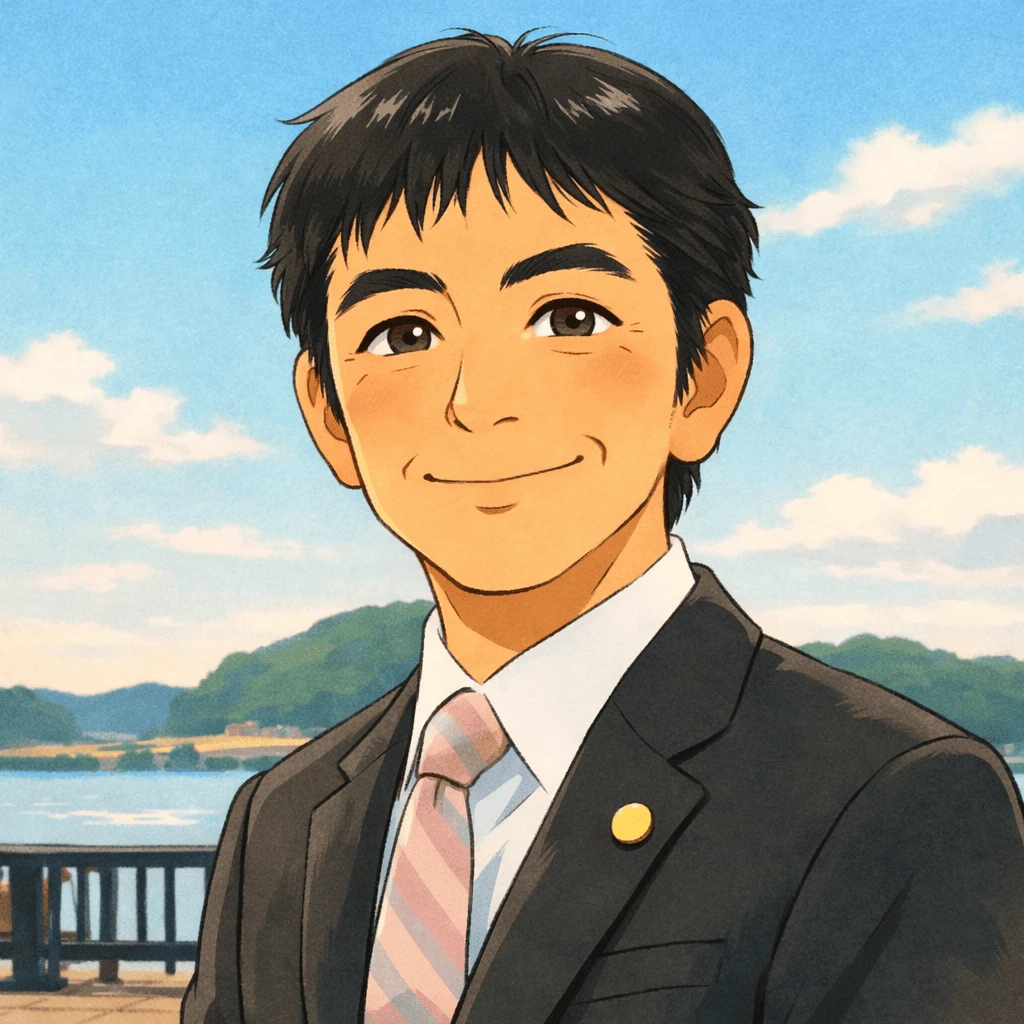
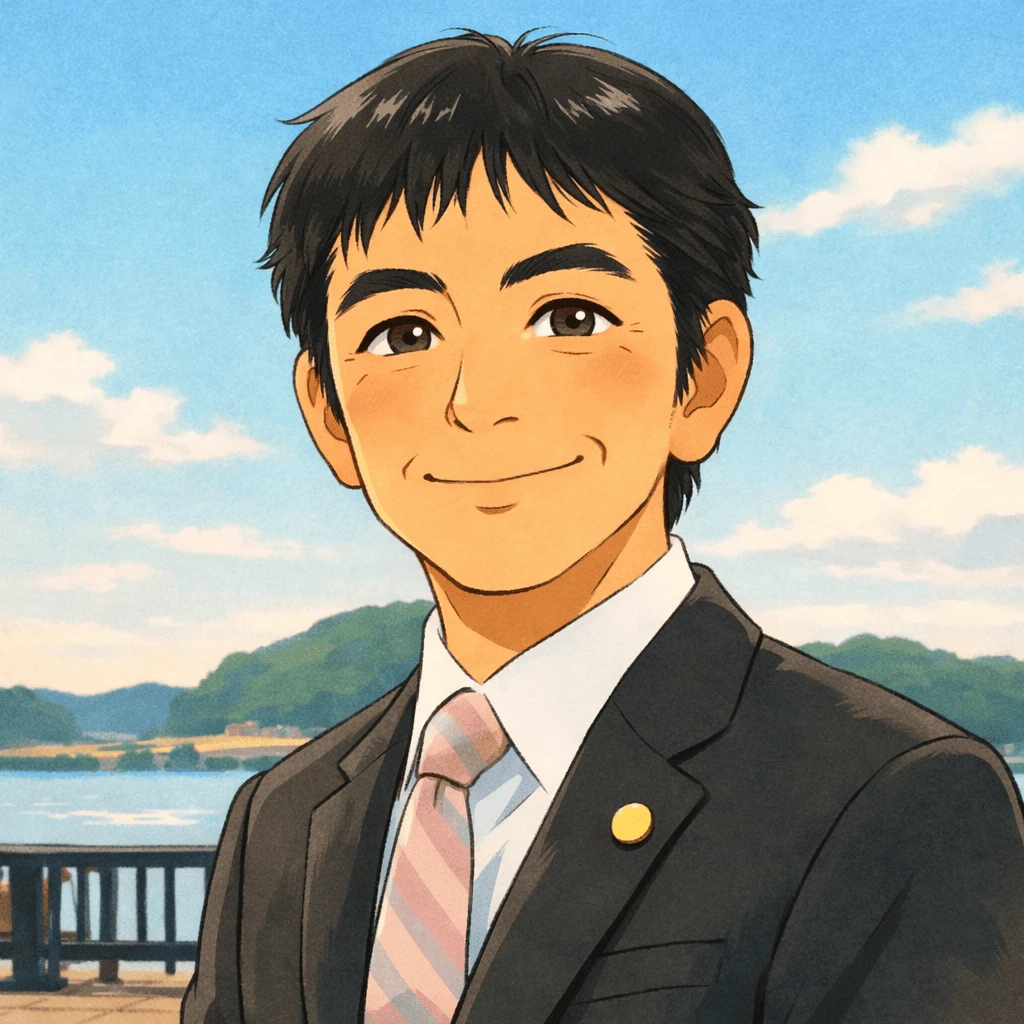
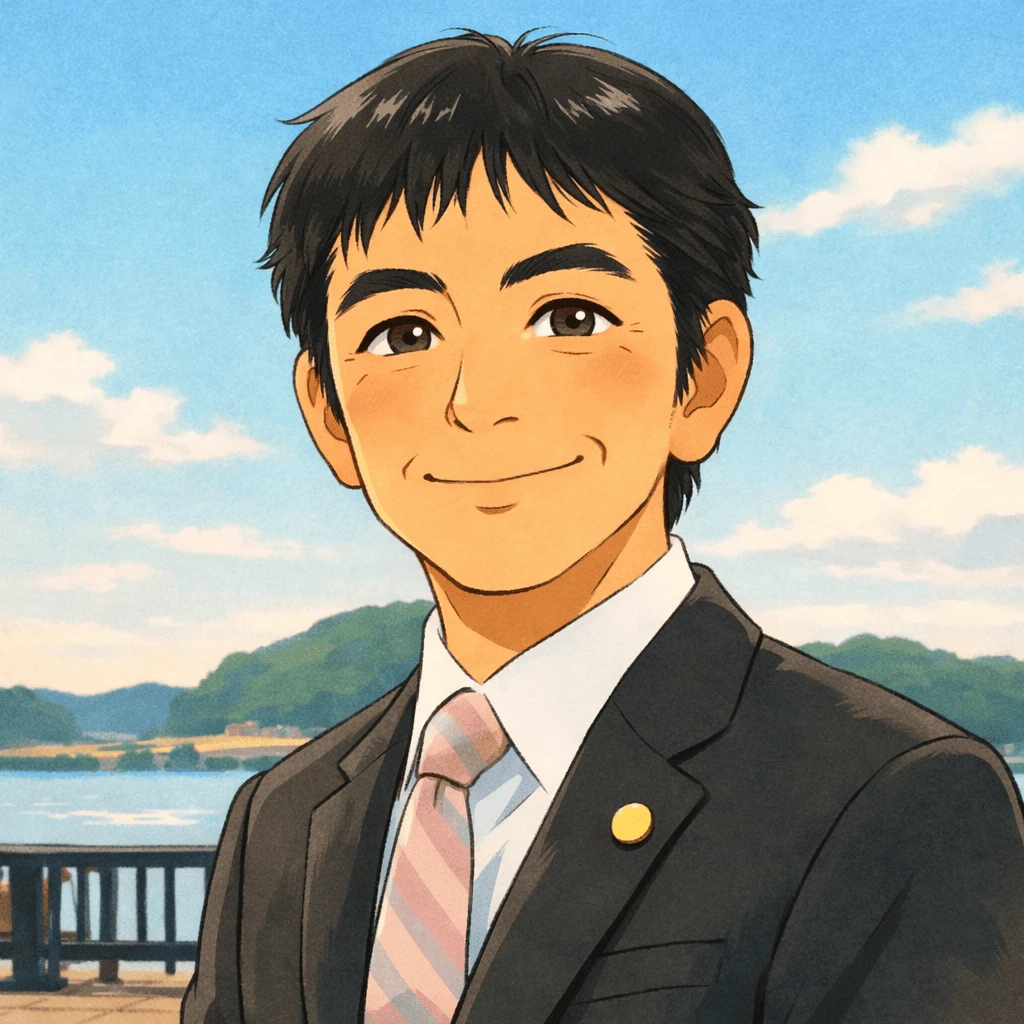
少額訴訟は退去費用トラブルの最終手段です。まずはガイドラインを根拠とした書面交渉、内容証明郵便の送付と段階的に進め、それでも解決しない場合に少額訴訟を検討してください。証拠書類をしっかり準備しておくことが成功の鍵です。
- 本記事は一般的な情報提供を目的としており、実際の退去手続きや費用負担については契約書・管理会社・貸主の案内を必ずご確認ください。
- 少額訴訟の手続きや費用は管轄する簡易裁判所により異なる場合があります。最新情報は裁判所のホームページでご確認ください。