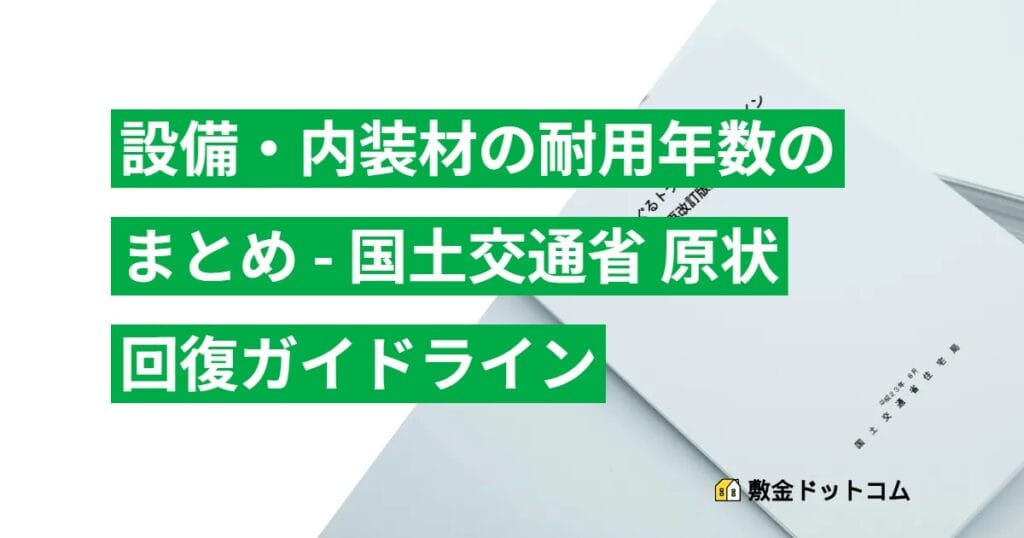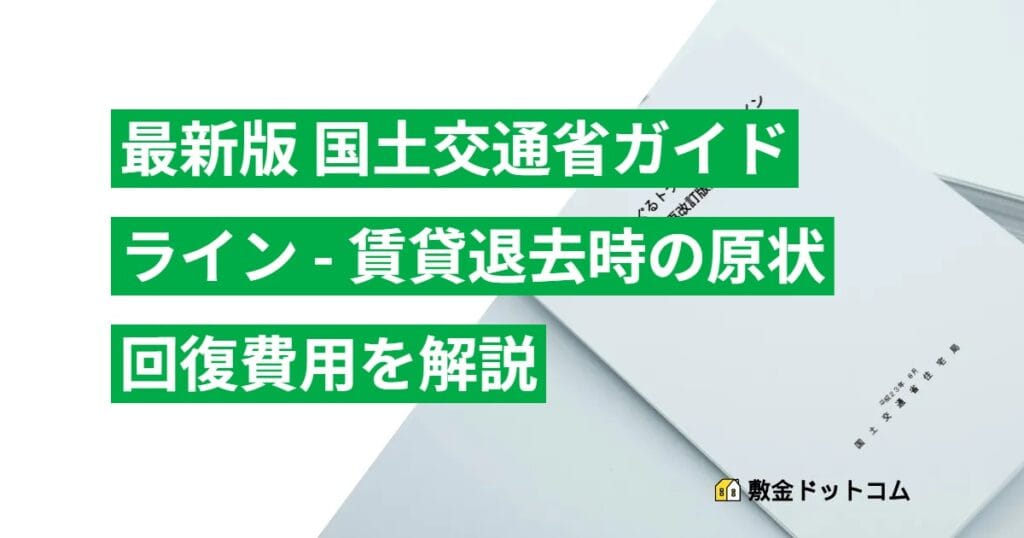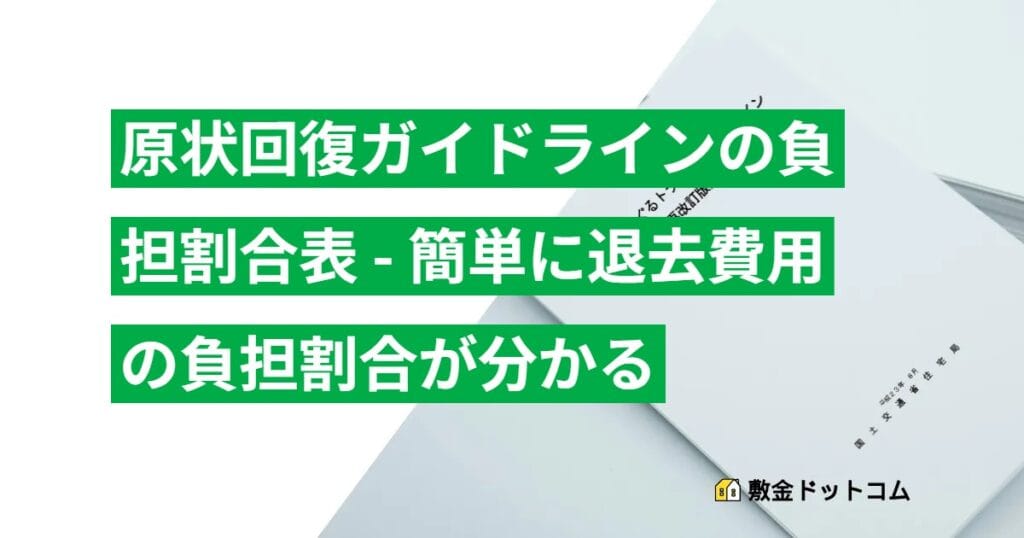原状回復ガイドライン– tag –
原状回復ガイドラインは、賃貸住宅の退去時における貸主・借主間のトラブルを防ぐため、国土交通省が策定した指針です。入居者の故意・過失による損耗と通常の使用による自然損耗を明確に区分し、借主が負担すべき修繕費用の範囲を具体的に示しています。例えば、壁の画鋲跡や家具設置による床の凹み跡は通常損耗として貸主負担となる一方、タバコのヤニ汚れやペットによる傷・臭いは借主負担となるケースが多くあります。ここでは、原状回復ガイドラインに関する記事をご覧いただけます。
-

【保証金返還の可否に関する判例】通常使用損耗でないため保証金返還なし
-

【敷引契約の消費者契約法適用に関する判例】敷引契約は消費者契約法10条違反せず
-

【違約金条項の消費者契約法適用に関する判例】違約金支払条項は消費者契約法10条違反
-

【定額控除特約の有効性に関する判例】通常損耗の定額控除特約は有効
-

【カビ汚れの費用負担に関する判例】カビは借主にも2割程度の負担
-

【毀損・汚損の損害賠償特約に関する判例】通常使用は特約対象外
-

【設備・内装材の耐用年数のまとめ】国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
-

【最新版 国土交通省ガイドライン】賃貸退去時の原状回復費用をわかりやすく解説
-

【原状回復ガイドラインの負担割合表】簡単に退去費用の負担割合が分かる